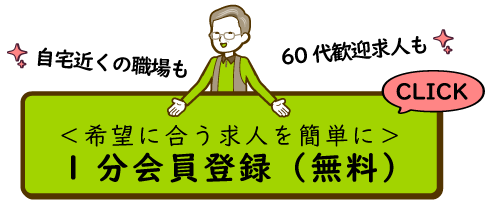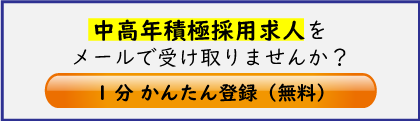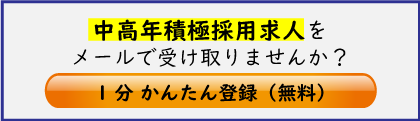申請すれば受給できる「加給年金」とは?もらえる条件や、申請方法を解説!
- ちょっと得する知識
- 公開日:2025年4月 3日

申請をすればもらえる加給年金。実は制度を知らずに受給できておらず、損をしている方も多いと言われています。そんな加給年金について、適用条件から手続きの流れまで詳しく解説します。
この記事の目次
加給年金とは、老齢厚生年金に追加される年金のこと
加給年金とは、厚生年金の被保険者が65歳に達した際、配偶者や子どもなどを扶養している場合に老齢厚生年金に追加される年金のことです。
65歳を迎え定年に達しても、扶養している親族がいる場合には扶養家族の生活費等の経済的負担が大きいことから、扶養手当の役割を担う加給年金が設けられました。ただし、受給するためには一定の条件が必要となり、配偶者や子どもを扶養しているからといっても必ず受け取れるものではありません。
また、加給年金の受給対象は主に、厚生年金の受給資格がある会社員や公務員となります。自営業者やフリーランスなどの厚生年金への加入資格がない人でも、過去に厚生年金加入期間が条件を満たす場合には加給年金の対象となりますので、予めご自身が対象であるかを確認しておく必要があります。
厚生労働省の人口動態統計によると、初婚夫婦の年齢差割合は夫が年上の場合がおよそ55%、妻が年上の場合はおよそ25%、そして同い年の夫婦は約20%といいます。つまり、歳の差がある夫婦が大半となっている現在、扶養する側が先に定年を迎えることは当たり前になってきているとも言えます。
加給年金の受給額は、配偶者の生年月日によって計算されます。年齢が若くなるにつれて減額される仕組みが取られており、子どもの場合は2人目までは年間約23万円、3人目からは年間約8万円が支給されるとのこと。
65歳で定年退職をする方にとって扶養する家族がいることは、今後の生活に一抹の不安を抱えてしまうことにもなりかねません。そのような場合、加給年金は家計の強い味方となってくれる制度と言えます。
データ元:日本年金機構「加給年金額と振替加算」、e-Stat「人口動態調査」
加給年金の条件とは?

では、続いて加給年金の具体的な受給条件をみていきましょう。
日本年金機構によれば、加給年金は"厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が65歳到達時点で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算される"との説明があり、加給年金の判定のタイミングは在職時の改定時点や退職時の改定時点となります。
加給年金が加算される受給条件は以下の通りです。
・厚生年金の加入期間が20年以上、または共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の加入期間が40歳以降に15年から19年以上ある
・厚生年金の受給者が65歳になるか、あるいは定額部分支給が始まる時点で、配偶者や子どもがいる
さらに、加給年金の対象となる配偶者や子どもにも以下の条件があります。
・被保険者が生計を維持している配偶者で、65歳未満
・被保険者が生計を維持している18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満かつ1級・2級の障害がある子
この加給年金の対象には戸籍上の配偶者だけでなく、事実婚のパートナーも含まれます。なお、配偶者や子どもに一定以上の所得があると、加給年金の対象から外れてしまうので注意が必要です。
「生計を維持している」とは?
受給条件となっている「生計を維持している」とは、一般的には共に暮らしていることが求められます。さらに、別居の場合でも仕送りを行っていたり、健康保険の扶養親族であったりすれば「生計を維持している」と認められます。
加給年金の手続きはどこで行えばいい?
条件を満たせば加給年金の受給ができることがわかりました。では、手続きはどのように進めたらいいのでしょうか。
加給年金は条件を満たしていれば自動的に加算されるものではなく、申請手続きが必要となります。対象者であるにも関わらず、申請を怠ってしまったが故に、加給年金を受給できない場合もありますので注意しておきましょう。
申請には以下の必要な書類があります。慌てないためにも、事前に準備しておくようにしましょう。
・年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)
受給開始年齢到達の約3カ月前に日本年金機構から郵送で送られます。また、日本年金機構の公式ホームページから印刷することも可能です。
・厚生年金受給者の戸籍謄本(記載事項証明書)
年金の受給者と、対象となる配偶者や子どもとの関係を証明するための書類です。
・世帯全員分の住民票の写し
年金の受給者と、対象となる配偶者や子どもの生計が同じかどうかを確認するための書類です。
・対象となる配偶者、子どもの所得を証明する書類(所得証明書、非課税証明書)
加給年金の支給対象となる配偶者や子どもが、厚生年金受給者により生活を経済的に支えられていることを確認するための書類です。
そして、上記の書類を準備した後は最寄りの年金事務所か年金相談センターに提出します。「加給年金」について疑問や相談がある方は、最寄りの年金事務所や年金の相談窓口である「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)に問い合わせてみるのもおすすめです。
手続きを忘れてしまったら?
加給年金は、手続きをしなければ受け取ることができません。もし、手続きを忘れてしまっても5年前までは遡って請求することができます。しかし、5年以上が経過してしまうとそれもできなくなるので注意が必要となります。
データ元:日本年金機構「電話での年金相談窓口」
加給年金の支給が停止する場合とは?

これまでは申請の仕方や受給条件に触れてきました。では、いざ受給が始まった後に受給対象から外れた場合はどうなるのでしょうか。
加給年金は、該当する配偶者や子どもが条件を満たさなくなると、支給が停止されます。主な支給停止条件は以下の通りです。
・子どもが18歳に達した年度の末日を迎えた場合
・「生計を維持」の条件を満たさなくなった場合
・配偶者が老齢厚生年金(または退職共済年金)の受給権が生じた場合
・配偶者が障害年金を受給している場合
加給年金が終了する際には、必要な手続きがある場合もあります。「もしかして加給年金の対象から外れるのでは?」と思った方は一度、年金ダイヤルや最寄りの年金事務所への問い合わせを検討してみましょう。
加給年金の注意点とは?
申請をしっかりすれば受け取れる、加給年金。では、受け取る際にはどのような注意点があるのでしょうか。
繰り下げ受給をした場合は受け取れない
年金の繰り下げ受給をした場合は、繰り下げた期間の加給年金は受取れなくなります。老齢年金は、受給を繰り下げることによって繰り下げた期間に応じて年金を増額して受け取ることができます。しかし、加給年金は増額の対象になっていません。繰り下げた期間の加給年金を、後から受取ることはできないことを覚えておきましょう。
厚生年金が全額支給停止の場合
厚生年金が全額支給停止となる場合は加給年金も受取れません。厚生年金保険に加入しながら年金を受給する場合、賃金と年金額に応じて在職老齢年金の一部または全部が支給停止される場合があります。厚生年金が全額支給停止となる場合には、加給年金も受取れなくなりますので注意が必要です。
加給年金額対象者が亡くなったときや離婚したとき
加給年金額対象者の方が亡くなったとき又は離婚したときは、翌月から加給年金額は加算されず、届出が必要となります。また、届出が遅れると支払い過多となった年金額を後日返還しなければならなくなりますので、注意しておきましょう。
まとめ
65歳を過ぎても扶養親族がいる場合に受給ができる、加給年金。扶養家族がいれば自動で受給できるわけではないため、支給条件を確認し対象となる方は忘れずに申請をしましょう。