生命保険料控除とは?計算方法や受ける時の注意点を解説
- ちょっと得する知識
- 公開日:2025年3月 7日

年末調整や確定申告の際に、生命保険料控除について目にすることもあるでしょう。今回は、生命保険料控除の基本から計算の仕方、生命保険料控除を利用する際の注意点などを解説します。生命保険に加入している人はもちろん、加入を検討している人も、ぜひ一度ご確認ください。
この記事の目次
生命保険料控除で、所得税や住民税の負担が軽くなる
生命保険料控除とは、生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つの保険料を支払っている納税者に適用される所得控除の1つです。支払った保険料によって、一定金額がその年の所得から差し引かれるため、所得税や住民税の負担が軽くなります。
生命保険は任意加入のため、全員が控除を受けられるわけではありません。しかし、加入している人は税額負担が軽くなる機会ですので、忘れずに申請を行いましょう。
生命保険料控除の新制度と旧制度の違い
生命保険料控除には、新制度と旧制度の2つがあります。旧制度は2011年12月31日より以前に契約した生命保険に対して適用され、新制度は2012年1月1日以降に契約した生命保険に対して適用されます。
それぞれの違いや変更点を理解して、生命保険料控除を利用しましょう。
生命保険料控除の旧制度
生命保険料控除の旧制度は、控除区分が一般生命保険料と個人年金保険料の2つです。それぞれの控除額は所得税が5万円まで、住民税が3万5000円までとなります。各控除を利用した場合、合計で所得税が10万円、住民税が7万円です。
生命保険料控除の新制度
2012年1月1日以降に加入した生命保険に適用される新制度では、介護医療保険料が増設され、一般生命保険料と個人年金保険料、介護医療保険料の3つの控除区分となりました。それぞれの所得税の控除額は4万円まで、住民税は2万8000円までで、合計額は所得税が12万円、住民税は7万円です。全体の控除額は、旧制度よりも2万円アップしています。
また、生命保険の契約が2011年12月31日以前でも、2012年1月1日以降に更新や特約の中途付加などを行った場合は、新制度が適用されます。自身の生命保険契約は、新制度と旧制度のどちらが適用されるかわからない場合は、生命保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書で確認しましょう。
生命保険料控除の対象となる保険商品
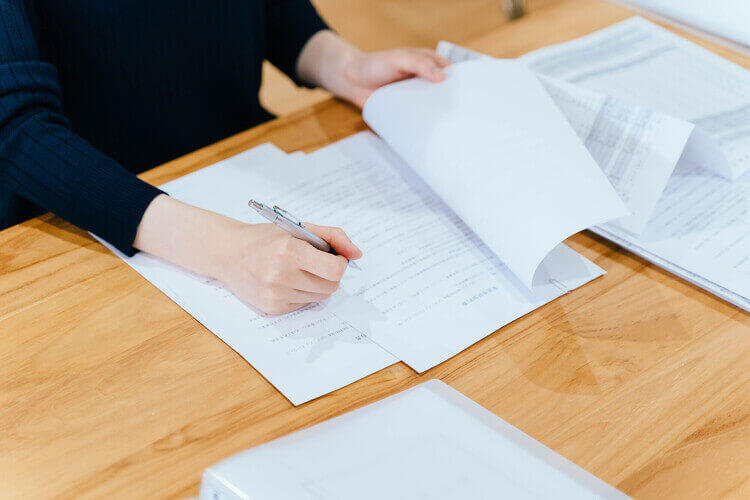
生命保険料控除の対象となるのは、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料の3つです。基本的には、下記のような保険が生命保険料控除の対象です。
| 控除区分 | 対象保険商品 |
|---|---|
| 一般生命保険料 | 定期保険・収入保障保険・終身保険・学資保険など |
| 介護医療保険料 | 医療保険・がん保険・介護保険など |
| 個人年金保険料 | 個人年金保険など |
生命保険料控除の対象となる条件
一般生命保険料
生命保険会社や外国生命保険会社等、損害保険会社または外国損害保険会社等と締結した身体の疾病または身体の傷害、その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われるものが対象です。
介護医療保険料
疾病または身体の傷害、その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約または生命共済契約等のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるものが対象です。
個人年金保険料
年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であることや、年金の支払は年金受取人の年齢が原則として、満60歳になってから支払うとされている、10年以上の定期または終身の年金であることが条件です。さらに、被保険者等の重度の障害を原因として、年金の支払いを開始する10年以上の定期年金または終身年金であるものも対象となります。
参照元:国税庁 生命保険料控除の対象となる保険契約等
生命保険料控除の申請方法や必要書類
生命保険料控除を申請する場合、会社員か自営業者かで方法が異なります。また、必要な書類も人によって異なるため、事前に確認をしましょう。
会社員の場合
会社員の場合は年末調整にて、生命保険料控除を受けられます。会社から年末調整の書類が配布された際に、必要事項を記入し、生命保険料控除証明書を提出すれば問題ありません。ただし、年収が2,000万円以上の人は年末調整を受けられないため、自身で確定申告を行う必要があります。
自営業者の場合
自営業者の場合や、年収2,000万円以上など会社での年末調整が利用できない人は、確定申告で生命保険料控除の手続きを行う必要があります。確定申告は2月16日から3月15日の間に、所得税の確定申告で証明書を添付して提出します。e-taxで確定申告をした場合は、証明書の添付省略が可能です。
必要書類
生命保険料控除を受ける際に必要な書類は、2つです。会社員で年末調整を受ける場合は、保険料控除申請書と、生命保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書を一緒に提出します。もし、自身で確定申告を行う場合は、確定申告書類と生命保険料控除証明書の2つです。
保険料控除申請書には、以下のような内容を確認や記入をして、提出を行います。
• 保険会社の名前
• 保険の種類
• 保険期間または年金支払期間
• 契約者の氏名
• 保険金の受取人
• 新旧の区分
• 本年中に支払った保険料の金額
• 保険料の合計額
• 控除額
内容に間違いがないか確認したうえで、勤務先または税務署へ期間までに提出しましょう。
生命保険料控除の計算方法
生命保険料控除の額は、1年間で支払った保険料を、計算式に当てはめて算出します。新制度と旧制度で金額が変わるため、それぞれの計算方法をご紹介します。
新制度の控除額の計算方法
新制度の場合は、最大で所得税4万円、住民税2万8000円の控除を受けられます。新制度の控除額の金額と計算方法は以下の表の通りです。
▼所得税の控除額 計算方法
| 年間支払保険料額 | 控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 支払保険料全額 |
| 2万円超4万円以下 | 支払保険料×2分の1+1万円 |
| 4万円超8万円以下 | 支払保険料×4分の1+2万円 |
| 8万円超 | 一律4万円 |
▼住民税の控除額 計算方法
| 年間支払保険料額 | 控除額 |
|---|---|
| 1万2,000円以下 | 支払保険料全額 |
| 1万2,000円超3万2,000円以下 | 支払保険料×2分の1+6,000円 |
| 3万2,000円超5万6,000円以下 | 支払保険料×4分の1+1万4,000円 |
| 5万6,000円超 | 一律2万8,000円 |
旧制度の控除額の計算方法
続いて、旧制度の控除額の計算方法について、ご紹介します。旧制度の所得税控除額は、以下の通りです。
▼所得税の控除額 計算方法
| 年間支払保険料額 | 控除額 |
|---|---|
| 2万5,000円以下 | 支払保険料全額 |
| 2万5,000円超5万円以下 | 支払保険料×2分の1+1万2,500円 |
| 5万円超10万円以下 | 支払保険料×4分の1+2万5,000円 |
| 10万円超 | 一律5万円 |
▼住民税の控除額 計算方法
| 年間支払保険料額 | 控除額 |
|---|---|
| 1万5,000円以下 | 支払保険料全額 |
| 1万5,000円超4万円以下 | 支払保険料×2分の1+7,500円 |
| 4万円超7万円以下 | 支払保険料×4分の1+1万7,500円 |
| 7万円超 | 一律3万5,000円 |
控除額が気になる人は、自身の保険料額を確認して計算してみましょう。
生命保険料控除のシミュレーション

実際に生命保険料控除をどの程度受けられるのか、シミュレーションをご紹介します。
今回は新制度のみが適用されており、一般生命保険料を年間10万円、介護医療保険料を年間7万円、個人年金保険料を年間12万円支払っている場合で見てみます。
| 所得税 | 住民税 | |
| 一般生命保険料控除 | 4万円 | 2万8,000円 |
| 介護医療保険料控除 | 3万7,500円 | 2万8,000円 |
| 個人年金保険料控除 | 4万円 | 2万8,000円 |
| 控除額合計 | 11万7,500円 | 8万4,000円 |
この場合、住民税が8万4,000円ですが、上限額が7万円までのため、控除が受けられるのは7万円です。
生命保険料控除を受ける際の注意点
生命保険料控除を受ける際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。どういった点に気をつけておくべきか、事前に確認しておきましょう。
家族の生命保険料は、支払い方法によって控除を受ける人が変わる
生命保険を契約している人のなかには、家族の分の保険料を支払っている人もいるでしょう。夫が妻の分の保険料を支払っている場合、保険の契約名義が妻だったとしても、保険料を支払っている夫が、生命保険料控除を申告できます。
もし、妻の生命保険料を妻の口座から引き落としている場合は、払込をしているのが妻本人とされます。そのため、納税者である夫は生命保険料控除を受けられません。もし、妻が扶養の範囲内で働いていた場合は、配偶者控除が適用されるため、妻は生命保険料控除を受けられません。
保険料控除の申告を忘れたら確定申告を行う
もし、年末調整の際に生命保険料控除の申告を忘れた場合は、自身で確定申告を行う必要があります。ただし、早めに気づいた場合は会社に一度追加の申告を行いましょう。場合によっては、年末調整に間に合う可能性もあります。
時期的に年末調整に間に合わない場合は、自身で確定申告を行って控除を受けましょう。もし、確定申告で申告を忘れた場合でも、保険料を支払った年の翌年1月1日から5年以内に「所得税及び復興特別所得税の更生の請求書」を提出すれば、還付を受けられます。
控除証明書を紛失したらすぐ再発行
生命保険料控除の証明書は、自身が加入している保険会社から毎年秋頃に送付されます。そのまま、年末や確定申告の時期まで保管をしておく必要があるため、失くさないようにしましょう。もし紛失した場合は、すぐに再発行手続きを行います。急ぎで発行を依頼したい場合は、電子データでダウンロードできる場合もあるため、加入している保険会社に確認してください。
転職した場合は転職先で年末調整ができるか確認する
年の途中で転職をした場合は、転職先の企業で年末調整ができるか確認しましょう。特に秋頃に転職した場合、早い会社ではもう年末調整の手続きを終えている場合があります。転職した年のみ、自身で確定申告が必要となる可能性があるため、転職を検討している人や転職したての人は事前に確認しましょう。
また、転職先で年末調整するためには、前の職場の源泉徴収票が必要です。期日までに源泉徴収票が届きそうかなども、確認しておく必要があります。
生命保険料控除の対象外となる保険がある
生命保険料控除は、すべての生命保険が対象となるわけではありません。保険期間が五年未満の貯蓄型保険や財形保険、団体信用生命保険などは、生命保険料控除の対象外です。また、個人年金保険でも「個人年金保険料税制優遇適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般生命保険料になるといった場合もあります。
もし、死亡保障と介護・医療補償をかねた組込型保険に加入している場合は、法令などに基づき一定の条件を満たしている場合につき、介護医療保険料控除の対象となります。自身の加入している保険が生命保険料控除の対象となっているかはもちろん、どの控除区分に該当するのかを年末調整前までに確認しておきましょう。
まとめ
年末調整で受けられる、生命保険料控除についてご紹介しました。生命保険料控除は、生命保険に加入している人が、所得税や住民税の控除を受けられる制度の1つです。会社員の場合は年末調整で、自営業者の場合は確定申告の際に申告をすると、控除が受けられます。
生命保険料控除で控除される額は、適用される制度や控除区分によって異なります。まずは、生命保険の加入時期や商品がどの部分に該当するかを確認したうえで、控除額を計算しましょう。生命保険料控除を活用すれば、最大12万円の所得控除を受けられます。ぜひ、生命保険に加入している人は、申請を行いましょう。

























