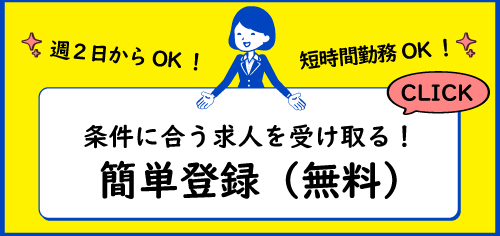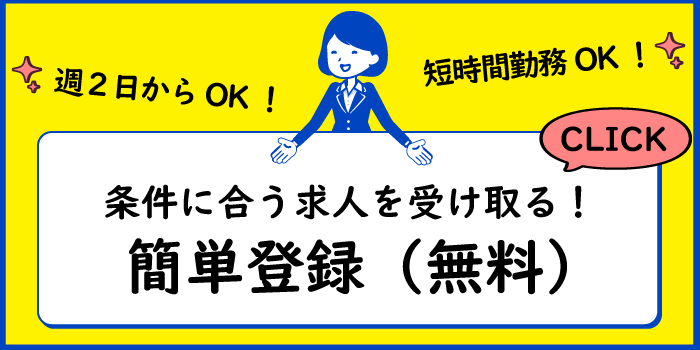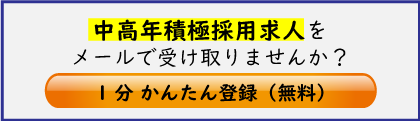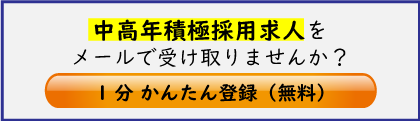2024年10月からの児童手当の制度改正で、一体何が変わる?受給条件や変更点を解説!
- ちょっと得する知識
- 公開日:2025年3月11日

令和6年10月から児童手当が制度改正されました。今回は、制度改正の背景や変更点、受給条件について解説します。児童手当を受けるには、市区町村への申請が必要です。自身が該当しているか、情報を確認しましょう。
この記事の目次
児童手当とは、児童を養育している方を対象に手当が支給される制度
2024年(令和6年)10月分より、児童手当の制度改正が行われました。
児童手当とは、生活の安定と次世代を担う子どもの健やかな成長に寄与することを目的に、児童を養育している方を対象に手当が支給される制度です。
今回の制度改正では少子化対策と子育て支援の拡充を目標に、総額約4兆円規模に及ぶ「こども・子育て支援加速化プラン」が取りまとめられました。そのうちのおよそ1兆円が児童手当をはじめとする給付に充てられることに。こども家庭庁の年間の予算総額の4分の1にあたることからも、その重要度の高さが窺いしれるでしょう。
従来も児童手当はありましたが、この制度改正ではこれまで以上に大幅な予算が組まれたというわけです。また、この財源は公的医療保険料などで確保される見込みで、子育て世帯以外も含む全世代で月額およそ500円程度を負担することとなっています。
日本では今、少子化は社会現象とも言えるほど深刻化しています。毎年の出生率を見ればわかるように、今後日本社会や日本経済を担う若者の減少は、国力低下を招きかねないと言わざるを得ません。こうした少子化の背景には、若者たちの経済的不安が関係していると考えられています。
そこで、止まらぬ少子化を抑止しようと岸田内閣下で「異次元の少子化対策」が発表されたのです。その中でも、今回の児童手当の支給額拡大は少子化にストップをかけられる支援制度として注目を集めています。
児童手当の受給条件は?
児童手当の受給資格をみていきましょう。原則として児童が日本に住んでいることが条件となりますが、留学をしている場合なども一定の要件を満たしていれば支給されます。
・日本の住所を有しなくなる前日までに、継続して3年以上国内の住所を有していた
・教育を目的として海外居住し、父母と同居していない
・日本の住所を有しなくなった日から、3年以内である
養護施設や里親に養育を委託している場合は、原則として父母ではなく施設の設置者または里親に支給されることになっています。児童手当を受給するためには、現在住んでいる市区町村への申請が必要です。
データ元:政府広報オンライン「2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を」、こども家庭庁「こども未来戦略 「加速化プラン3.6兆円」の施策詳細」
児童手当拡充で、これまでとどう変わる?

今回の改正で、どのような点に変更があったのでしょうか。
・支給対象年齢の変更
従来は中学卒業までが支給対象となっていましたが、令和6年10月からは高校卒業までに延長されました。つまり、18歳に達する日以降の最初の3月31日まで手当が支給されることに。この支給条件には高等学校に通っていることは必須となっていません。高校に通っていなくても、保護者と生計が同一であることなどを要件に「18歳の誕生日を迎えた最初の3月31日まで」支給されることになります。
さらに、会社員やアルバイトとして社会に出ていても、生計が同じで保護者が子どもを養育していれば支給要件を満たしていることになります。ただし、子どもが一人暮らしをして自分の給料だけで生活している場合は、独立しているとみなされて支給対象外です。
・所得制限の撤廃
これまでの児童手当にはこどもが2人と配偶者の年収が103万円以下の場合で、主たる生計者の年収が960万円以上のケースなどは受給に制限が設けられていました。しかし、今回の制度改正では所得制限は設けられず、全家庭に支給されることとなりました。所得制限を設けることは児童手当の「すべての子どもの成長を支える」という趣旨から外れていると判断し、所得制限の撤廃が行われたといいます。
・支給回数の変更
従来の児童手当は年3回の支給でしたが、隔月(偶数月)の年6回に増やされました。2024年12月の支給分から開始予定となっています。4か月ごとに年3回の支給より、2か月分ずつ年6回の支給にすることで、家庭での児童手当の積極的な活用が期待されています。
・第3子以降の手当を拡充
令和6年10月からは、3人目以降の子どもがいる世帯に対しては、1人あたり月3万円の児童手当が支給されることになります。子供が多い世帯の経済的な負担を減らし、より手厚い支援を行うことで、少子化問題に直接的にアプローチしようと考えられたためです。これにより、経済的理由から3人目の子どもを諦めるしかなかった方にも日本で安心して子育てをしてもらおうという訳です。
▼〈従来の児童手当(1人あたり月額)〉
| 3歳未満 | 15,000円 |
|---|---|
| 3歳以上小学校修了まで | 10,000円 |
| 中学生 | 10,000円 |
(※所得制限限度額以上:5,000円)
▼〈令和6年からの児童手当(1人当たり)〉
| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
|---|---|
| 3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
児童手当は拡充したのに、扶養控除は縮小する?
2024年10月からは所得制限もなく、高校生年代までは月1万円、第3子以降の児童は3万円へ支給額が拡大されます。このように一見、子育て世代にとってメリットが多いかと思われますが、扶養控除は縮小されることを覚えておきましょう。扶養控除とは、養っている親族がいる人が受けられる所得控除のことです。
所得控除とは、所得からある決まった額を差し引いて、税金がかかる所得額を減らすことを指します。従来では高校生の子どもを扶養している親は、扶養控除によって所得税の計算の元となる所得を年間38万円、住民税の計算の元となる所得を年間33万円差し引くことができるとされていました。
ところが、16~18歳の子どもを1人養う場合に適用されている扶養控除額を所得税については38万円から25万円に縮小し、住民税については33万円から12万円に縮小すると決定されたのです。
扶養控除額縮小は、所得税は令和8年分から、住民税は令和9年度分から始まる予定となっており、令和8年以降から扶養控除の縮小によって所得税・住民税は実質増税となります。児童手当の拡充の一方で、高校生に対する扶養控除が縮小されてしまうのでは、税金は増えるから意味がないのではないか、といった声も上がっています。
高校生を養育する家庭にとって、毎月1万円の児童手当が支給されるようになったとしても、扶養控除が縮小されるとその分支払う税金が増えます。児童手当の増加分である年間12万円よりも、扶養控除の縮小に伴い増えた税金の金額のほうが大きい場合、結局手取りが減って損をしてしまうと言えるでしょう。
ただし、一般的な会社員の年収(400~500万円程度)の場合であれば、損をしてしまうことはありません。扶養控除は所得控除の一種です。所得控除とは、収入から経費を引いた後の所得額から差し引かれるものです。そして、差し引かれた金額に税率をかけた金額を、所得税や住民税として支払います。つまり、扶養控除の金額そのものが支払う必要のある税金から減るわけではないということです。
課税される所得金額が500万円の場合の所得税率は20%、住民税は10%ですので、一般的な収入の会社員の場合、今回の制度変更で損をすることはないと言えるでしょう。
では、より具体的な数字に落とし込んで考えてみましょう。
〈条件〉
・世帯主が都内在住の年収500万円の会社員
・妻は専業主婦
・子どもは1人で、年齢は16歳(高校生年代)
〈改正前〉
所得税:13万4500円
住民税:25万2000円
児童手当:0円
手取り額(収入500万円-税額+児童手当):461万3500円
〈改正後〉
所得税:14万7500円
住民税:27万3000円
児童手当:年12万円
手取り額(収入500万円-税額+児童手当):463万9500円
このように年間の手取り収入で比較してみると、改正後のほうが2万円以上増える計算です。扶養控除の控除額減少は一見痛手に見えますが、それ以上に児童手当の拡充が大きく影響し、実質の手取り額が増えるようですね。扶養控除の改正は金額が減少するため、一見すると家計に響いてしまうと見られがちですが、児童手当の拡充により改正後、一般的な家庭では、手取り金額が増えることとなります。
ひとり親控除とは
今回の制度改正では様々な変更点があります。例えば、ひとり親控除もその一つでしょう。
年間の課税所得が500万円までのひとり親を対象に、所得税の課税対象から35万円を差し引いていましたが、今後は所得の制限を1000万円まで引き上げた上で、控除額も38万円に拡大することが決定しています。
対象の方は申請をお忘れなく!

支給期間の延長や所得制限の撤廃などによる今回の制度改正では、児童手当の支給対象者が拡大されることになります。該当する方は、市区町村への申請が必要になりますので忘れないようにしましょう。
日本ではこれまでにも子どもに対する経済的な支援は設けられてきました。しかし、2024年度のこども家庭庁予算案においては前年度に比べてさらに9.8%の増額を行っています。さらに、ひとり親世帯向けの児童手当も所得制限の引き上げを行うことにより、多くの世帯で受給できるようになりました。その背景には少子化の深刻な問題があると言われています。
日本の人口は、2008年の1億2,809万人をピークに、減少傾向にあります。国立社会保障・人口問題研究所の全国の将来推計人口では、少産多死が進むことで、2040~60年代には毎年100万人の人口が減っていくことが示されています。このように、今後の日本を担う若者の母数が減ること自体が日本の国力低下に直結してしまうと考えられます。
実際に、1才6カ月までの子どもをもつ母親の7割超が「日本の社会は、出産・子育てがしにくい」と回答しているといいます。また、出産・育児がしにくいと思う理由としては、「経済的・金銭的な負担が大きいから」が最も多かったとのだとか。つまり、経済的・金銭的な負担が大きいために出産や育児に支障をきたしているというのが今の日本の現状であると言えます。
そこで、政府は児童手当のような経済的な支援の他に、保育士の配置基準も変更し、今後は保育士への人件費を669億円増やす方針です。また、放課後に預ける学童保育職員の人件費も228億円増やすなど、多角的で積極的な少子化対策に取り組んでいます。今後、日本は出生率を上げるためにも児童手当のような経済拡充をしていく必要に迫られているのです。
データ元:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」、株式会社ベネッセコーポレーション「たまひよ妊娠・出産白書」
まとめ
2024年10月から制度改正された、児童手当。子育て世代にとって少しでも経済的な負担を減らし、子育てしやすい環境づくりの第一歩、そして少子化の歯止めになることを期待したいですね。