2025年(令和6年分)の確定申告の変更点は?定額減税などの注意点も解説!
- ちょっと得する知識
- 公開日:2025年2月27日
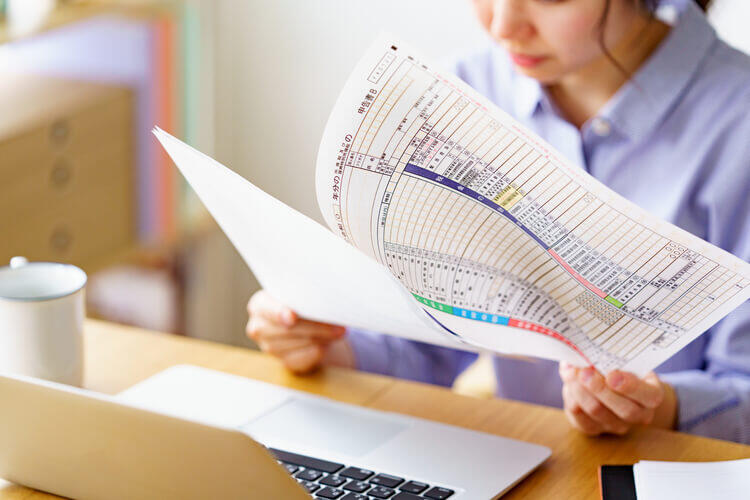
2025年(令和6年度)の確定申告には、いくつか変更点があります。今回は、確定申告の基本情報から、定額減税を含む変更ポイントを解説します。抜け漏れなく申告を行えるよう、事前に情報をチェックしてみましょう。
この記事の目次
確定申告の対象となる人・お金
確定申告をする必要があるのか、どんなお金を申告するのかについても、簡単にご紹介します。申請漏れのないよう、確認しましょう。
確定申告が必要な人
確定申告が必要なのは、以下の条件に該当する人です。
• 個人事業主やフリーランスなどで所得が48万円を超える人
• 年収2,000万円以上の会社員
• 副業で年間20万円以上の収入がある人
• 医療費控除を申請する人や初めて住宅ローン減税を利用する人
確定申告の対象となるお金
確定申告は、1月1日〜12月31日に発生した所得について行います。個人事業主の場合は、その年の1月1日〜12月31日に発生した売り上げが対象です。また、会社員でも株式投資で得た利益や不動産によって得た所得などは、確定申告が必要となります。そのほか、2箇所以上の会社から給与を得ている人なども、確定申告が必要です。
2025年(令和6年度)の確定申告 6つの変更点

今回の2025年(令和6年度)の確定申告では、6つの変更点があります。どのような変更があるのか、どういった対応が必要となるのか、ぜひ申告前にご確認ください。
①定額減税欄の追加
2024年6月に、急な物価高による家計の負担を軽減するために行われた「定額減税」の記入欄が追加されています。定額減税は、納税者とその扶養親族の人数によって計算された定額減税分を、令和6年度の住民税や所得税から差し引く制度です。
納税者本人は所得税3万円・住民税1万円、扶養親族は1人につき所得税3万円・住民税1万円が減税されます。確定申告書内第一表の「税金の計算」「44」と「45」欄に、人数や計算結果の金額を記入します。
• 44欄:特別税額控除(3万円×人数)を記入
• 45欄:所得金額から44欄の金額を差し引く
同一生計配偶者や扶養親族の定額減税を受けるためには、人数分の氏名や生年月日、マイナンバー情報などを、確定申告の第二表に記載します。もし、定額減税で所得税額から控除しきれない金額がある場合は、給付金が市区町村から支払われます。
確定申告を前に、定額減税がしきれないと見込まれている場合は、事前に給付が行われています。また、所得税額と定額減税額が確定した後に、当初給付額に不足金額があるとわかった場合は、追加支給も行われる予定です。
➁所得金額調整控除の記入方法変更
所得金額調整控除の適用がある人で、一定の条件を満たす人は第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄の「その他」の欄に「1」を記入する方法に変更となりました。なお、定額減税の対象となる配偶者や扶養親族の場合は「2」を記入します。
以下の条件にすべて該当する場合は「1」を記入する
• 所得金額調整控除額がある
• 配偶者が他の納税者の扶養家族となっている
• 配偶者が配偶者(特別)控除ではなく、かつ、特別障害者である
扶養親族の場合は、以下の通り
• 所得金額調整控除額がある
• 扶養親族が他の納税者の扶養親族又は同一生計者
• 扶養親族が納税者自身の扶養控除又は障害者控除の対象とならない扶養親族であり、かつ、特別障害者又は23歳未満
所得金額調整控除は、給与所得者のみが利用できる所得控除のため、個人事業主などの場合は該当しません。
➂子育て世代等の住宅ローン減税拡充に伴う項目追加
住宅ローン減税や子育て対応のリフォームを行う場合に、借入限度額を上乗せして、上限額が維持される措置が設けられました。対象者は令和6年12月末時点で、以下のいずれかに該当する特例対象個人です。
• 年齢が40歳未満、かつ、配偶者を有する人
• 年齢が40歳以上、かつ、年齢が40歳未満の配偶者を有する人
• 年齢が19歳未満の扶養親族を有する人
特例対象個人に該当する場合は、確定申告第二表への記載が必要です。確定申告第二表の「配偶者や親族に関する事項欄」に追加された「住宅」欄に丸をつけます。
④スマホ用電子証明書スタート
2024年より、スマホ用の電子証明書が導入されました。従来、確定申告をスマホで行う場合は、その都度スマホでマイナンバーカードを読み取る必要がありました。しかし、スマホ用電子証明書によって、今後は一度の読み取りのみでスムーズに手続きが行えるようになります。現在はAndroidのみが対応していますが、今後iOSも対応となるでしょう。
⑤確定申告書作成コーナーのスマホ対応
国税庁が運営している確定申告書作成コーナーが、2025年1月からスマホにも対応となります。これまでは、パソコンでしか作成できなかったため、パソコンを持っていない人は手書きで作成する必要がありました。
しかし、スマホ対応が始まったため、パソコンは持っていないがスマホはあるという人も手軽に申告ができるようになります。また、パソコン画面も操作性を向上させるために、デザインが変更される予定です。
⑥収受日付印の廃止
確定申告の書類を税務署へ紙で提出していた場合、収受日付印の捺印がされていましたが、今回の確定申告より廃止となります。このため、提出した日付や税務署の管理については、自身で行う必要があります。収受印の廃止は、電子申告などによって税務署に行かずに申告ができる社会を作るためです。
申告書の提出状況を確認する際は、e-taxの申告書等情報取得サービスを利用するか、交付請求などを行いましょう。なお、当面は希望者向けに申告時の日付と税務署名を記載した、リーフレットが交付されます。
確定申告の流れ
確定申告の流れをご紹介します。書類を作成した後、どうやって提出するのか、納付方法などをご紹介していますので、ぜひ提出前にご確認ください。
確定申告に必要なもの
確定申告を行う際に必要なものは、以下の通りです。
• 確定申告書類
• 本人確認書類
• 所得金額がわかるもの
• 控除に必要な書類
e-taxで申告を行う場合は、確定申告書類を紙で用意する必要はありません。また、本人確認書類はマイナンバーカードなど、個人番号が記載されたものが必要です。そのほか、青色申告決算書や、控除を受けるために送られてくる書類などが必要となります。人によって必要となる書類の種類や数が異なるため、書類を作成する前に全部揃っているか確認しましょう。
確定申告の提出方法
確定申告書類の提出方法は、以下の3つです。
税務署の窓口
窓口は、平日の8時30分〜17時が受付時間です。直接職員に確定申告に関する相談ができるのは、窓口提出のメリットです。しかし、土日祝日は閉まっているため、相談や検算の利用は平日に訪れる必要があります。
郵送
郵送は締切日(2025年は3月17日)の消印であれば、期限内の提出とみなされます。書類で提出したいが、税務署に行けないといった場合は郵送で提出しましょう。ただし、2025年3月17日に投函しても、投函時間によっては消印が2025年3月18日になる場合があります。消印が期限を過ぎていると、期限後申告となり延滞税などの対象となる可能性があるため、早めに投函しましょう。
e-tax
e-taxで提出をした場合は、窓口の受付時間などに関係なく、土日や深夜でも提出ができます。また、医療費控除申請の際に必要な源泉徴収票や、保険料控除証明書などの書類提出が必要ありません。窓口や郵送での提出よりも、早く還付金を受け取れるのもメリットです。なお、青色申告特別控除の65万円の控除を受けるためには、e-taxによる申告が必須です。
確定申告の納税方法
確定申告の書類を提出し、納税額が確定したら、納税を行います。納税方法はいくつか用意されているため、自身の都合に合う方法で納税しましょう。
• 振替納税制度
• 金融機関や税務署の窓口で納付
• クレジットカード納付
• コンビニ納付
• e-taxでの電子納税
• スマホアプリ納税
納税額が30万円以下の場合は、e-taxでの電子納税やコンビニ納税、PayPayなどのスマホアプリ納税が便利です。3つの納税方法は、自宅や自宅近くで時間を問わずに納税できる点がメリットです。
もし、納税額が30万円より多い場合や、納税の時期を調整したい場合は振替納税やクレジットカード納付を利用しましょう。また、領収書を希望する場合は、窓口納付で領収書をもらいましょう。

確定申告の内容を間違えたら
確定申告の書類を提出した後に、内容の間違いに気づいたら修正を行い、再度提出しましょう。確定申告の期限内であれば、訂正申告を行います。確定申告期限後に修正する際は、申告・納税額が修正前より多くなる場合は修正申告を、申告・納税額が修正前より少なくなる場合は更正の請求を行います。
例えば、確定申告後に納税額が実際よりも少ないことを税務署に指摘された場合は、税額の10%もしくは15%の過少申告加算税が課されます。しかし、税務署から指摘される前に気づき、自主的に修正申告をした場合は過少申告加算税が課されません。反対に、税額を多く納め過ぎた場合は、確定申告から5年以内に更正の請求を行うと、還付金として過払い額を受け取れます。
確定申告を忘れたら
もし、今年の確定申告の手続きを忘れた場合、どのような問題が起こるのかについてご紹介します。確定申告を忘れた際に起きるのは、以下の4つの問題です。それぞれの内容について、以下で解説します。
①延滞税が発生する
もし、確定申告書類は提出したが、期限までに納税をしなかった場合、法定納期限の翌日から納付が完了するまでの日数に応じて延滞税が加算されます。納期限の翌日から2ヶ月以内に納付した場合は年2.4%、2ヶ月を経過した日以降に納付した場合は年8.7%の税率が適用されます。
➁無申告加算税が発生する
納税義務のある人が、期限までに確定申告を行わなかった場合、無申告加算税が発生します。税率は、納付すべき金額によって、以下のように変わります。ただし、期限後申告であっても法定申告期限から1ヶ月以内に、自主申告をした場合は無申告加算税は発生しません。
| 納付すべき金額 | 税率 |
|---|---|
| 50万円未満 | 15% |
| 50万円超300万円未満 | 20% |
| 300万円超 | 30% |
➂青色申告特別控除の適用が受けられない
青色申告特別控除とは、青色申告者が55万円または65万円の控除を受けられる制度です。控除を受けるには、申告期限までに青色申告で、確定申告を行う必要があります。もし、期限内に確定申告を行わなかった場合、青色申告特別控除の適用は受けられません。控除額は最小の10万円となるため、控除額が少なくなります。
④青色申告の承認が取り消される
確定申告を期限までに行わず、税務調査が入った場合、青色申告の承認が取り消される可能性があります。取り消しとなるのは、正当な理由なく帳簿書類の提示をしない、税務署長の指示に従わない場合、隠蔽または仮装を行った場合などです。
青色申告の承認が取り消されると、青色申告特別控除などの税制優遇は受けられません。なお、再度青色申告を利用するには、1年経過後に申請をし承認が下りてからになります。
まとめ
2025年(令和6年度)の確定申告の変更点や、確定申告の基本情報についてご紹介しました。2025年(令和6年度)の確定申告では、以下の変更があります。
• 定額減税欄の追加
• 所得金額調整控除の記入方法変更
• 子育て世代等の住宅ローン減税拡充に伴う項目追加
• スマホ用電子証明書スタート
• 確定申告書作成コーナーのスマホ対応
• 収受日付印の廃止
特に、定額減税に関する変更はほとんどの人に関連する内容です。提出前に抜け漏れがないか、間違いはないか確認し、正しい形式で提出をしましょう。

























