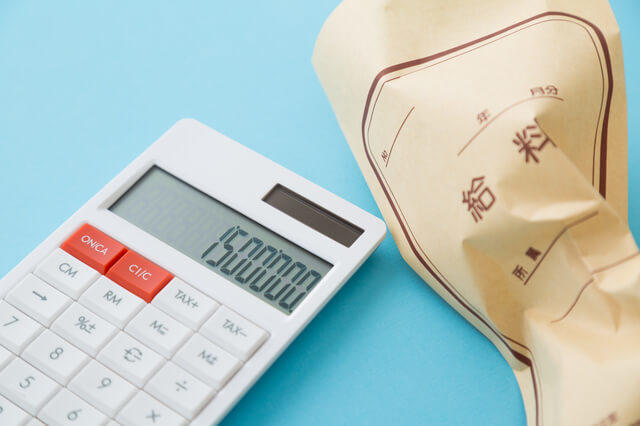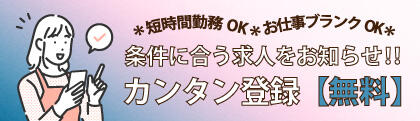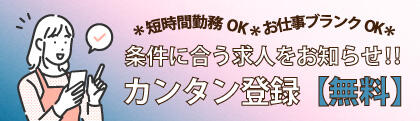パートの扶養範囲とは? 扶養から外れたらどうなる?基本をご紹介!【社労士監修】
- ちょっと得する知識
- 公開日:2018年7月 5日

「税金が控除されるから、扶養内で働きたいんだよね」――ママ友との会話にちょくちょく上る扶養のこと。実は知識があいまいだったりしませんか? 「そもそも、パートの扶養って何?」「扶養の範囲内で働くメリットって何?」と、疑問はつきません。そこで、パートで働く際の「扶養」について、最初におさえておきたい基本的な知識をご紹介します。
この記事の目次
扶養の範囲内とは?
「税金上の扶養」とは?
扶養とは何かについて考える前に、収入と税金の関わりについて理解しましょう。パートタイムやアルバイト、正規雇用など、どのような雇用形態であっても、所得には原則「税金」が課せられます。そして、税金は所得の額によって変動します。
住民税と所得税の一般論として、年収が98万円未満の場合、住民税や所得税などの税金を支払う義務がありません。税金の支払い義務が生じるのは、98万円を超えてから。98万円以上103万円以下の人は、地域によって控除されるところもありますが、基本的には住民税が課せられるようになります。そして103万円を超えると、さらに所得税が発生します。
「年収103万円」を超えるか超えないかで税金の負担が大きく変わるのは、「配偶者控除」と言う制度によるもの。妻の年収が103万円以下の場合は夫の扶養内になり、一定の所得控除を受けられることが税制によって定められています。そのため、パートタイムで働く方の中には、「103万円」に収まるように勤務時間を調整する人も少なくありません。これがいわゆる「103万円の壁」と言われるものです。

「社会保険上の扶養」とは?
年収によって配偶者の所得税が控除されるように、社会保険も、年収がある程度以上になると配偶者が自分で社会保険に加入し、その保険料を負担する必要があります。夫が会社勤務の場合で、妻の年収が130万円以上になると社会保険の扶養から外れ、夫とは別に、妻自身が国民年金や国民健康保険などの社会保険料を支払う必要があります。そのため、「月いくらまで働けるか」を計算して130万円以内に抑える主婦が多く存在します。これがいわゆる「130万円の壁」です。
加えて、2016年10月から、社会保険の加入対象が拡大されました。
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・賃金が月額8.8万円(年収106万)以上であること
・勤務期間が1年以上見込まれること
・従業員501人以上の企業で働いていること
※学生は適用外
【出典】「短時間労働に対する被用者保険の適用拡大」
これまでは週30時間以上働く方が社会保険加入の対象でしたが、上記条件に該当する方についても、適用対象となり、夫の扶養から外れて社会保険に加入する必要があります。
このように、扶養控除の仕組みは非常に複雑です。賢く生活していくためにも、控除の意味をしっかり理解しておきましょう。
こちらの記事も参考になります。
「扶養内のパート。社会保険で損しないために【社労士監修】」
パートで扶養範囲を超えてしまったら?
扶養から外れたら、手取り金額が減ってしまうの?
では、配偶者の扶養から外れたら、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
一番大きなデメリットは、金銭的な負担が増えること。これまで控除されていた税金や社会保険料を支払うことになるのですから、一気に金銭的な負担が増えてしまいます。
仮に、従業員300人程度の企業で働いている場合の、手取りの金額目安を見ていきましょう。(あくまで概算であり、厳密な数値ではありません)
| 年収 | 99万 | 129万 | 152万 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 0円 | 13,000円 | 24,500円 |
| 住民税 | 0円 | 31,000円 | 54,000円 |
| 社会保険 | 0円 | 0円 | 212,800円 (年収の14%計算) |
| 手取り金額 | 99万 | 1,246,000円 | 1,228,700円 |
上記の数字をみると、129万円分働くほうが、152万円分働くよりも手取りが多いというまさかの結果に。給与明細を見て、「所得から税金や社会保険料が引かれると、手取りはこれだけ? あんなに働いたのに......」とがっかりした気持ちになってしまうこともあるでしょう。
夫の家族手当が支給されない可能性も!
上記の結果のように、「せっかく働いたのに、手取りが減るなんて...」という事以外にも、扶養から外れた場合の影響は発生します。家庭によってはこちらのほうが大きな影響を及ぼすことも。
それは、夫が支給されている「家族手当」が支給されなくなるという可能性です。会社によって家族手当の支給要件は異なりますが、給与規則において「配偶者の年収が103万以下」と定められているところも多くあり、その場合は家族手当の支給が翌年度まで停止されてしまいます。これでは、月々の家族手当が1万円だとしても、年間で12万円の収入ダウンとなってしまいます。
さらに、起こりうる事態は「夫の所得税が増える」ということ。これまでは扶養家族がいたため控除されていた税金が、扶養から外れたことによって徴収されることになります。
扶養から外れても悪いことばかりではない?
このようなデメリットを見ると、「こんなにお金を引かれるくらいなら、控除内で働いたほうがまし」――と考える人もいることでしょう。しかし、デメリットばかりではありません。控除から外れることで得られるメリットもたくさんあります。
妻が多く働けば、たとえ税金や社会保険料の支払いが発生しても、収入が増えます。働いた分だけ収入が増えるのですから、経済的には楽になるでしょう。バリバリ働いて世帯年収を増やして、ゆとりのある生活がしたい。そんな希望を持っている方は、控除から外れるデメリットよりもメリットの方を強く感じられることでしょう。
また、夫の扶養控除に入っている場合は、国民年金の受給資格のみが得られますが、厚生年金に加入すればその分、年金受給額が増えます。老後を考えて、夫の控除から外れる選択をすることも「あり」でしょう。このほか、健康保険に加入することで、「出産手当金」などを受給することができます。
そして、扶養控除から外れても、年収201万6千円以内であれば、「配偶者特別控除」を受けることができます。妻の所得に応じて、3万~38万円が夫の所得から控除されるため、デメリットばかりではないのです。
まとめ:メリット・デメリットを理解して、ベストの働き方を選ぶ

扶養控除の範囲内で働くか。それとも、扶養控除から外れても妻の年収を増やすか。その選択が「正解」かどうかは、人それぞれ。「年に一回は家族で旅行したいから、世帯年収を増やすぞ!」という考えたり、「今は子どもが小さいし、体力的にもしんどいから、まずは扶養控除内で」という考え方もありでしょう。
そして「いくら稼ぐ」ということも大切ですが、「どんな仕事」をするか、「どんなやりがいのある仕事を選ぶか」ということも同じくらい大切です。「収入」と「仕事内容」と「働き方」のそれぞれを含めて検討し、家族みんなが笑顔で幸せに生活していくためにも、皆さん自身にとってベストの働き方を検討してみてください。
記事に関する問合せは、ご意見・お問い合わせよりお寄せください。
※個別の相談はお受けできかねます。予めご了承ください。