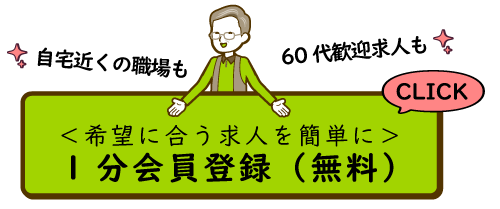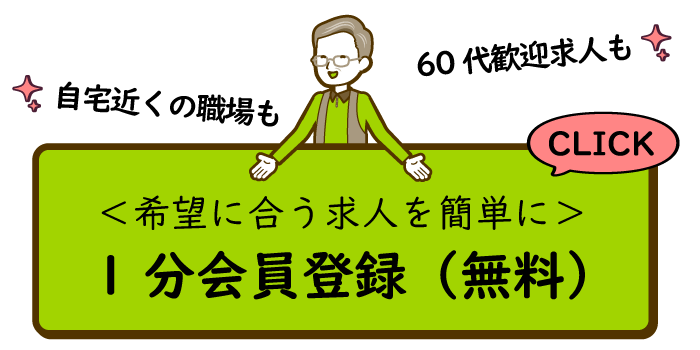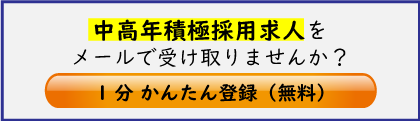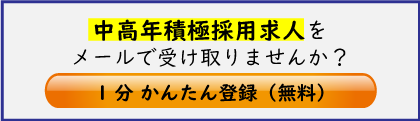知らなきゃ損するお金の制度!役所申請でもらえる手当金・給付金
- ちょっと得する知識
- 公開日:2024年6月 6日
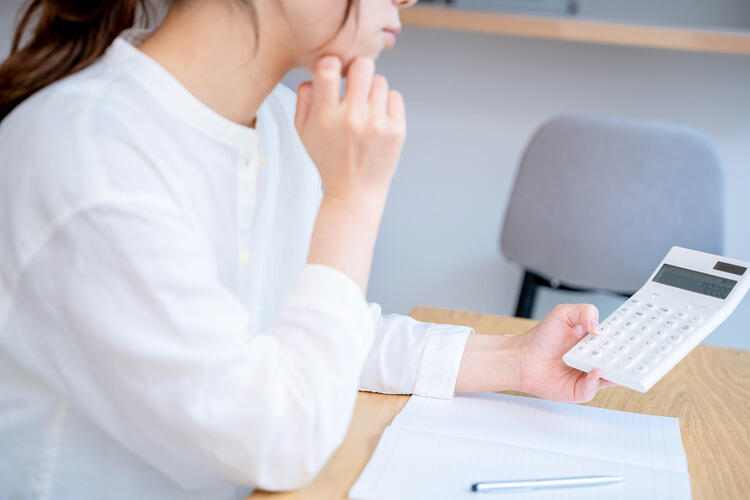
年々、税金や社会保険料などの負担額が増加しています。しかし、手当金や給付金といった、申請をすればお金を受け取れる制度も多数用意されています。今回はミドルシニア世代でも受け取れる、住まい・医療・仕事に関する給付制度をご紹介します。知らなければ受け取れないお金ばかりですので、事前に知っておきましょう。
この記事の目次
〈住まい・生活に関する制度〉住宅特定改修特別税額控除、年金生活者支援給付金を解説
住まいや生活に関係する内容で、ミドルシニアの人でも利用できる可能性のある手当や制度をご紹介します。
住宅特定改修特別税額控除
住宅特定改修特別税額控除は自宅のバリアフリー改修や耐震改修、三世代同居改修などの工事を行った場合に、所得税額から控除される仕組みです。住宅ローンの利用がなくても適用されるため、事前に適用要件を確認しましょう。
今回は、バリアフリー改修工事について解説します。
高齢者や要介護または要支援の認定を受けている本人、もしくは同居する人が所有し居住する家のバリアフリー改修工事を行った際に適応される控除です。バリアフリー改修工事に該当するのは、手すりの設置や段差の解消、お風呂・トイレの改良などがあります。
一定の要件を満たした場合に、控除対象限度額(150万円もしくは200万円)を上限として、控除対象額の10%の控除を受けられます。
▼住宅特定改修特別税額控除(バリアフリー改修工事)の適用要件
• 所有し居住する住居であること(賃貸住宅は除く)
• バリアフリー改修工事の日から6ヶ月以内に住んでいること
• 控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること
• 工事をした後の住宅床面積が50平方メートル以上であり、かつ床面積の1/2以上を生活スペースとしていること
• 2つ以上の家を持っている場合は、メインの住まいであること
• 改修にかかった費用が50万円以上であること
• 工事費用の1/2以上の額が居住用部分の工事費用であること
▼申請方法
適応要件に当てはまり、住宅特定改修特別税額控除を受ける場合は、確定申告を行う必要があります。確定申告時に、以下の必要書類を合わせて提出しましょう。
▼確定申告時の提出書類
• 住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
• 建築士等が発行した「増改築等工事証明書」
• 家屋の「登記事項証明書」など(床面積が50平方メートル以上であることが分かるもの)
• 介護保険の被保険者証の写し(要介護または要支援の認定を受けている本人、もしくは同居する親族に当てはまる場合)
参考:国税庁「バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は消費税率の引き上げ分を活用して、公的年金等の収入金額やその他の一時所得の額が基準以下の人を対象に、年金に上乗せして支給をするものです。受給する年金の種類によって、支給要件は異なります。
老齢基礎年金を受給している場合
老齢基礎年金とは、原則65歳から受け取ることができる年金です。保険料を納めた期間が10年(120か月)以上である必要があります。
▼支給要件
• 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
• 同一世帯の全員が市区町村民税非課税
• 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が878,900円以下
▼給付額
月額5,310円を基準に、以下の計算の合計額を算出します。
• 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
• 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円×保険料免除期間/被保険者月数480月
障害基礎年金を受給している場合
障害基礎年金とは、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象となる年金です。
▼支給要件
• 障害基礎年金の受給者
• 前年の所得が4,721,000円以下
▼給付額
• 障害等級が2級の方:月額5,310円
• 障害等級が1級の方:月額6,638円
遺族基礎年金を受給している場合
遺族基礎年金とは、亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取れる年金です。
▼支給要件
遺族基礎年金の受給者
前年の所得が4,721,000円以下
▼給付額
月額5,310円
※2人以上の子が受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。
▼年金生活者支援給付金の申請方法
年金生活者支援給付金を受け取るためには、日本年金機構へ認定請求の手続きが必要です。また、手続きの方法は現在基礎年金を受給しているかどうかによって異なります。
【すでに老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方】
すでに年金を受給している方で、前年の所得が低下したことにより年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、日本年金機構からはがきが届くことになっています。はがきに必要事項を記入し返送することで手続きが完了します。
【これから老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方】
年金の手続きを行う際に、年金生活者支援給付金の手続きも同時に行います。原則、添付書類は必要ありません。
参考:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
〈健康・医療に関する制度〉高額療養費制度、高額介護サービス費制度を解説

健康や医療に関する手当金もあります。医療や介護の費用を抑えられる可能性があるため、利用できないか確認してみましょう。
高額療養費制度
高額療養費制度は同月内にかかった医療費の自己負担額が、一定の額を超えた場合に超過分を支給される制度です。ただし、入院した際の個室料や食費、先進医療など対象とならない費用もあります。利用の際は事前に確認が必要です。申請をする際は、加入している公的医療保険に対して、高額療養費の支給申請書を提出しましょう。
上限額は収入や年齢によって異なりますが、世帯での合算ができます。また、直近1年以内で3回以上上限額に達した場合、4回目からは「多数回」に該当し、上限額が下がります。69歳以下の方の上限額と、多数回に該当した場合の上限額は以下の通りです。
| 適用区分 | 上限額 | 多数回該当の上限額 |
|---|---|---|
| 年収1,160万円〜 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
| 年収約770〜1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% | 93,000円 |
| 年収約370〜770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | 44,400円 |
| 〜年収約370万円 | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
参考:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
高額介護サービス費制度
医療費だけではなく、介護に関する費用も一定の基準を満たすとお金が戻ってくる場合があります。介護保険を利用した場合、サービスを受けると自己負担額は原則1割です。しかし、1ヶ月の自己負担額が限度額を超えた場合は、以下のような金額を受け取り可能です。
| 区分 |
限度額(月額) |
|---|---|
| 年収約1,160万円〜 | 140,100円(世帯) |
| 年収約770〜1,160万円 | 93,000円(世帯) |
| 年収約370〜770万円 | 44,400円(世帯) |
| 世帯全員が住民税非課税 | 24,600円(世帯) |
| 世帯全員が住民税非課税かつ、前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 生活保護受給者 | 15,000円(世帯) |
ただし、高額介護サービス費の対象とはならないものもあります。福祉用品の購入費用や住宅改修費用、施設サービスの居住費などです。申請をする際は、該当条件に当てはまっているか確認しましょう。
参考:厚生労働省「高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」
〈仕事に関する制度〉高年齢雇用継続給付金、介護休業給付を解説

定年後の再雇用で賃金が低下した際に申請できる高年齢雇用継続給付金や、仕事を介護で休職する際に申請できる介護休業など、働くことに関する制度をご紹介します。
高年齢雇用継続給付金
60歳〜65歳未満の被保険者が、60歳の時点で支給されていた賃金よりも、75%未満に低下した時に申請できる制度です。申請はハローワークで行い、認められれば各月に支払われた賃金の最大15%が支給されます。
▼高年齢雇用継続給付金の支給要件
• 支給対象月の初日から末日まで被保険者である
• 支給対象月中に支払われた賃金が、60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下している
• 支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額未満(※)である
• 申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額(※)を超えている
• 支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象ではない
(※)この金額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます。
高年齢雇用継続給付金は、雇用保険を受給していない人向けの「高年齢雇用継続基本給付金」と、雇用保険の受給中に再就職した人向けの「高年齢再就職給付金」があります。どちらの支給を受けるかによって、さらに条件が異なるため事前に確認しましょう。
▼高年齢雇用継続基本給付金の受給資格
• 60歳以上、65歳未満の一般被保険者である
• 一般被保険者であった期間が通算して5年以上ある
▼高年齢再就職給付金の受給資格
• 60歳以上、65歳未満の一般被保険者である
• 基本手当についての算定基礎期間が5年以上ある
• 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある
• 1年を超えて雇用されることが確実な安定した職業に就いており、一般被保険者になっている
• 同一の就職において、再就職手当の支給を受けていない
参考:厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
介護休業給付
介護休業給付金は、配偶者や親子どもの介護が必要となり介護休業を取得する際に、給料の67%が保証される制度です。介護休業は法律で権利が認められており、条件を満たすと最大93日、最大3回までの分割で支給されます。
介護休業は要介護状態の家族を、2週間以上を目安として仕事を休む必要があった場合に取得可能です。また、介護休業後に職場復帰をする人が対象であるため、退職が決まっている人は介護休業を取得することはできません。
▼介護休業の給付額
休業開始時賃金日額×支給日数(最大93日)×67%
▼介護休業の受給要件
• 雇用保険の被保険者である
• 介護休業開始2年間で、1ヶ月の間に11日以上出勤している月が12ヶ月以上ある
有期雇用労働者の場合は、上記に加えて以下の要件も満たす必要があります。
• 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から、6か月を経過する日までに労働契約が満了するこがが明らかでない
また、介護をする対象も限られており親や子ども、兄弟などが対象です。申請をする際は、原則事業主を通して行う必要があります。
参考:厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」
〈死亡した場合に関する制度〉遺族年金を解説
配偶者や家族が死亡してしまった場合に、受け取れるお金もあります。
遺族年金
遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなったとき、その人に生計を維持してもらっていた遺族が受け取れる年金です。遺族年金には国民年金から支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金から支給される「遺族厚生年金」の2つがあります。支給される際は、どちらか一方または両方が支給されます。それぞれの支給条件などについては、以下でご紹介します。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は亡くなった人によって生計を維持されていた、「子のある配偶者」または「子」が受け取れます。この場合の「子」は、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級か2級の状態にある人です。
▼遺族基礎年金の受給要件
以下のいずれかに該当する方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
• 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
• 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、日本国内に住所を有している人が死亡したとき
• 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
• 老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき
遺族厚生年金
遺族厚生年金は亡くなった人によって生計を維持されていた、遺族が受け取れます。
▼遺族厚生年金の受給要件
• 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
• 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
• 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
• 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
• 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
参考:日本年金機構「遺族年金」
まとめ
申請すると受け取れるお金についてご紹介しました。申請するお金はさまざまな人を対象にしており、ミドルシニアやシニアに向けたものも多くあります。介護のために自宅をリフォームした場合や、介護費用・医療費で出費が発生した場合は、補助金や控除の対象になる場合があります。
また、60歳以降に仕事を続ける際にも補助金を受け取れる場合もあります。仕事を続けながらお金を受け取れる場合もあるため、積極的に活用しましょう。自身はもちろん、家族に介護が必要となった時などに受け取れるお金もあります。事前に条件を確認し、忘れずに申請を進めましょう。