ふるさと納税はいつまで?ワンストップ特例と確定申告の違い、ポイント付与について解説
- ちょっと得する知識
- 公開日:2024年12月26日
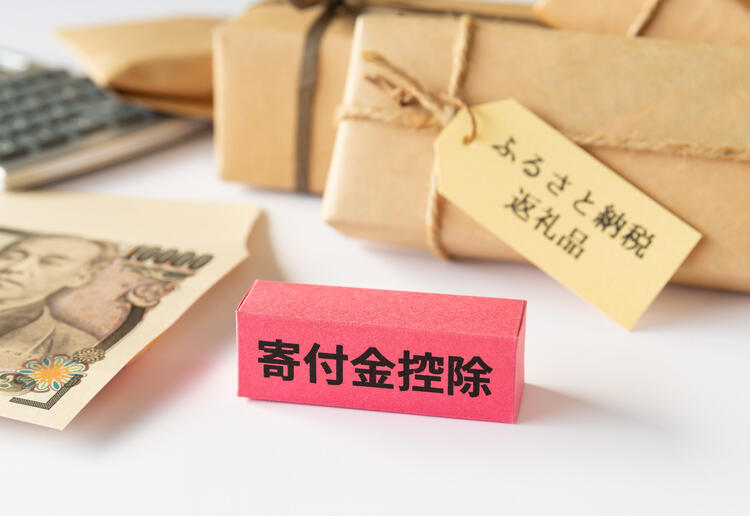
ふるさと納税は1年間を通して受付をしていますが、税金の控除手続きには期限が設けられています。今回はふるさと納税の概要から、税金控除手続きについて解説。さらに、急いで選んで後悔しないよう返礼品選びのポイントや、注意点などもご紹介します。今年こそはふるさと納税に挑戦したい人は、ぜひご一読ください。
この記事の目次
ふるさと納税とは寄付の一種
ふるさと納税は寄付の一種です。自身で選んだ自治体に寄付を行うと、返礼品の受け取りや税金の控除が受けられます。自己負担額は2,000円で、それ以上の分が控除額として税金から差し引かれます。
控除の対象となる税金は所得税と住民税の2つで、確定申告で行った場合は両方が、ワンストップ特例制度の場合は住民税のみが控除の対象です。ふるさと納税の申し込み期間は、1月1日〜12月31日の23:59までとなっており、24時間365日いつでも申し込み可能です。
ふるさと納税の流れ
ふるさと納税の具体的な利用の流れは、以下の通りです。
1. 限度額を把握する
ふるさと納税は、自身の年収や家族構成によって、控除できる金額の上限が決まっています。そのため、最初に自身の控除上限額を確認しましょう。例えば、年収500万円で共働き、子供1人の世帯の場合の上限額は4万9,000円です。上限額については、ふるさと納税のサイトで、簡単にシミュレーションを利用して確認できます。
2. 返礼品を選ぶ
控除額がわかったら、控除額の範囲内で好きな返礼品を選びましょう。自治体によってさまざまな返礼品が用意されているため、自身に合った返礼品を見つけられます。
3. 税金控除の申請を行う
返礼品の申請後は、税金控除の申請が必要です。もし、寄付をした自治体が5ヶ所以下の場合は、ワンストップ特例制度が利用できます。寄付をした自治体が6ヶ所以上の場合や、確定申告が必要な人は、確定申告の際に申請しましょう。
受領日の違いを知っておく
ふるさと納税で税金控除を受けるには、その年の1月1日〜12月31日までに決済が完了したものが対象です。そのため、12月31日に申し込みをしても、決済が次の日になれば翌年分に含まれます。
決済完了までにかかる時間は、各支払い方法の受領日によって異なります。受領日の違いによって、受けられる控除金額が想像よりも低かったとならないよう、各受領日を知っておきましょう。
• クレジットカード:決済完了日
• 銀行振込:指定口座に支払いした日
• 払込取扱表:指定口座に支払いした日
• 現金書留:自治体側が受領した日
特に年末年始休みの期間などは、駆け込みで申し込みをする人も増えてくるため、処理に時間がかかる可能性があります。早めに申し込みを行いましょう。
寄付ができたか確認するには
ふるさと納税を行った後に寄付ができているか確認するには、以下の方法があります。
受付完了メールを確認する
受付完了メールには、支払い用のURLが記載されています。もし、支払いが完了していれば完了の旨が、まだ完了していない場合は期限切れや不備があるなどのメッセージが表示されます。
マイページから確認する
ふるさと納税のサイトを利用して申し込みを行った場合は、マイページの寄付履歴などで確認可能です。
寄付先の自治体へ問い合わせ
そのほか、銀行振込などを行った際は自治体側がステータス管理を行っており、決済完了メールが届かない場合があります。反映に時間がかかっている場合は、寄付した自治体へ問い合わせをしましょう。
ふるさと納税の控除手続き期間について

ふるさと納税の申し込みはいつでもできますが、控除手続きを行う際には期間に気を付ける必要があります。ワンストップ特例制度と確定申告で期限も異なるため、事前にしっかりと確認しましょう。
ワンストップ特例制度を利用する場合
ワンストップ特例制度を利用する場合は、翌年の1月10日に必着で自治体に申請を行います。その際、本人確認書類も同時に提出する必要があります。ワンストップ特例制度は確定申告の必要がない給与所得者かつ、寄付した自治体数が5ヶ所以下の場合に利用できる制度です。
翌年の1月10日までに寄付をした自治体に書類を提出すると、自身が住んでいる自治体に対して寄付先の自治体が控除情報を提出します。その後、住民税が控除されます。書類は1月10日に必着のため、遅くても3日前までには投函しましょう。
確定申告で行う場合
確定申告で行う場合は、寄附金控除の申請を3月15日までに行いましょう。自身で税務署に書類を提出すると、まず所得税の還付が受けられます。また、その後に住んでいる自治体から住民税の控除が受けられる仕組みです。
自己負担額の2,000円を除いた金額が、所得税と住民税から全額控除されるのは、魅力的です。ワンストップ特例制度の書類を提出できなかった人や、医療費控除など行う場合は、確定申告の際に提出しましょう。
ふるさと納税の仲介サイトからのポイント付与
現在、ふるさと納税を行う際に利用される、仲介サイトでは利用によってポイントが付与されています。しかし、2025年10月よりふるさと納税の仲介サイトによるポイント付与が廃止となります。
廃止される理由は、サイト同士のポイント付与競争が発生する点や、ポイントへ支払う手数料が増加し、自治体側の負担が大きくなっている点があげられます。ただし、今回廃止されるのは仲介サイトのポイント付与であり、クレジットカードによる決済を行った際に付与される、カードのポイントは従来通り行われます。
ポイントの廃止は2025年10月からのため、ポイントを少しでも貯めておきたい人は、2025年9月中までに申請を行いましょう。また、獲得したポイントの利用期限は、各ポータルサイトによって異なるため、随時確認しましょう。
ふるさと納税の返礼品選びに迷ったら
ふるさと納税をしようと考えているが、どうやって返礼品を選べばいいのか悩んでいる人も多いでしょう。以下では、返礼品を選ぶためのポイントを5つご紹介します。ぜひ、返礼品選びの参考にしてください。
生活必需品を選ぶ
ふるさと納税の返礼品選びに悩んでいる場合は、生活必需品の中から選んでみましょう。返礼品の中には、トイレットペーパーやタオル、洗濯洗剤などの消耗品が用意されています。食品やクーポンなどとは異なり使用期限がないため、注文品を自身のペースで利用できるのは嬉しい点です。
毎日の生活で使うものを購入するだけで、税金の控除を受けられるのは魅力的です。
食品を選ぶ場合は、保存が効くものを選びましょう。冷凍可能なものはもちろん、乾麺やパックご飯、缶詰などであれば、災害時の備蓄にもなります。
旅行やレジャーなどで使えるもの
返礼品は形ある物だけではなく、旅行時に使えるクーポンや宿泊ギフト券などもあります。興味はあるけれど、行った経験のない場所の宿泊券を選べば、お得に旅行を楽しめるでしょう。特別な日のお祝いなどにも利用可能です。
また、仲介サイトによっては、ゴルフなどのレジャーで利用できるクーポンも用意されています。自身の出かけたい場所や、趣味で利用できる物がないか確認しましょう。
後から好きな物を選べる商品
後から自分で選べるカタログギフトなどもおすすめです。カタログギフトであれば、期限が長く設けられているため、じっくりと自分の好きなものを選べます。また、ポイントを活用すれば、より豪華な返礼品を選べるでしょう。
ふるさと納税の控除上限額はその年に利用しなければ、余った分が繰り越されることはありません。無駄なく活用したい場合は、利用期限が長く設定されているカタログなどを検討しましょう。
家族や友人へのギフトに利用する
ふるさと納税の返礼品を、家族や友人へのギフトとして送ることもできます。カタログギフトや旅行のクーポン、果物などは誕生日や記念日のお祝いとして選ばれています。返礼品のなかには熨斗に対応している物もあり、ギフトとしての利用も可能です。欲しい物がないなら寄付だけも検討する
どうしても欲しい物がない場合は、寄付だけを行うこともご検討ください。寄付先には、能登地震被害支援や保護犬のレスキュー、子供食堂などがあります。返礼品がない場合が多いですが、なかには返礼品を用意している団体もあります。控除を受けながら社会貢献にもつながるため、控除額を使い切りたい場合は寄付のみも検討してみましょう。

ふるさと納税をする際の注意点
ふるさと納税を利用する際には、いくつか知っておきたい注意点があります。後悔せずにふるさと納税を活用するためにも、事前にご確認ください。
名義が違うと控除が受けられない
ふるさと納税は、「寄付をした人」と「支払いをする人」が同じでないと、控除が受けられません。例えば、寄付をしたのは妻名義だが、支払いをしたクレジットカードは夫名義だった場合、名義が一致しないために控除を受けられなくなります。
せっかくふるさと納税を行っても、控除が受けられなくなるため、必ず利用するクレジットカードや銀行口座の名義が同一になっているか確認しましょう。
節税になるわけではない
ふるさと納税を行うと所得税や住民税の控除を受けられますが、直接的な節税になるわけではありません。ふるさと納税は寄付をする形で、自治体に対して前払いをする制度です。その後に還付や控除が行われるため、税額自体が減額されるわけではありません。
さらに、控除の上限額を超えて寄付をした場合、超過分は自己負担となるため、本来のふるさと納税の恩恵を受けられなくなります。節税対策ではないことは、理解しておきましょう。
寄付をした年のお金は持ち出し
ふるさと納税は自身で選んだ自治体に対して前払いを行い、その翌年に還付や控除が受けられる制度です。そのため、1番最初の年に寄付した金額は、持ち出しとなります。財政的な余裕がない時に寄付を行うと、家計が厳しい状態に陥ることもあるかもしれません。所得税や住民税の還付、控除を受けるにはタイムラグがある点は知っておきましょう。
早めに申請を行う
年末になると、今年の控除上限額を使い切ろうと、駆け込みで申し込みをする人が増えます。申し込み数が増えれば、希望の返礼品を受け取れなくなる可能性も。さらに、自治体によっては、早めに年内の分を締め切ってしまう場合もあります。希望の返礼品を受け取るためにも、余裕を持って申請を行いましょう。
まとめ
ふるさと納税の基本情報や、ワンストップ特例と確定申告の申請期限、後悔しないための返礼品選びのポイントをお伝えしました。ふるさと納税自体は1月1日〜12月31日まで、いつでも申し込みを受け付けています。
しかし、税金の控除を受けるための手続きは期限が決まっており、ワンストップ特例制度は翌年1月10日必着、確定申告は3月15日までに行う必要があります。忘れないよう、必ず余裕を持って行いましょう。
ふるさと納税には多数の返礼品が用意されており、食料品のほかには生活必需品やギフトに使えるアイテムもあります。多数の返礼品の中から、後悔しないアイテムを選びましょう。ふるさと納税の仕組みを理解して、ぜひお得に活用しましょう。

























