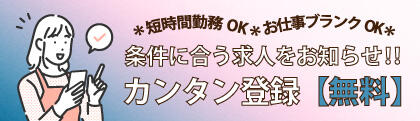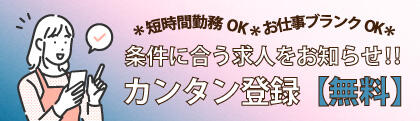【最新情報】年収103万円の壁が引き上げ?引き上げ予定額や開始予定時期についてご紹介
- ちょっと得する知識
- 公開日:2025年1月10日

昨今、103万円の壁が引き上げられるとニュースで話題になっています。そこで、今回は103万円の壁の概要から、年収の壁が引き上げられる背景、引き上げ予定額などをご紹介します。また、引き上げられた場合のメリットやデメリットについても解説するため、年収の壁を意識して働いている方は、ぜひご一読ください。
この記事の目次
103万円の壁は所得税が発生するボーダーライン
103万円の壁は、所得税が発生するかどうかの境目となる年収を指しています。配偶者や親の扶養範囲内で働いている人にとっては、重要なボーダーラインとなっており、103万円を超えないように調整している人も多くいます。103万円という数字は、基礎控除の48万円と、給与所得控除の55万円の合計から算出された額です。
103万円の壁を超えるとどのような影響があるか
年収が103万円を超えると、所得税が発生します。所得税の分だけ手取りが減少するため、生活費への影響が出てくるでしょう。年収が103万円を超えた場合、支払う税額は年収によって変わります。所得金額に応じた税率は、以下の通りです。
| 所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜194万9000円 | 5% | 0円 |
| 195万〜329万9000円 | 10% | 9万7500円 |
| 330万〜694万9000円 | 20% | 42万7500円 |
| 695万〜899万9000円 | 23% | 63万6000円 |
| 900万〜1799万9000円 | 33% | 153万6000円 |
| 1800万〜3999万9000円 | 40% | 279万6000円 |
| 4000万円以上 | 45% | 479万6000円 |
引用元:国税庁 所得税の税率
また、2037年までは、所得税額の2.1%の復興特別所得税の納付も必要となります。例えば、年収が105万円の場合の納税額は所得税が1,000円、復興特別所得税は21円で1,021円です。そのほか、学生やフリーターなどで親の扶養に入っている人が、年収103万円を超えると親の所得税や住民税が増加します。
103万円の壁が引き上げられる背景や目的は?
今回、103万円の壁が引き上げられることになった背景や目的には、以下のようなものがあります。
• 国民の手取り収入を増やすため
• 労働力不足を解消するため
• 女性の社会進出の手助け
最近は最低賃金が上昇しているため、103万円にすぐ届いてしまい、従業員はより短時間で働くことになります。そのため、より人手不足に拍車がかかっている状況です。年収の壁が引き上げられると、現在年収の壁を意識して働き控えをしている人がこれまでより長時間働けるようになります。
また、103万円の壁を意識して働く人の多くは、主に主婦である女性です。扶養の範囲内で働いている場合、スキルを活かしきれない可能性もあり、能力のある女性の社会進出を妨げている問題もあります。年収の壁が引き上げられれば、より多くの人が能力を活かして働けるようになるでしょう。
103万円の壁はいつから・いくら引き上げられるのか

103万円の壁については現在協議が続いているため、いくらまで引き上げられるのかなどは未定です。しかし、年収の壁の引き上げ時期は、2025年から開始となることで合意しています。そのため、年明けから徐々に生活や働き方に変化が起こるでしょう。
引き上げ予定額については、178万円を目指すとされています。178万円とされている根拠は、103万円の壁制度が始まった1995年の最低賃金に関係しています。103万円の壁が始まった1995年の最低賃金は611円でしたが、2024年の最低賃金は1,055円と1.73倍です。その上昇した分と同様に、年収の壁も103万円の1.73倍である178万円にしようという考え方です。
しかし、123万円とする案も出ています。123万円は現在の控除額を20%引き上げた金額です。(所得税の基礎控除を48万円から58万円、給与所得控除を55万円から65万円に引き上げた合計金額)
103万円の壁が引き上げられるメリット
103万円の壁が引き上げられることには、いくつかのメリットがあります。どのようなメリットがあるか、以下でご紹介します。
学生が働きやすくなる
103万円の壁が引き上げられると、学生がアルバイトで働ける時間が増加します。そもそも現在の学生の場合、勤労学生控除が設けられているため103万円を超えても所得税はかかりません。しかし、扶養親族の負担が増えるために、結果として103万円以内に収まるように働いている学生がほとんどです。
年収の壁が引き上げられれば、長期休暇でも年収の壁を意識せずに働けるため、将来のキャリアにつながるような経験ができるでしょう。さらに、労働できる時間が増えるため、職種やバイト先の選択肢も増えていきます。103万円の壁が引き上げられると、学生がより働きやすくなるでしょう。
親の税負担が軽減される
103万円の壁が引き上げられると、子供を扶養している親の税負担が変わります。現在は、扶養している子供の年収が103万円を超えると、所得税が親側に発生します。
具体的には、年収が103万円以内の場合、19歳〜23歳未満の特定扶養親族の控除が利用可能です。しかし、年収が103万円を超えた場合、親の所得税率が10%なら約6万円、20%なら約12万円の負担が発生します。年収の壁が引き上げられれば、103万円を超えても税金が発生しないため、結果として親の負担も軽減されます。
世帯年収が増加する
103万円の壁が引き上げられれば、扶養の範囲内で働ける範囲も広がり、世帯年収の増加が期待できます。現在は扶養の範囲を超えてしまうからと、103万円で収まるように働いていた人が多くいます。また、最低賃金が上昇しているが、扶養の問題があるために金額や労働時間の調整に苦労している人も。
しかし、年収の壁が引き上げられれば、従来のような働き控えをする必要もありません。働ける時間が増えるため、その分世帯年収の増加が期待できるでしょう。
労働力の増加につながる
103万円の壁が引き上げられると、企業側にも労働力増加というメリットがあります。現在は103万円の範囲内で働くパート・アルバイトの人も多く、人手不足となっている企業も多いです。年収の壁が引き上げられれば、より長い時間働ける人が増加します。特に、人手不足となりやすいサービス業や飲食業では、壁の引き上げによって労働力を確保しやすくなるでしょう。
103万円の壁が引き上げられるデメリット
103万円の壁が引き上げられると、デメリットも出てきます。どのようなデメリットがあるのか、個人に影響が出るであろう内容を、3つご紹介します。
次の年収の壁にぶつかる
103万円の壁が引き上げられると、従来以上に働けるようになるでしょう。しかし、年収の壁にはいくつかの種類があるため、103万円の壁だけが引き上げられても、他の壁にぶつかる可能性があります。
特に、103万円の次の壁である、106万円と130万円の壁です。どちらも、社会保険に加入をするかどうかのボーダーラインです。
106万円の壁
年収が106万円を超えて、かつ以下の条件を満たした場合は、社会保険の加入が必要になります。月額賃金は、時給や日給などで働いた金額が対象となるため、通勤手当やボーナスは含まれません。
• 従業員が51人以上
• 週の所定労働時間が20時間以上
• 月額賃金が88,000円以上
• 2ヶ月を超える雇用の見込み
• 学生ではない
130万円の壁
130万円を超えた場合は、社会保険に加入する必要があります。社会保険への加入が必須となるため、130万円の壁と呼ばれています。
103万円の壁が引き上げられても、今度は社会保険に関する壁が出てくるため、結局労働時間や金額を気にして働かなければならないでしょう。
学生の税負担が増える
学生の場合は103万円を超えて働いても、勤労学生控除が設けられているため、直接税負担があるという場合は少ないでしょう。この勤労学生控除は年収が130万円以内であれば、受けられる控除です。
しかし、103万円の壁が引き上げられて、働き控えをする必要がなくなってくると、勤労学生控除の対象となる130万円を超える人が増えるでしょう。勤労学生控除の範囲を超えると、自身で社会保険に加入する必要が出てくる可能性があります。場合によっては学生自身の税や保険料などの負担が上昇するでしょう。
生活に影響が出る場合がある
年収の壁が103万円から引き上げられると、税収が減り生活に影響が出る可能性があります。もし、178万円に引き上げられた場合は7兆円〜8兆円の税収減となり、そのうちの4兆円は地方税が減収となります。
地方税が減収となると、行政が独自で行っているサービスを受けられなくなるといった問題が出てくるでしょう。例えば、学校給食費の負担軽減や駅の再開発、学校の整備などがあげられます。これまで受けられていたサービスなど、生活に関わっていた部分に影響が出る可能性がある点は知っておきましょう。
103万円の壁が引き上げられた際に必要となる対応

103万円の壁が引き上げられた際、どのような対応が必要となるのかを知っておきましょう。例えば、現在103万円を超えないように雇用契約を結んでいる場合は、新たな壁に応じた勤務時間に再設定しなおす必要があります。どの程度までなら働けるのか、日常生活に影響のない範囲を模索するところから始める人もいるでしょう。
また、103万円の壁が引き上げられると、他の年収の壁も変更が出る可能性が出てきます。どのように変化をしていくのか、自身に影響する内容や金額などはあるかを随時確認し、状況に応じて働き方を変更していく必要もあるでしょう。
103万円の壁が引き上げられたら手取りはどうなる?
もし、年収の壁が178万円に引き上げられた場合、基礎控除額は48万円から123万円に拡大されます。所得の10%の所得税を支払っている場合は7万5000円、20%の人は15万円、無条件で手取りが増えるでしょう。手取りが増えるのは、多くの人にメリットとなります。
しかし、年収の壁には社会保険の対象となる106万円と130万円の壁が存在します。社会保険に加入した場合は、手取りから社会保険料が引かれるため、実際は微増となる可能性もあるでしょう。人によっては103万円の壁が引き上げられても、106万円の壁を意識して就労調整が必要となる場合があります。
なお、106万円の壁の要件となっている年収106万円や、企業の従業員数が51人以上といった要件は今後撤廃される予定です。企業で働く人のほとんどが社会保険に加入する必要が出てくると、103万円の壁が引き上げられても手取りの増加が期待できないといった可能性も考えられます。
まとめ
昨今話題の、103万円の壁の引き上げについてご紹介しました。所得税が発生する年収103万円の壁を引き上げて、手取り少なさや労働力不足といった問題を解消しようという背景を元に、変更される予定です。2025年から引き上げが行われる予定ですが、どの金額を上限とするかについては未定です。
103万円の壁が引き上げられると、労働力不足の解消や働く子供を扶養している親の税負担が軽減されるなどのメリットがあります。しかし、税収が減ることで地方の財源が減り、生活に関するサービスを受けられなくなるなどのデメリットが出てくる可能性もあります。
今後、どのように年収の壁が変化していくのかを把握し、自身に合った働き方を模索していきましょう。