定額減税の疑問、控除しきれない場合はどうなるの?調整給付について解説
- ちょっと得する知識
- 公開日:2024年7月 3日
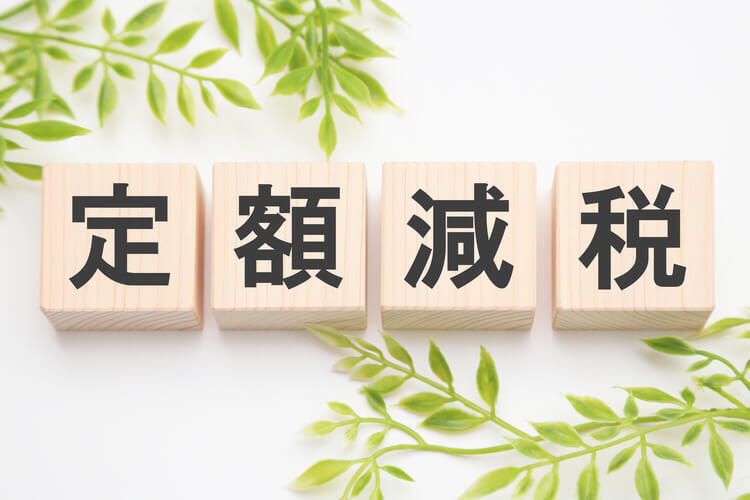
今年(2024年)の6月から実施されている定額減税。自治体や企業の担当者は急ピッチで対応が進められました。実際に6月の給与明細で、定額減税分が控除されていることを確認された方も多いのではないでしょうか。本日はそんな定額減税の疑問の一つ、控除しきれない場合の「調整給付」についてご紹介します。
この記事の目次
2024年6月からスタートした定額減税
いよいよ定額減税が始まりました。まずは、定額減税とは一体どのようなものかをもう一度おさらいしましょう。
定額減税とは、2024年に決定された新しい減税制度です。具体的には、令和6年分の所得税30000円/人・住民税10000円/人が減税されるというものです。2024年6月1日以降の給与支払分から減税され、給与所得者をはじめとする納税者の経済的負担を軽減することが目的とされています。
定額減税の対象となるのは、日本国内に住所があり、2024年分の所得税・住民税の納税者です。ただし、2024年の合計所得金額が1,805万円以下(※給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)であることが条件になります。
今回の定額減税は、納税者本人のほか、同一生計配偶者や扶養親族も対象となります。条件は以下の通りです。
・納税者本人と生計を一にしていること
・日本国内に住所があること
・年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与所得だけの場合、給与収入が103万円以下であること)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
以上の対象者には、所得税と住民税をあわせて1人あたり合計4万円が減税されます。
実際の減税額はどのくらい?
たとえば、合計所得金額1,805万円以下の納税者本人と同一生計配偶者、扶養親族2人、計4人世帯の場合の定額減税による控除額は以下のようになります。
所得税からの控除額
納税者本人3万円+同一生計配偶者と扶養親族(3人×3万円)=12万円
住民税からの控除額
納税者本人1万円+同一生計配偶者と扶養親族(3人×1万円)=4万円
つまり、この世帯の減税額は合計16万円になるという訳です。
こんな場合も、定額減税の対象になる?
定額減税という制度が始まったこと自体は様々なニュースや、実際に給与明細などで把握することができます。では、もう少し詳細に定額減税の対象となる条件をみていきましょう。
アルバイトの場合は?
アルバイトの方は、収入や扶養に入っているかどうかによって対象になるかを判断します。たとえば、アルバイトの収入が103万円以下で親族に扶養されている場合、扶養する人が定額減税を受けることになるため、本人には影響がありません。
また、アルバイト収入が103万円以下であれば所得税はかかりませんが、年収が100万円を超える場合は住民税の所得割がかかります。この場合は扶養に入っていなければ、住民税のみ定額減税が受けられます。さらに、収入が103万円を超えている場合で、給与から所得税などが源泉徴収されていれば、定額減税の対象となります。
副業をしている会社員の場合は?
会社員で副業をしているなど、複数口からの収入がある人の場合は、メインで給与をもらっている会社で控除されることになっています。また、定額減税額のうちメインの給与をもらっている会社で控除しきれなかった金額がある場合は、確定申告を行った上で最終的な定額減税額の精算を行うことができます。
さらに、個人事業主などの事業所得者は、住民税に関しては定額減税前の税額をもとに算出され、2024年6月分の税額から控除されます。そこで、控除しきれない場合は2024年8月分以降の税額から、順次控除されることになります。
なお、所得税は2024年分の所得税の確定申告で、2025年分の所得税額が控除されます。対象者は確定申告を忘れずにするようにしましょう。
定額減税しきれない場合の「調整給付」とは?

定額減税の対象者の中には、税額が定額減税可能額に満たない方が存在します。そういった方々に対しては、差額を推定計算して現金で給付する「調整給付」という制度が設けられています。
今回の定額減税額は、1人あたり住民税1万円と所得税3万円を合わせた4万円が減税されることになっています。たとえば、妻と子ども1人を扶養する3人家族では、減税額は12万円です。しかし、実際に納めている税金が12万円よりも少ない場合、減税しきれない差額が発生します。その差額分は「調整給付」として受け取ることができるのです。
現在のところ、定額減税可能額に満たないとされる方は2,300万人ほどにのぼると累計されています。多くの方が調整給付の対象となると考えられますので、事前に申請方法や給付の流れを確認しておきましょう。
調整給付の対象者
要件を満たす次の方が対象となります。
・令和6年分所得税が課税される見込みの方、または、市区町村から令和6年度住民税所得割が課税されている方
・定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
具体的には、定額減税前の「令和6年度分個人住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得額)」から定額減税可能額を控除しきれない方です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、減税前の所得税額や住民税所得割額のいずれもが0円の場合は、調整給付の対象とはなりません。
つまり、納税者本人と扶養親族の数から算定される減税額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合に限り、市区町村が差額分を給付します。
調整給付の申請方法
調整給付の対象者には市町村から申請書や確認書等が送付されることになっています。申請方法は、マイナンバーカードを利用したオンライン申請や郵送申請など、自治体それぞれが用意しています。なお、自治体が独自の要件や申請期限を設けている場合もあります。予め自治体のHPを確認し、案内に従うようにしましょう。
調整給付の給付までの流れ
まずは自治体から給付金額と振込口座を記載した確認書が送られてきます。届き次第、申請方法を確認し案内に従い申請を行いましょう。確認書の審査後、数週間のうちにご自身が申告した口座へと振り込まれます。(※各自治体によっては異なる場合があります)
データ元:内閣官房「「定額減税しきれないと見込まれる方」 への給付金」
給与から見る、調整給付の対象になる世帯とは?
「調整給付があるというのは分かったけれど...実際どのように算出されるの?」と、疑問に思う方も多いはず。では、実際に想定される給付額の計算方法と、調整給付に該当するケースをみていきましょう。
調整給付の計算方法
給付額については、以下の①・➁を合計し、1万円単位に切り上げた額となります。
➀所得税から減税しきれない額=所得税 定額減税可能額-令和6年分 推計所得税額
➁住民税から減税しきれない額=個人住民税 定額減税可能額-令和6年度 個人住民税所得割額
➂調整給付額=①+➁
また、あくまで推計所得税額であるため、確定申告書や源泉徴収票の令和5年分所得税額と一致しないこともあります。そうした場合は、令和6年分所得税額が確定した後に、給付の不足があれば令和7年度以降に追加給付予定とのことです。
ケース1:世帯主(給与所得者)・配偶者・子ども2人の4人世帯
定額減税可能額
所得税減税可能額...3万円×4人=12万円
住民税所得割分減税可能額...1万円×4人=4万円
【給与収入が300万円の場合】
① 120,000円-所得税(推計)4,000円=116,000円
② 40,000円-住民税20,900円=19,100円
③ 116,000円+19,100円=135,000円(定額減税しきれない合計額)
給付金は1万円単位の切り上げとなるため、調整給付金は140,000円となります。
【同じ世帯で、給与収入が700万円の場合】
① 120,000円-所得税(推計)168,000円=-48,000円(満額減税)
② 40,000円-住民税282,600円=-242,600円(満額減税)
③ 0円+0円=0円
満額減税されるため、調整給付金はありません。
ケース2:単身世帯(給与所得者)
定額減税可能額
所得税減税可能額...3万円×1人=3万円
住民税所得割分減税可能額...1万円×1人=1万円
【給与収入が200万円の場合】
④ 10,000円-所得税(推計)27,000円=3,000円
⑤ 40,000円-住民税54,700円=-14,700円(満額減税)
⑥ 3,000円+0円=3,000円(定額減税しきれない合計額)
給付金は1万円単位の切り上げとなるため、調整給付金は10,000円となります。
ケース3:65歳以上の夫婦世帯(年金所得者)
定額減税可能額
所得税減税可能額...3万円×2人=6万円
住民税所得割分減税可能額...1万円×2人=2万円
【年金収入が300万円の場合】
⑦ 60,000円-所得税(推計)41,800円=18,200円
⑧ 20,000円-住民税85,700円=-65,700円(満額減税)
⑨ 18,200円+0円=18,200円(定額減税しきれない合計額)
給付金は1万円単位の切り上げとなるため、調整給付金は20,000円となります。
定額減税のタイミングでの詐欺に注意!

定額減税の対象者で控除しきれない場合には、調整給付が行われることがわかりました。しかし、ここで気を付けておきたいことがあります。
今回の定額減税のタイミングで、給付金を装った詐欺の被害報告が上がっているといいます。くれぐれも自治体職員を装った定額減税についての詐欺にはご注意ください。各自治体は、給付金の受給にATMの操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません、と注意を呼び掛けています。
万が一、自宅や職場などに自治体の職員を装った連絡やコンタクトがあった場合は、お金を振り込んだり口座番号を教えたりせずに、すぐに110番通報しましょう。
まとめ
対象者のうち、控除しきれない世帯には調整給付がされる今回の定額減税。ご自身は該当するのかを予めきちんと確認しておきましょう。

























