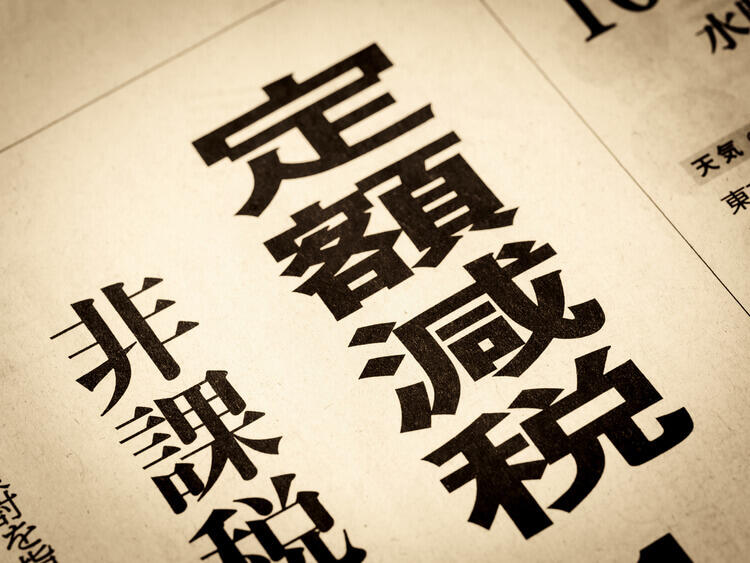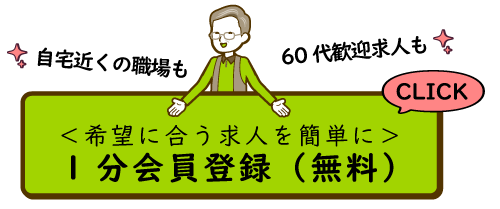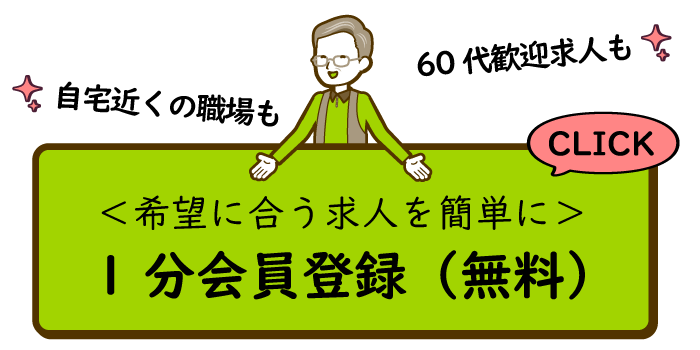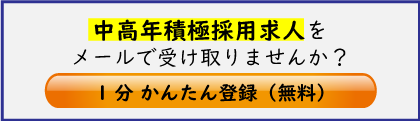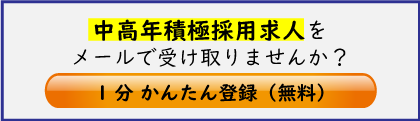2024年6月より開始!「定額減税」に関する気になる疑問を解説
- ちょっと得する知識
- 公開日:2024年5月28日

今年の6月より、定額減税が導入されることになりました。政府は、この制度で国民の税負担を軽減し、経済活性化を図りたいと考えています。しかし、定額減税の方法はわかりにくいところも。今回は定額減税の基本的な解説から、育休中でも対象になる?住宅ローンに影響はある?といった、定額減税に関する気になる疑問について回答します。
この記事の目次
定額減税で所得税3万円・住民税1万円の控除
定額減税は、2024年4月1日に「令和6年度税制改正法」で制定されました。納税者本人とその扶養家族1人につき、所得税3万円・住民税1万円の合計4万円が2024年の税金から控除されるというものです。
ただし、所得制限が設けられているため、所得税にかかる合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外です。その一方で、フリーランスなどの事業所得者は、2024年分の確定申告時に給与所得者と同様の特別控除が適用されます。さらに、所得税や住民税の非課税世帯においては、別途給付金支給制度が設けられることになっています。
定額減税が実施される理由は昨今の物価上昇
定額減税の導入の背景には昨今の物価上昇の影響を減らし、経済活性化を図る目的があります。現在、物価高や経済政策としてあらゆる施策が取られていますが、その中でも定額減税は直接的な個人の可処分所得増加に繋がると、注目を集めているのです。
コロナウイルス感染症は5類感染症へと移行し、私たちはマスク要らずでコロナ禍以前のような生活が送れるようになりました。しかしコロナ禍以降、物価は大きく上昇を続けています。光熱費や食料品の高騰を見ても、その上昇率がお分かりいただけると思います。そんな物価高は生活する私たちの経済的な打撃となり、家計を圧迫しています。
総務省によれば、2023年平均の消費者物価指数は前年比で4.0%の上昇となりました。また、生鮮食品やエネルギーを含む総合指数も前年比で3.2%上昇し、高い水準となっています。そこで政府は、そんな物価高な社会に対応する手段として、税金の一部還元ができる「定額減税」を決定したという訳です。
参考:総務省「2020年基準消費者物価指数」
定額減税の対象者と、減税額の計算方法
定額減税の対象者となる人
定額減税の対象となるのは2024(令和6)年分所得税の納税者であり、合計所得金額が 1,805 万円以下である人です。働き方には関係なく、個人事業主や年金受給者も対象となります。さらに、国内の居住者に限られています。居住者とは国内に住所がある人、または現在まで1 年以上の居所がある個人のことを指します。
定額減税の計算方法
所得税
本人30,000円 + 同一生計配偶者または扶養親族の人数 × 30,000円
住民税
本人10,000円 + 同一生計配偶者または扶養親族の人数 × 10,000円
「同一生計配偶者」とは、その年の 12 月 31 日の現況で納税者と生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が 48 万円以下の人が該当します。さらに、扶養親族についても以下の条件がありますので、注意しておきましょう。
・配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
・納税者と生計を一にしていること。
・年間の合計所得金額が 48 万円以下であること。
・青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払を受けていないことや白色申告者の事業専従者でないこと。
定額減税の実施方法は給与所得者・事業所得者・年金受給者で異なる
定額減税は、給与所得者だけではなくあらゆる人に幅広く恩恵が得られる制度です。減税方法は給与所得者・事業所得者(自営業や個人事業主)・年金受給者によって異なります。所得税と住民税が減税となるタイミングも違うため、それぞれ解説します。
給与所得者の場合
所得税の減税方法
2024(令和6)年6月から控除され、6月だけで減税額を満額引ききれない分は翌月以降に繰り越されます。賞与も減税の対象となるため、6月に支給される賞与で全額が減税された場合は、翌月以降の減税はありません。
住民税の減税方法
住民税は本来6月〜翌年5月にかけて、12分割して給与から引かれます。今回の定額減税では、2024(令和6)年6月分の住民税が徴収されず、7月から2025年6月までの11ヶ月間で、本来の住民税額から減税額を引き11分割した額が徴収されます。
事業所得者の場合
所得税の減税方法
給与所得者ではない自営業者や個人事業主などは、原則として来年の確定申告時に減税さます。ただし、前年の所得を基に計算した納税額が15万円以上である予定納税の対象者は、確定申告を待たずに控除を受けることができます。
2024(令和6)年7月の予定納税より自動的に控除される仕組みとなっているためです。7月で控除しきれなかった場合は、第2期分予定納税から、さらに残りがある場合は確定申告時に控除されます。
住民税の減税方法
住民税は年4回徴収のうち、第1期の2024(令和6)年6月徴収分から減税されます。第1期分で控除しきれない場合は、第2期(8月)以降で控除されることとなっています。
年金受給者の場合
所得税の減税方法
公的年金(老齢年金)は2024(令和6)年6月から減税され、引ききれない分は次の支給時である8月以降に順次減税となります。
住民税の減税方法
年金受給者の住民税は、8月徴収分までの税額が既に確定しています。そのため、2024(令和6)年10月分から減税され、引ききれない分は12月分以降の徴収分から順次減税されます。
定額減税の対象者以外には給付金の支給
定額減税は納税額を減額する制度であるため、所得が基準以下であり納税をしていない層は対象外です。そのような定額減税の対象外となる、住民税非課税世帯には給付金の支給が行われます。
2023年、住民税非課税世帯には「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」として3万円の給付がありました。今後7万円の追加を行い、合計10万円の給付金となります。また、住民税非課税世帯のうち、18歳以下の子どもがいる子育て世帯には、子ども1人につき5万円の追加給付が決定しています。
参考:国税庁「定額減税について」
定額減税のメリットとデメリットとは?
定額減税のメリットは手取り額の増加
今回の定額減税は所得が高いほど減税額が大きくなる「定率」ではなく、所得水準にかかわらず同じ額の恩恵を受けられる「定額」であるため、低所得層ほど実質的な減税効果は高くなる傾向にあります。この制度の大きな特徴としては、給与所得者・公的年金受給者・事業所得者といった様々な納税者に対応しているということです。
国としても、定額減税によって消費の拡大を期待できることがメリットでしょう。現在、物価高騰の影響で個人消費は冷え込んでいます。そのため、定額減税によって税負担が軽減されれば、消費傾向も上向きになることが予想されています。
定額減税のデメリット
一方、デメリットはほとんどないと考えられています。しかしながら、個人事業主などの場合は、源泉徴収が行われないことから、毎月の手取りが増加するということはなく、来年の確定申告のタイミングまでその恩恵を受けられません。
さらに、1人4万円の定額減税だけでは社会の物価高に本当に対応できているのかといった懸念の声が上がっている点は、デメリットに含まれるかもしれません。
こんな場合はどうなる?定額減税に関するQ&A
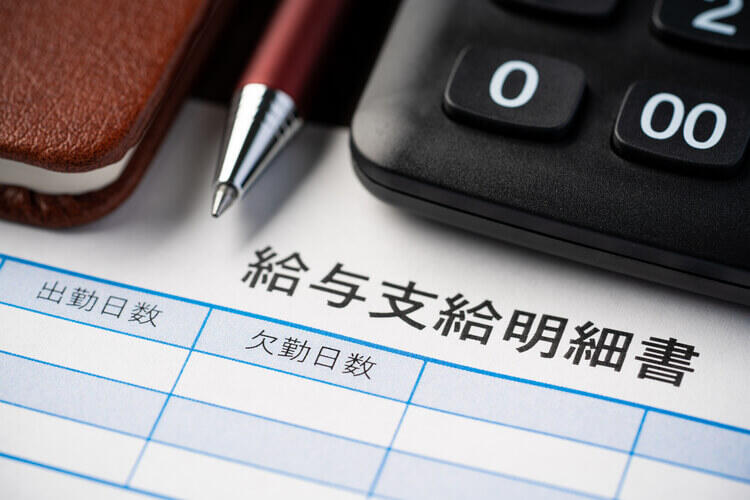
定額減税が始まるタイミングで、さまざまな状況下にある人もいるかと思います。こんな場合はどうするのか、Q&A形式で解説します。
Q.今年の6月2日以降に就職をした場合はどうなる?
A.2024(令和6)年6月2日以後に就職した人は、月次減税の対象となる基準日在職者には該当しないため、月次減税ではなく「年調減税(年末調整時の定額減税)」で対応することになります。
Q.扶養親族の数に変更があった場合はどうなる?
A.月次減税額の計算は、扶養控除等申告書に氏名等が記載されている「控除対象扶養親族」において、居住者である人を基準にして行われます。そのため、扶養親族の数に変更があっても月次減税額の増額は行われません。もし、扶養親族が増えた場合には、年末調整または確定申告によって対応することを覚えておきましょう。
Q.育児休業中の場合でも定額減税を受けられる?
A.育児休業中の者であっても、2024(令和6)年6月1日に在籍していて、扶養控除等申告書を提出している居住者は月次減税の対象になります。ただし、育児休業中で給与の支払いがない場合は、復帰後に支払われる最初の給与又は賞与において源泉徴収される所得税から減税されることになっています。
Q.年金をもらいながら働いている場合はどうなる?
A.年金と給与をもらっている方は、年金からも会社の給与からもそれぞれ定額減税の適用を受けます。年金と給与の重複控除は、最終的に2025年の確定申告のタイミングで精算が行われます。
Q.住宅ローンやふるさと納税に影響はある?
A.定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税には影響しません。
住宅ローン控除への影響
住宅ローン控除は所得税から差し引き、差し引けなかった分は住民税からも差し引くことになっています。しかし、住民税には差し引ける金額が「前年度課税所得×5%、最高9万7500円」までと決められています。そのため、定額減税によって所得税が減ってしまうと、住宅ローン控除の控除額が減ってしまうのではないか、と懸念する方もいるでしょう。
しかし、定額減税と住宅ローンはどちらも受けられる仕組みとなっています。
定額減税は、住宅ローン控除が例年通りに適用された後の税額に適用されます。また、住宅ローン控除が先に控除されたことによって、定額減税分が差し引けなかった場合は、差額を給付金として受け取ることができるのです。
ふるさと納税への影響
ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄付ができる制度です。寄付を行うと、所得税や住民税から控除できるようになっています。
定額減税によって、ふるさと納税の控除額上限の計算で用いる「所得割額」が減ってしまうのではないかと思われるかもしれません。しかし、ふるさと納税の控除額上限は、定額減税を行う前の所得割額を用いて計算されるため、ふるさと納税に関しても定額減税の影響はありません。
Q.給与収入が2,000万円ある場合はどうなる?
A.定額減税の対象者は、合計所得金額が1,805万円以下の方です。給与収入だけの場合、2,000万円を超えると対象になりません。合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいたとしても、給与収入が2,000万円以上の方は定額減税の対象にはならないのです。
Q.臨時的な収入があった場合はどうなる?
A.給与収入が2,000万円を超えていなくても、臨時的な収入があった場合、定額減税の対象外となる可能性があります。株式や不動産の譲渡所得、退職所得など臨時的な所得も合計所得金額に含まれるためです。
例えば、年間の給与収入が1,500万円で、不動産の売却益が900万円あるとすれば、合計所得金額が規定の数値を超えるため、定額減税の対象となりません。
Q.副業している場合はどうなる?
A.副業をしている方は、定額減税の事務処理は扶養控除等申告書を提出している主たる会社で行うとされています。基本的には、複数の会社で定額減税の対象になることはありません。
Q.年内に控除しきれなけれない場合はどうなる?
A.2024(令和6)年に支給される給与に係る源泉徴収税額から控除しきれなかった場合の残額は、調整給付金として支給されることになっています。調整給付の金額は、所得税と個人住民税の控除不足分の合計を1万円単位で切り上げて算出されます。
Q.海外に扶養親族がいる場合はどうなる?
A.今回の定額減税は、国内の物価高騰に対しての減税目的です。そのため、海外に住んでいる扶養家族は対象外です。国内に在住(国内に住所がある、または現在まで1 年以上の居所がある)扶養親族のみが対象であることを認識しておきましょう。
参考:国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A 」
まとめ
急激な物価高の影響は、所得が低い人ほど影響を受けるとされています。なぜなら、所得が低ければ低い人ほど、収入に対する生活費の割合は大きくなるためです。今回の一律4万円の定額減税では、少しでも国民の冷え込んだ消費の解消が期待されています。