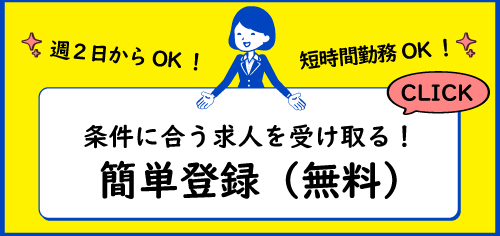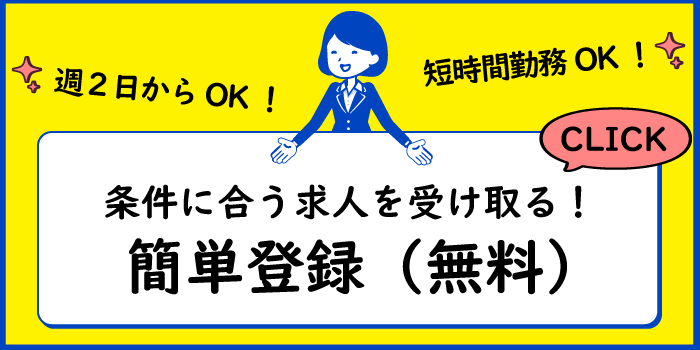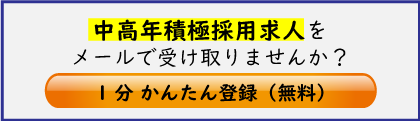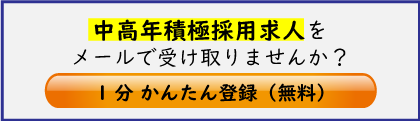2026年4月から始まる独身税(子ども・子育て支援金)とは?負担額や使い道、活用できる税制をご紹介
- ちょっと得する知識
- 公開日:2025年6月19日

2026年4月に始まる「独身税」は、正式には「子ども・子育て支援金」という制度です。子育て支援のために全世帯から徴収されるお金ですが、独身者への負担が増えるにも関わらず、恩恵が少ないために独身税と呼ばれています。今回は子ども・子育て支援金の概要や独身税と呼ばれる理由、負担額などを解説します。また、独身の人でも使える税制や将来に備える方法もご紹介しますので、ぜひご一読ください。
この記事の目次
独身税とは未婚者に対して課される税金
独身税とは、未婚者に対して課される税金のことです。結婚や出産の推奨が目的で、海外では実際に導入された実績もあります。日本では、独身税の導入はまだ始まっていません。しかし、2026年4月から始まる子ども・子育て支援金が、実質独身税ではないかとされています。
独身税が導入される背景
独身税と呼ばれる、子ども・子育て支援金が導入される背景には、子育て支援の強化があります。厚生労働省のデータを見ると、2023年の出生数は72万7,277人で、2022年より約4万4,000人減少しています。また、出生数がピークだった1949年の269万6,638人から、年々減少し続けている状態です。
日本では少子高齢化と人口減少が進んでおり、このままでは経済や制度に深刻な影響を与えると懸念されています。2030年以降には若年人口の急激な減少が予想されており、2030年に入るまでの時期が少子化の流れを食い止められるかどうかのラストチャンスとされています。
少子化を止めるための方法として、今回の子ども・子育て支援金の導入が決定されました。長期的には子どもが増えることで、社会全体の安定を図るという目的もあります。
参照元:厚生労働省 結果の概要
独身税の財源
少子化の流れを変え、出生率を上げていくために、こども家庭庁では子ども・子育て支援金を含めた「こども未来戦略」を掲げています。この戦略では、総額3.6兆円の財源が必要となると見積もっています。財源は、以下の3つで賄われる予定です。
• 既存予算の活用:1兆5,000億円
• 歳出改革:1兆1,000億円
• 支援金制度(新規):1兆円
財源は医療保険に上乗せする形で、2026年〜2028年度にかけて段階的に金額を引き上げていく予定です。しかし、歳出改革や賃上げによって、実施的な負担は生じないようにすると説明をしています。
参照元:こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について
子ども・子育て支援金が独身税と呼ばれる理由

子ども・子育て支援金が、独身税と呼ばれるのには主に以下の2つの理由があります。
• 給与からの天引き
• 独身者には恩恵がない
子ども・子育て支援金は、給与から医療保険に上乗せの形で徴収されるため、税金と同じような立ち位置であると受け取られています。また、独身者は徴収された子ども・子育て支援金の恩恵は受けられません。そのため、独身者の負担が重すぎる、還元を受けられないのでは独身税と同じではないかと、考えている人もいます。
実際には、子ども・子育て支援金は保険料であり子育て支援制度のため、独身税ではありません。しかし、結婚もしていない、子育てもしていない世帯にまで負担を求めているために、独身税だと呼ばれています。
子ども・子育て支援金の負担額
子ども・子育て支援金の負担額は、加入している医療保険制度や所得によって以下のように変わります。
▼加入者1人当たり支援金額
| 2026年度見込み額 | 2027年度見込み額 | 2028年度見込み額 | |
| 全制度平均 | 250円 | 350円 | 450円 |
| 被用者保険 | 300円 | 400円 | 500円 |
| 協会けんぽ | 250円 | 350円 | 450円 |
| 健保組合 | 300円 | 400円 | 500円 |
| 共済組合 | 350円 | 450円 | 600円 |
| 国民健康保険(市区町村国保) | 250円 | 300円 | 400円 |
| 後期高齢者医療制度 | 200円 | 250円 | 350円 |
参照元:こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度における給付と拠出の試算について
人によって金額は変わりますが、年間で3,000円〜5,400円の負担が増える見込みです。さらに、1年ごとに負担額は増額されます。また、子ども・子育て支援金は、すべての世代が子育て支援を行うことを目的としているため、後期高齢者医療制度からも徴収が行われる点が特徴です。
子ども・子育て支援金の使い道
子ども・子育て支援金の使い道は、主に以下のようなものがあります。
| 使い道 | 詳細 |
|---|---|
| 児童手当の拡充 | 所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額 |
| 妊婦のための支援給付 | 妊娠・出産時に10万円の経済支援 |
| 乳児等のための支援給付 | 月一定時間までの枠内で、柔軟な通園ができる仕組み |
| 出産後休業支援給付 | 男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28日間手取り10割相当になるよう給付 |
| 育児時短就業給付 | 時短勤務中の賃金額の10%を給付 |
| 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置 | 国民年金第1号被保険者の子どもが1歳になるまでの期間、国民年金保険料を免除 |
参照元:こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について
子育てに関する支援の設立や、給付のために徴収されたお金は使用される予定です。
子ども・子育て支援金の影響は独身だけじゃない
子ども・子育て支援金は子育て世帯のみが恩恵を受けられるため、独身の人は負担だけが大きくなり、恩恵を受けられないとして独身税とも呼ばれています。しかし、子ども・子育て支援金の影響があるのは、独身者だけではありません。
子どもがつくれない場合やあえて子どもを持たないDINKs世帯も、独身者と同様に恩恵を受けられません。また、子育てがひと段落し、夫婦2人で過ごしている世帯なども同様です。独身者だけではなく、子育てとは距離が離れている人たちにも影響が出るでしょう。
子ども・子育て支援金への反応
子ども・子育て支援金は独身税と呼ばれるほど、恩恵を受けられる人が限られるため、反対意見を抱えている人が多くいます。実際に子育て世帯を支援するのは構わないが、国庫の負担を増やさないで欲しい、給付を受けられないのに負担だけ求められるのは不公平だといった反対意見が出ています。
また、徴収されたお金が正しく運用されるのかが分からない、不透明感も反対意見につながっている要因です。子ども・子育て支援金制度のように、結婚をしていて子どもがいる世帯が優遇され、独身者や子なしの世帯が負担だけを強いられるのは、両者間の断絶を広げる可能性もあるでしょう。
独身の人が使える税制・使えない税制

子ども・子育て支援金制度で独身の人の負担が増えるとされていますが、所得控除を利用できれば、税金の負担は減らせます。以下では、独身の人でも使える税金を抑える制度と、独身の人は使えない制度をご紹介します。
独身の人が使える税制
独身の人が使える制度には、以下のようなものがあります。
• 社会保険料控除
• 医療費控除
• 雑損控除
• 小規模企業共済等掛金控除
• 生命保険料控除
• 地震保険料控除
• 寄附金控除
• 基礎控除
基本的には年末調整の際に利用できますが、医療費控除や雑損控除、寄附金控除は確定申告を行う必要があります。利用できるかどうかは人によって異なるため、一度確認してみましょう。
また、扶養控除は場合によっては独身の人でも利用できる可能性があります。扶養控除は、自身の子どもを扶養に入れて利用している人が多いでしょう。しかし、扶養に入れられるのは6親等内の血族および3親等内の姻族のため、自身の親も対象になります。親を扶養に入れる場合は、以下の条件を満たしている必要があります。
• 生計を一にしている
• 親の収入が一定額以下
• 親が個人事業主の専業専従者ではない
もし同居をしていない場合でも、常に生活費や療養費などを仕送りしていれば、生計を一にしているとみなされます。さらに社会保険の扶養にも入れられる可能性があります。うまく扶養控除を利用できれば、独身の人であっても税額負担を抑えられるでしょう。そのほか、ひとり親や寡婦である場合など、結婚していたが現在は独身である場合は、それぞれの控除を利用できる可能性があります。
独身の人が使えない税制
独身の人が使えない制度についてもご紹介します。
• 配偶者控除
• 配偶者特別控除
上記の2つは配偶者がいる人が利用できる制度のため、独身の人は利用できません。
税制ではありませんが、結婚の祝い金や出産・子育てのための一時金制度なども、独身の場合は使えません。
独身の人が将来に備えていく方法
手取りが減っていくなかでも、将来に備えていくための方法を3つご紹介します。まずは気軽に取り入れられるものから、始めてみましょう。
家計の見直し
最初に現在の家計の見直しを行いましょう。収入金額と支出金額をおおよそでいいので、割り出します。収入に対して、支出があまりにも大きい場合は、支出の削減から始めましょう。削減を検討する際はスマホの利用料やサブスク代、保険料などをメインに見直しを行います。
上記の固定費は、一度見直しをすると節約効果が長く続きます。使っていないサブスクや無駄なオプションはないか、確認しましょう。家計を見直す際は、手をつけやすい食費などの変動費から始める人もいますが、おすすめしません。節約効果があまり見られず、長続きしないためです。まずは固定費から見直しを行い、状況に応じて変動費も無理のない範囲で見直していきましょう。
NISA
NISAは少額から積み立てられる、非課税投資制度です。証券会社や銀行によっては、毎月100円からでも積み立てられるので、無理のない範囲で資産形成ができます。通常、投資で得た利益を受け取ると、20.315%の税金が発生しますが、NISAの場合は非課税です。NISAの基本情報は以下の通りです。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
| 非課税保有期間 | 無制限 | 無制限 |
| 口座開設期間 | 恒久化 | 恒久化 |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有限度額 | 総額1,800万円 | 総額1,800万円(うち1,200万円まで) |
| 口座開設期間 | 長期の積立・分散に適した一定の投資信託 | 上場株式や投資信託など |
| 対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 |
つみたて投資枠と成長投資枠は併用可能なため、自身のライフプランに応じた投資が行えます。コツコツと資産形成をする場合はつみたて投資枠をメインに、一気に積み立てるなら成長投資枠も活用しましょう。
iDeCo
iDeCoは自身で用意する、私的年金制度の1つです。年金制度は1階部分が国民年金、2階に厚生年金、3階は私的年金で構成されています。1〜3階までの年金制度を活用できれば、老後の生活資金を効率よく形成できるでしょう。
iDeCoのメリットは運用益が非課税になる、掛金が全額所得控除になるほか、受け取りを年金方式か一時金方式のどちらかでできる点です。毎月5,000円から積み立てができるため、コツコツと老後の資産形成が行えます。
デメリットはNISAと異なり、途中での引き出しができない点です。原則60歳を迎えるまでは、積み立てて運用したお金は引き出せません。そのため、iDeCoは老後の資金を貯めたい人におすすめです。
まとめ
独身税と呼ばれる子ども・子育て支援金や、独身の人が使える税制などについてご紹介しました。子ども・子育て支援金は子育ての支援を目的に、全世代から医療保険に上乗せをする形で徴収されるお金です。
独身の人のみが徴収されるわけではありませんが、子育て世帯以外には恩恵がないために、反対意見も多く出ています。子ども・子育て支援金の徴収によって手取りが減ってしまう人でも、所得控除をうまく利用できれば、税金の支払額を抑えられるでしょう。
また、将来のために家計の見直しやNISA、iDeCoを活用しておくと老後の資金を確保できます。ぜひ今回の子ども・子育て支援金制度を機に、将来のライフプランなどを見直してみてください。