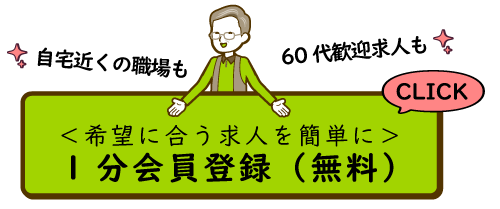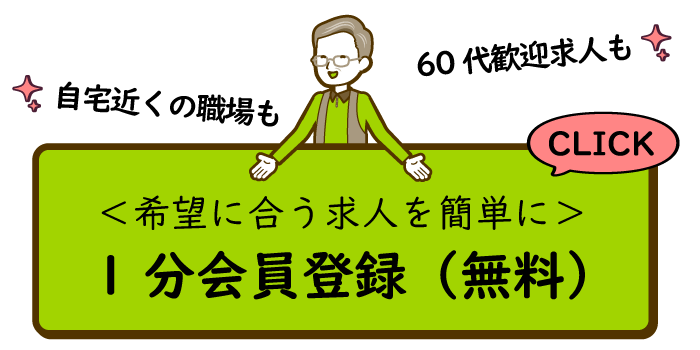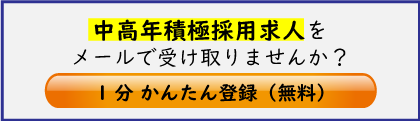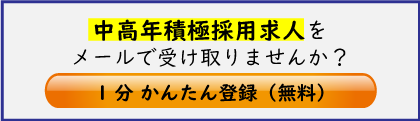社会保険料が高すぎる!?上がる原因や推移、対策まで徹底解説!
- ちょっと得する知識
- 公開日:2025年5月13日

毎月給与から天引きされている健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料の金額が高すぎると感じる人も多いでしょう。今回は社会保険料の種類などの基本情報から、保険料が上がる原因、推移などをご紹介。また、個人でできる対策も解説します。
この記事の目次
社会保険料には5つの種類がある
社会保険料とは、健康保険と厚生年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険の5つのことです。病気や怪我、失業など誰でも起こりうるリスクに対して、社会全体で備えるための制度となっています。それぞれの特徴は、以下の通りです。
• 健康保険
会社に勤めている本人と、その家族が加入できる公的医療保険制度。病気や怪我の時の診察代が、原則自己負担3割となる。
• 厚生年金保険
国民年金の2階部分にあたる年金。国民年金に上乗せして支給される。
• 雇用保険
失業や休業した際に給付などを行う、支援制度。
• 労災保険
就業中や通勤途中に起こった怪我や病気などに対して、保険給付を行う制度。
• 介護保険
健康保険の被保険者が40歳以上になると加入する保険。
それぞれ、保険料の負担割合は異なりますが、健康保険と厚生年金保険、介護保険については会社と加入者で折半です。雇用保険は、会社と加入者で負担しますが、割合は会社の方が多くなります。労災保険は、会社側が負担全額です。
社会保険の加入条件
社会保険への加入が必要なのは、適用事業所と呼ばれる事業所に在籍している人です。正社員の場合は、原則全員が加入対象となります。パートやアルバイトの場合は、適用事業所で働いており、かつ以下の条件に該当する人が加入対象です。
• 週の所定労働時間が20時間以上
• 月額賃金が8.8万円以上
• 雇用期間の見込みが2ヶ月超であること
• 学生ではない
• 従業員数が51人以上の企業
引用元:厚生労働省 パート・アルバイトの皆様へ
所定労働時間は、雇用契約書などに記載された時間を指しており、残業時間は含まれません。そのため、残業によって今週20時間以上働いたので、社会保険に加入する必要があるとはなりません。
社会保険に加入しなかった場合は?
会社員やパート・アルバイトで加入条件を満たしている人は、社会保険への加入が必須です。しかし、なかには高い保険料を支払いたくないからと、加入が必要にも関わらず、加入しないことを考えている人もいるでしょう。
もし、社会保険の加入が必要な人が加入しなかった場合は、事業所に対して6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が課せられる可能性があります。また、立ち入り検査時に検査を拒絶した場合などは、従業員に対して6ヶ月以下の懲役又は、30万円以下の罰金が課せられるでしょう。
さらに、社会保険未加入が発覚し、強制的に年金事務所などへ加入させられた場合は、過去2年間分を遡って保険料を徴収される場合があります。通常、社会保険料は会社と加入者とで折半となるため、加入者側にも請求が届くでしょう。
社会保険料の計算方法
社会保険料の計算には、給与や賞与に対してそれぞれ保険料率を掛けて計算します。給与の場合は4月〜6月に支払われた報酬月額を元に決定された、標準報酬月額を使用します。計算式は、以下の通りです。
• 健康保険=標準報酬月額×健康保険料率
• 厚生年金保険=標準報酬月額×厚生年金保険料率
• 介護保険=標準報酬月額×介護保険料率
• 雇用保険=標準報酬月額×雇用保険料率
例えば、東京都の協会けんぽに加入している標準報酬月額が50万円の人の健康保険料は以下のようになります。
500,000円×東京都の健康保険料率9.81%=49,050円
49,050円÷2=24,525円(保険料は折半のため)
給与から差し引かれるのは、24,525円となります。
また、賞与の場合は標準賞与額に基づいて、以下の計算式で計算を行います。
• 健康保険=標準賞与額×健康保険料率
• 厚生年金保険=標準賞与額×厚生年金保険料率
• 介護保険=標準賞与額×介護保険料率
• 雇用保険=標準賞与額×雇用保険料率
例えば、東京都の協会けんぽに加入している人の標準賞与額が、56万250円の場合、健康保険料は以下のようになります。
560,000円(端数切り捨て)×東京都の健康保険料率9.81%=54,936円
54,936円÷2=27,468円(保険料は折半のため)
賞与から差し引かれるのは、27,468円となります。
社会保険料が上がる原因5つ
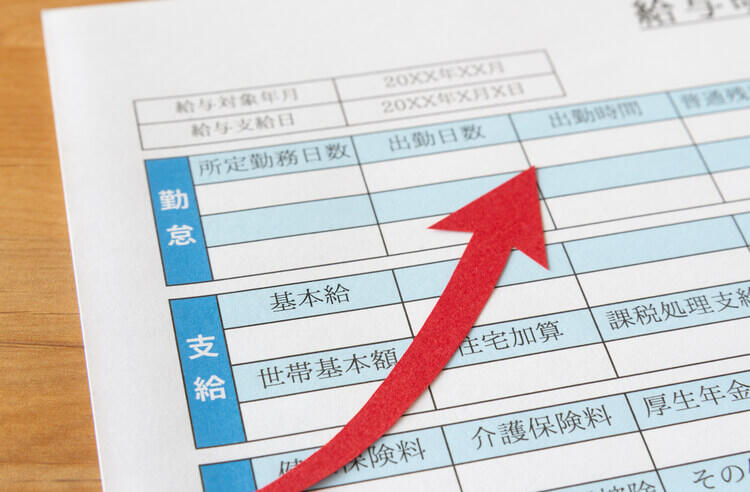
社会保険料が上がるには、いくつかの原因があります。どのような理由で上がるのか、今回は5つの理由をご紹介します。
大幅に昇給した
昇進や転職などによって基本給が大幅に昇給した場合、社会保険料も上がります。基本給が上がると、健康保険料や厚生年金保険の計算で利用する標準報酬月額も上がるためです。また、雇用保険料も給与が上がると、その分保険料が上がっていきます。基本給が上がった場合は、その後の社会保険料も上がると理解しておきましょう。
もらえる手当が増えた
給与のほかに通勤手当や住宅手当など、会社から給付される手当が増えると社会保険料が上がる可能性があります。社会保険料を決める標準報酬月額には、給与のほかに手当の金額も含むためです。
例えば、結婚をして郊外に引っ越しをし、通勤手当や住宅手当、家族手当などもらえる手当の金額が増えた場合、標準報酬月額も上がるため、社会保険料の増加につながります。また、昇給のほかに役職手当などがついた場合も同様です。
負担料率が増加した
社会保険料の計算に利用する、保険料の負担料率が増加した場合、社会保険料も増えます。例えば、健康保険料率は毎年都道府県ごとに見直しが行われます。2023年には13の都府県で、保険料率が値上がりしました。自身の給与や手当は変わっていなくても、加入している協会けんぽで料率の改定があった場合は、社会保険料が増える可能性があります。
2025年問題の影響
まさに現在問題となっている、2025年問題も社会保険料に影響します。2025年問題とは団塊世代の全てが75歳以上となり、医療や介護の需要が増大する問題です。75歳以上の医療費は、75歳未満の約4倍もかかるとされており、かなりの医療費が必要です。
後期高齢者の病院での支払い負担は1割もしくは2割のため、残りはすべて健康保険から支払われています。後期高齢者が増加する2025年以降には、必要な医療費は現在の1.5倍に増える見込みです。
また、年金給付の増加によって年金財政の圧迫、介護保険料の上昇なども予想されています。さらに、後期高齢者の増加と現役世代の減少により、一人当たりの社会保険料負担が今後も増加するでしょう。
社会保障給付の充実
近年、国民の生活をより良くするために、社会保障給付の充実に向けた施策が行われています。厚生年金保険の適用範囲拡大や医療サービスの拡充、子育て支援強化などです。社会保障給付が充実することで、さまざまな恩恵を受けられています。
しかし、財源の確保も必要となっており、社会保障給付が充実する分、社会保険料も引き上げが必要となっています。より多くの人がさまざまな施策やサービスを受けられるようになっていますが、今までは支払う対象ではなかった人も、今後は社会保険料を支払う必要がある、現在支払っている人は金額が上昇するでしょう。
社会保険料の推移について
会社で働いている人は、社会保険料がどんどん増えていると感じている人も多いでしょう。実際に社会保険料はどの程度増加しているのか、推移について解説します。まずは、公的医療保険に加入する国民皆保険体制が整えられた1961年から、現在までの健康保険料率の変化は以下の通りです。
| 1961年 | 2008年 | 2023年 | |
| 健康保険料率 | 6.3% | 8.20% | 10.0% |
また、介護保険料率は、以下のように推移しています。
| 2000年 | 2008年 | 2023年 | |
| 介護保険料率 | 0.6% | 1.13% | 1.82% |
参照元:協会けんぽ 保険料率の変遷
厚生年金保険は、1942年に労働者年金法が始まり、現在の形や料率へと変化しています。その推移は、以下の通りです。
| 1942年 | 2004年 | 2023年 | |
| 厚生年金保険 | 4.9%(6.4%) | 13.58% | 18.3% |
1942年の数字は年収ベースで4.9%、月収ベースでは6.4%となっていました。しかし、徐々に料率が上昇し、現在では18.3%で固定されています。
社会保険料が高すぎると感じたらまずすること
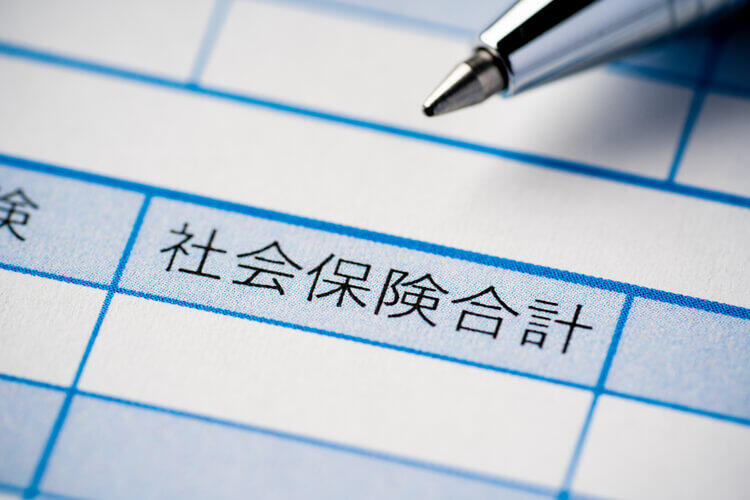
社会保険料は年々上昇しており、今後も健康保険料などは上昇する見込みです。以下では、社会保険料が高すぎると感じた時にできる、対策を5つご紹介します。
4月〜6月の残業を減らす
社会保険料を少しでも減らすためには、4月〜6月の残業時間を減らしましょう。社会保険料は毎年4月〜6月支給の報酬の平均額を元に計算し、9月から翌年8月まで支払う仕組みです。計算に使用する報酬額には残業代も含まれるため、4月〜6月の残業が多くなると、その分社会保険料も増えることになります。少しでも社会保険料の負担を減らすためには、極力残業を減らしましょう。
企業型確定拠出年金を始める
会社の福利厚生に企業型確定拠出年金が用意されている場合は、ぜひ加入を検討しましょう。企業型確定拠出年金は、会社側が掛金を拠出し、従業員が運用を行う年金制度です。企業型確定拠出年金の掛金は給与には含まれないため、社会保険料の計算の対象にはなりません。
例えば、月収30万円の人の場合は、毎月4.5万円が社会保険料として天引きされます。しかし、毎月5万円を企業型確定拠出年金へ拠出していた場合は、月収25万円として社会保険料を計算するため、毎月の天引き額は3.8万円です。企業型確定拠出年金を利用すると、会社から支給されている金額自体は変わりませんが、支払う社会保険料は変わってきます。
各種控除を利用する
直接的に社会保険料を下げる方法ではありませんが、社会保険料が高いと感じる、金額が上がった場合は、各種控除を利用しましょう。生命保険料控除や医療費控除、扶養控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除など、さまざまな控除が用意されています。
利用できれば、所得税や住民税の控除を受けられるため、結果として家計の助けとなります。少しでも支出を減らすためにも、現在利用できる控除はないかをぜひ確認しましょう。
副業を始める
社会保険料を増やさずに収入のみを上げたい場合は、副業の開始も検討しましょう。もし、個人事業主として副業を始めた場合、会社を通さずに収入を得られるため、保険料は発生しません。
現在ではクラウドソーシングで手軽に案件を探せるため、気軽に始められるでしょう。しかし、副業の収入が年間で20万円を超えた場合は、確定申告が必要です。正しい税額を計算して収める必要があるため、忘れずに行いましょう。
固定費を見直す
社会保険料が高い、社会保険料が上がったという人は、まず家計の見直しを行ってみましょう。特に携帯料金や光熱費、保険料、サブスクリプションの代金など、固定費は見直しを行うと効果が長く続きます。無駄なプランに加入していないか、本当に必要なサービスであるかを確認し、必要であればより安いプランや適切なプランへと変更しましょう。
まとめ
社会保険料についての基本情報から、金額が上がる理由、個人でできる対策についてご紹介しました。社会保険は安心して働けるように用意された、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・介護保険の5つを指したものです。
社会保険料は自身の働き方はもちろん、少子高齢化といった問題で年々増加傾向にあります。今後も増え続けるであろう社会保険料で、家計が逼迫されないためにも、今からできる対策を1つでも取り入れてみてください。