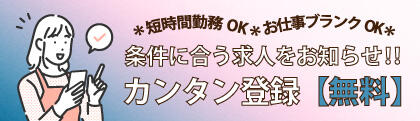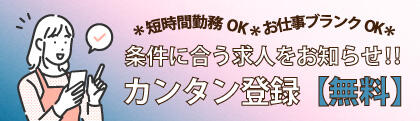年収150万円の壁って?パート主婦が知っておきたい配偶者控除や働き損を防ぐ方法
- ちょっと得する知識
- 公開日:2025年6月 9日

年収150万円の壁とは、配偶者特別控除を満額受けられるボーダーラインのことです。今回は年収150万円の壁や配偶者特別控除の概要、103万円や130万円の壁との違いについて解説します。パートとして扶養内で働いている方、今後扶養を外れて働く可能性のある方は、ぜひ最後までお読みください。
この記事の目次
年収150万円の壁は配偶者特別控除を満額受けられるボーダーライン
年収150万円の壁とは、配偶者特別控除を満額の38万円受けられるかどうかのボーダーラインのことです。配偶者の所得上限額95万円+給与所得控除55万円の合計が150万円のため、年収の壁として設定されています。
もし、パートの年収が150万円を超えると、扶養している夫側で受けられる所得控除の額が段階的に減少します。また、妻側も社会保険料の支払いが発生するなど、手取りが少なくなる可能性があるでしょう。
年収150万円の壁を超えると配偶者特別控除に影響する

パートで年収150万円を超えて稼いでいると、扶養している夫側の配偶者特別控除に影響がでます。控除額がどのように変わるのか、配偶者控除との違いについて解説します。
配偶者特別控除とは
配偶者特別控除とは、一定額以下の所得金額の配偶者を持つ、納税者が受けられる所得控除です。夫がパートで働いている妻を扶養している場合、扶養している側の夫が控除を受けられます。
配偶者特別控除はどちらか片方のみが利用できる制度で、夫婦間で互いに受けることはできません。配偶者特別控除を利用するには、以下のすべての条件に当てはまっている必要があります。
• 納税者の年収が1,000万円未満である
• 民法の規定による配偶者であること
• 納税者と生計を一にしている
• 合計所得金額が年間48万円超133万円以下である
• 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを年内に一度も受けていない、または白色申告者の事業専従者ではない
• 配偶者が配偶者特別控除を適用していない
• 配偶者が給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、配偶者が源泉徴収されていないこと(年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けていない場合は除外)。
この条件のなかで大きく影響するのが、パートとして働いている配偶者の年収です。
配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額は、配偶者の年収に応じて変わっていきます。パートとして働いている妻の年収が150万円を超えると、扶養している夫が受けられる配偶者特別控除の額が段階的に縮小される仕組みです。
自身の年収が150万円以下で配偶者の年収が900万円以下の場合、配偶者特別控除を利用して所得税は38万円、住民税は33万円の控除が受けられます。
①納税者本人の年間合計所得額900万円以下
➁納税者本人の年間合計所得額900万円超950万円以下
➂納税者本人の年間合計所得額950万円超1,000万円以下
| 配偶者の年間合計所得額 | ① | ➁ | ➂ |
|---|---|---|---|
| 48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
参照元:国税庁 配偶者特別控除
配偶者控除との違い
配偶者を扶養している納税者が利用できる控除には、配偶者特別控除のほかに配偶者控除もあります。配偶者控除が利用できるのは、以下の条件に該当している人のみです。
• 納税者の年収が1,000万円未満である
• 民法の規定による配偶者であること
• 納税者と生計を一にしている
• 合計所得金額が年間48万円以下、給与所得のみなら年間103万円以下
• 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを年内に一度も受けていない、または白色申告者の事業専従者ではない
配偶者特別控除との違いは、配偶者の年収です。配偶者控除は、合計所得が年間48万円以下でないと受けられません。配偶者特別控除は、合計所得が年間48万円以上133万円以下までなら受けられます。また、配偶者控除の控除額は以下の通りです。
| 納税者本人の年間合計所得額 | 一般の控除対象配偶者の控除額 | 老人控除対象配偶者の控除額 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
老人控除対象配偶者は、年齢が70歳以上の控除対象配偶者が対象となります。配偶者特別控除とは異なり、控除に影響をするのは納税者本人の合計所得金額のみです。
年収150万円の壁と他の年収の壁の違い
年収の壁には、150万円の壁の他にもいくつかの種類があります。以下では、よく聞く100万円・103万円・106万円・130万円の壁について解説します。
100万円の壁
100万円の壁は、住民税が発生するボーダーラインです。年収が100万円を超えると、多くの場合住民税が発生します。ただし、自治体によって金額が異なるため、場合によっては100万円未満でも住民税が発生する可能性があります。
103万円の壁
103万円の壁は、所得税が発生するボーダーラインです。給与所得者の場合、基礎控除48万円+給与所得控除55万円を年収から引けるため、合計額の103万円までは所得税が発生しません。年収が103万円を超えた場合は、超えた分に所得税率がかけられ税額が決定します。
例えば、年収が115万円だった場合の所得税額は以下の通りです。
年収115万円-(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)=12万円
課税所得12万円×所得税率5%=所得税額6,000円
また、年収が103万円を超えると、配偶者控除を利用できなくなります。
106万円の壁
106万円の壁は、勤務先の雇用人数や月収によって社会保険への加入が必要かを判断するボーダーラインです。社会保険への加入が必要となるのは、以下の条件を満たしている場合です。
• 週の所定労働時間が20時間以上
• 月額賃金が8.8万円以上
• 雇用期間が2ヶ月を超える見込み
• 学生ではない
• 勤務先の従業員数が51人以上
週の所定労働時間は契約時に決定した時間を指します。所定労働時間が10時間だが、一時的な残業で週20時間以上勤務した場合などは該当しません。月額賃金には残業代や交通費などは含まれません。勤務先の従業員数が50人以下でも、労使合意のある会社の場合は、社会保険への加入が必要となります。
130万円の壁
130万円の壁は勤務条件などに関わらず、社会保険への加入が必要となるボーダーラインです。年収が130万円を超えた場合は、勤務先の社会保険もしくは国民年金保険・国民健康保険への加入が必要です。
年収130万円の壁には、交通費や残業代、ボーナスなど支給された全額が含まれます。ただし、2023年10月より収入の増加が一時的なものであると認められた場合、配偶者の社会保険を抜けなくても良いという措置が設けられました。
繁忙期や一時的な人手不足が原因であると事業者が証明書を届け出れば、2年連続までは自身で勤務先の社会保険へ加入する必要はありません。
扶養内パートで働き損を防ぐためには

パートで働く方が働き損を防ぐには、年収の壁ごとにどのような問題が発生するのか、月額収入の上限を知っておくことが必要です。
年収の壁ごとの違いを知る
100・103・106・130・150万円とある年収の壁ごとに、税金が発生するのか、社会保険への加入が必要となるのかなど、条件が異なります。
100・103・150万円は、税金や控除に関する壁です。年収が壁の金額を超えると住民税や所得税の発生、配偶者特別控除が段階的に縮小されます。106・130万円は社会保険の壁です。年収が壁の金額を超えると、社会保険の加入と保険料の支払いが必要になります。
いずれも、壁を超えると手取りが減少するため、家計へ影響を与える可能性があるでしょう。希望する勤務形態や年収に対して、年収の壁がどのように関係するのか、手取りがいくら減少するのかを計算しておきましょう。
月額収入の上限を把握する
年収の壁の種類を知るのと同時に、月額収入の上限額についても把握しましょう。もし、希望する年収が103万円以下の場合、月の収入を8.5万円未満に抑える必要があります。130万円以内で働く場合は、月の収入は10.8万円未満に抑えておかなければいけません。
さらに、そこから勤務時間も割り出しておくと計算がしやすくなります。希望する年収を決めたあとは、月にいくらまでなら稼いで良いのかを把握し、その範囲を超えないように調整をしましょう。
働き損にならない年収はいくら?
パートとして働くうえで、働き損にならない年収はいくらなのでしょうか。パターン別に確認していきます。
扶養範囲内で働く場合は、103万円以内に抑えると収入=手取りとなり、所得税の支払いなどは発生しません。そのため、働き損にはなりません。103万円を超えて働いており、かつ106万円を超えて社会保険に加入していない場合は、120万円以上130万円未満を目指すと働き損になりにくいでしょう。
例えば、東京都で働いている場合、年収が129万円なら所得税約1万3,000円、住民税約3万3,500円で、手取りは約124万円です。年収が130万円になり、社会保険へ加入した場合は、保険料と税金で年間約19万円が引かれるため、手取りは109万円となります。
社会保険の扶養からも外れる場合は、150万円以上を超えて稼いだ方が、手取り額は大きくなります。年収130万円の場合、手取りは約109万円です。しかし、年収が140万円の場合は、手取りが約116万円、年収150万円の場合は手取りが約123.2万円となります。社会保険の扶養を外れて働く場合は、できるだけ150万円以上を目指すと働き損にはならないでしょう。
150万円以上稼ぐのは本当に働き損?
年収の壁を超えて働くと、税金や社会保険料の支払いなどで手取りが減少するため、働き損だと感じ、調整をしながら働いている人が多いのが現状です。しかし、年収130万円や150万円の壁を超えて働くのは、損ばかりではありません。
社会保険への加入によって、以下のようなメリットも得られます。
• 勤務時間や年収を気にせず、安定した収入が得られる
• 厚生年金の受給額が増える
• 失業保険や育休などの対象となる
将来のために備えられる、万が一の時に保障を受けられるのは、メリットとなります。
まとめ
年収150万円の壁や配偶者控除、働き損にならない方法についてご紹介しました。年収150万円の壁は、配偶者特別控除の満額38万円を受けられるボーダーラインです。年収が増えていくと、受けられる控除の額が段階的に少なくなっていきます。
パートで働いている場合は、税金の発生条件や社会保険への加入条件などに注意しましょう。気づいたら扶養から外れていた、手取りが減少していたとなる可能性もあります。少しでも手取りを増やすなら、状況に応じて103万円未満・120〜130万円未満・150万円以上など、収入額を調整しましょう。