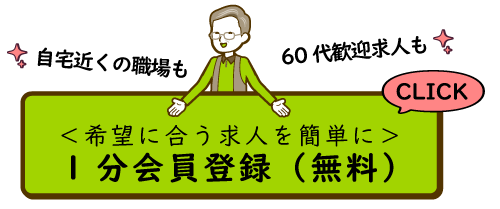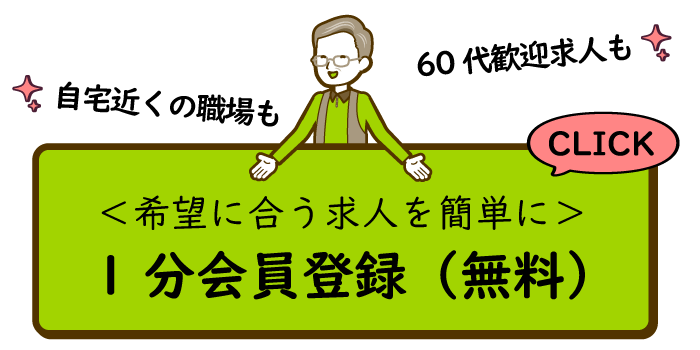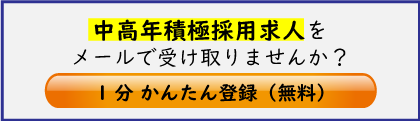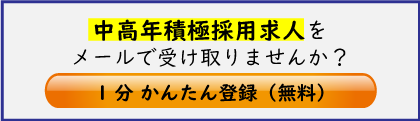知らないと損をする!価格高騰重点支援給付金の給付額と申請方法とは
- ちょっと得する知識
- 公開日:2025年5月27日
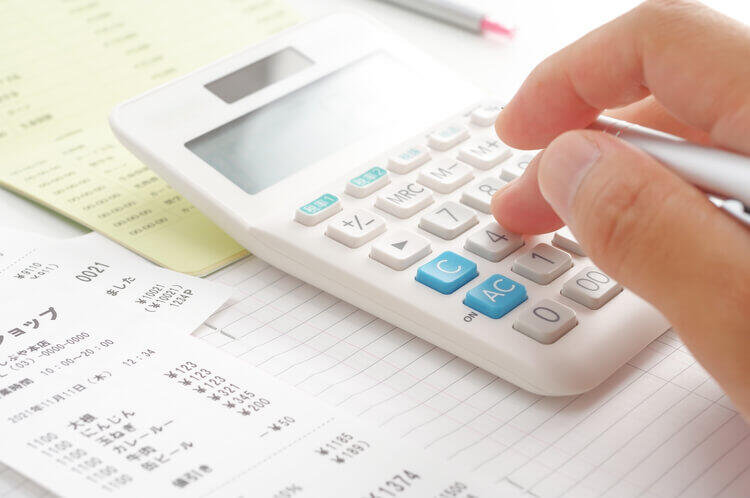
日本では、この30年で食品の物価が1.2倍に上がっているとされています。昨年、そんな状況も踏まえ、価格高騰重点支援給付金の支給が発表されました。本日は、価格高騰重点支援給付金についてまとめていきます。
この記事の目次
価格高騰重点支援給付金の支給が決定!その背景と目的とは?
政府は令和6年、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を閣議決定しました。これに基づき、物価高騰対策として「物価高騰支援給付金」の支給を決定したのです。
そこには、物価高騰が続いている日本の経済事情があります。コロナが5類感染症に移行後、私たちの生活は徐々にコロナ禍以前の様子を取り戻しています。しかし、生活の軸を支える食品やエネルギーを中心に、大幅な価格上昇が止まりません。ニュースなどでも、物価高や値上げについて耳にすることが多くなっています。
日本銀行が実施している「生活意識に関するアンケート調査」では、前年度と比べて「景況感が悪くなった」と回答した人は64.4%以上にのぼり、「良くなった」と回答した人はわずか4.6%でした。
また、現在の暮らし向きについても「ゆとりがなくなってきた」と6割が答え、物価に対する実感も「かなり上がった」と回答した人はなんと73.7%にも上りました。国民の生活環境は今、高い物価高と景気状況の悪化により苦しいものとなっています。
令和6年、厚生労働省は9割以上の企業が「従業員の賃金を引き上げた」あるいは「引き上げる予定だ」との発表をしていますが、実質賃金指数は2024年11月まで4ヵ月連続マイナスで推移しているため、急激な物価高に対しての対応が万全であるとはいえない状況となっています。
さらに、円安も物価高への拍車をかけており、海外から輸入する商品やガソリンや食料品も軒並み、値上げの措置が取られています。今後も円安が進めば、海外製品やガソリンといったエネルギーの値上げも加速してしまうといった懸念は拭えません。
昨今の物価高の原因とは?
日本が置かれている現状によって、物価高が進んでいると考えられます。例えば、国外情勢もその一因でしょう。ロシアのウクライナ侵攻によってエネルギー資源や穀物の供給に影響が生じており、輸送コストだけでなく、穀物や食肉、乳製品といった食料品も価格が高騰しているのです。
日本は世界でも有数の輸入国です。食料品に限っても、多くを輸入に頼っていますから、国外での情勢の変化により物価も変動してしまいます。総務省による「消費者物価指数」では、全ての商品を鑑みた総合指数で約3%の上昇を発表しています。賃金がそれほど上昇しないのにも関わらず、物価だけが高くなっている日本の現状があるのです。
データ元:厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査:結果の概要」、日本銀行「「生活意識に関するアンケート調査」(第101回<2025年3月調査>)」
価格高騰重点支援給付金の概要とは?
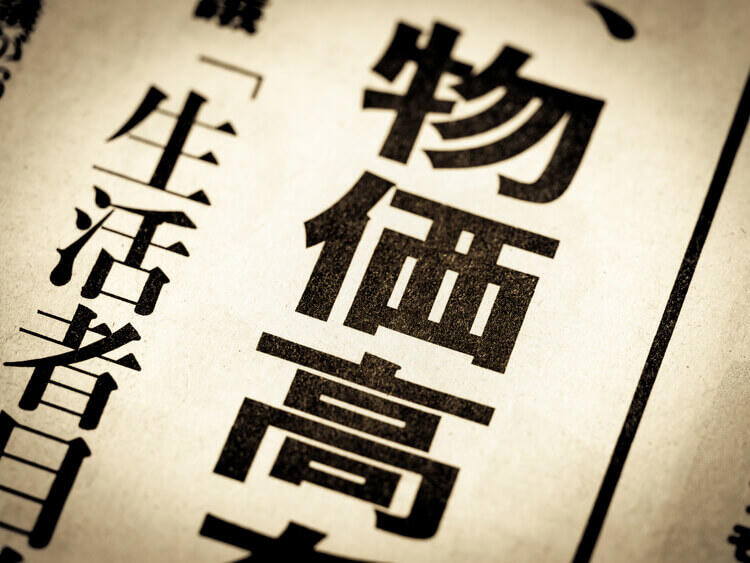
政府は2024年に事業規模が39兆円程度の経済対策を打ち出し、その中でも住民税の非課税世帯を対象とした家計を支援するために「物価高騰対策支援給付金」の給付を決定しました。
今回の給付金の対象になる世帯は、自治体によって要件が異なります。例えば、品川区であれば、令和6年12月13日時点で品川区に住民登録があり、「世帯全員が令和6年度の住民税が非課税の世帯」と「均等割のみ課税となる世帯」です。
ただし、自治体によって「均等割のみ課税となる世帯」は含まないなど違いがあるため、詳細は自身が住む市区町村に確認してみましょう。
価格高騰重点支援給付金の給付額とは?
給付の支援金額は1世帯あたり3万円です。また給付総額は家族構成によって異なります。例えば、同世帯にいる子ども1人あたり2万円が加算されますので、大人2人と子ども1人の世帯なら5万円、大人2人と子ども2人の世帯なら7万円が支給されます。
細かい条件や受給方法などは各自治体にもよりますが、下記の項目に当てはまる場合は対象外となるので注意が必要です。
・同一世帯に、令和6年度住民税が課税されている方が含まれている場合
・同一世帯に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合は
・同一世帯に、租税条約による免除の適用を届け出ている方がいる場合
こういった条件に当てはまるのにも関わらず受給した場合は、給付金の返還を求められるます。
まだ間に合う?価格高騰重点支援給付金の申請方法とは
今回の給付金は、3月末までで受付を終了している自治体もありますが、4月以降も申請を受け付けている自治体もあります。お住まいの自治体のHP等で確認しておきましょう。
多くの自治体では、原則として金融機関の口座への振り込みで支給されることとなっています。「支給のお知らせ」といった通知が届くので、速やかに対応しましょう。申請後、およそ1か月程度で振り込まれることになっています。
現金支給に留まらない支援をする自治体もあります。例えば、北海道知内町は全世帯に地元産米5キロの支給や商品券の配布を掲げています。また、今回の給付金は国籍に関係なく、支給対象世帯の要件を満たしていれば対象となる点にも注目しておきましょう。
内閣府によれば、3月までに約8割の市区町村において給付開始済みで、4月までに9割超、5月までにほぼ全ての自治体で給付が開始される予定となっているとのことです。
なぜ、支給条件が住民税非課税の世帯なのか
今回の受給条件には、住民税非課税の世帯が対象との項目があります。物価高によって家計圧迫を受けているのはどこも同じですが、収入が低い世帯の方が物価高の影響を多く受けるためだとされています。
例えば、物価高騰によって生活費が月1万円増えた場合、月の手取り25万円の家庭では4%の負担増ですが、月の手取り10万円の家庭では月の負担増が10%にもなります。つまり、低収入・低賃金の家計ほど物価高対策が必要とされているのです。
また、厚生労働省によれば、65歳以上の高齢者世帯の3分の1以上が住民税非課税世帯だといいます。元気で働ける現役世代よりも、年金に生活を頼る高齢者に向けての支援を強化するために「住民税非課税世帯」といったボーダーラインを引いたほうがより給付を必要とする世帯に届くという政府の思惑があるのです。
トランプ政権でさらなる物価高に!?支援が増える可能性も

トランプ政権が誕生したことにより「トランプ関税」が今、注目を集めています。これによって日本では輸入品や食料品の価格が上昇するとされており、さらなる物価高が家計に迫っているといいます。そんな中、政府・与党内で全国民に給付金を支給する案が出ています。
現時点では正式な日程は決まっていませんが、2025年度補正予算に盛り込まれる方向で調整中と報じられています。報道によれば、与党内では「1人あたり5万〜10万円」の支給が議論されています。自民党からは5万円前後の案が、公明党からは「10万円必要」との強い主張も出ています。
今後も私たちの生活に関わる給付金等の情報や報道には注目をしておく必要があるでしょう。2024年度の「価格高騰重点支援給付金」の対象にある方で、まだ申請されていない方は一度、お住まいの自治体に確認してみてください。
昔と今の物価と比較!
物価高と聞いてもどのくらい上昇しているのか意識したことはありませんよね。では実際、10年前と今とではどのくらい物の値段が違うのでしょうか。総務省のデータを参考に比べてみましょう。
・食パン
10年前:418円 → 今:478円
・ガソリン
10年前:153円 → 今:169円
・カップ麺
30年前:155円 → 今:236円
・ビッグマック(マクドナルド)
30年前:380円 → 今:480円
・消費税
30年前:3% → 今:10%(軽減税率8%)
このように、数字に置き換えてみるとありとあらゆるものが値上がりしているのがお分かりいただけるでしょう。また、物価高だけでなくこの数十年で増税もされています。
給与に関してみてみれば、2023年の給与所得者の平均年収は459万5000円でした。一方、30年前の1995年の平均年収は457万2000円と、今と比べても日本の平均所得はほぼ上がっていないのです。
大幅な物価高になっているのにも関わらず、賃金は上がっていない日本。生活苦に陥らないためにも、価格高騰重点支援給付金などの支援金は忘れずに申請しましょう。
データ元:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)調査結果」、国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
まとめ
物価高の影響で私たちの生活は数年前と比べて苦しいと言わざるを得ません。そんな中、「価格高騰重点支援給付金」といった給付金が物価高における家計を助ける対策になって欲しいものです。