2025年4月から雇用保険制度が改正!知らないと損する?雇用保険の適用拡大など改正内容をご紹介
- ちょっと得する知識
- 公開日:2025年2月14日
- 最終更新日:2025年3月28日
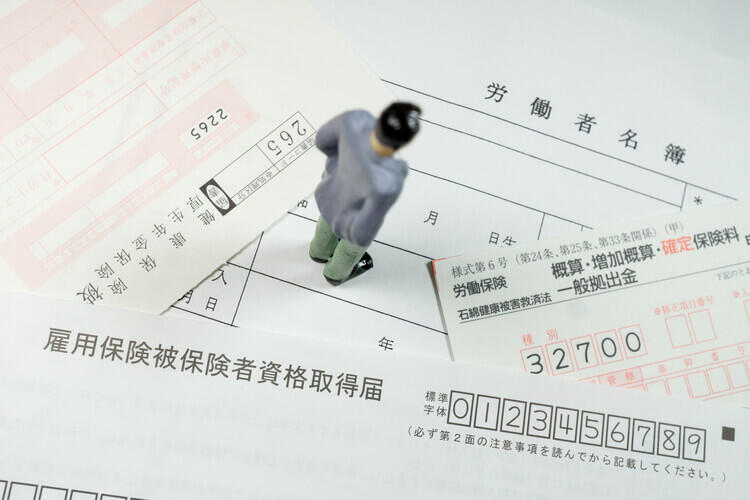
2025年4月から改正雇用保険が施行されます。どのように内容が変わるのか、自身への影響があるか知らない人も多いでしょう。今回は現在の雇用保険の概要から、改正された内容、施行日について解説します。企業に勤めている人はもちろん、今後転職を検討している人や教育訓練を希望している人は、ぜひご一読ください。
この記事の目次
雇用保険のとは、労働者の暮らしと雇用の安定を図る制度
改正された雇用保険の内容を知る前に、現状の雇用保険の概要について確認しましょう。雇用保険とは労働者が失業や休業をした場合に、労働者の暮らしと雇用の安定を図るために給付が行われる制度です。雇用保険は労働者を雇用している会社や、組織に強制的に適用されます。具体的な加入条件は、以下の通りです。
雇用保険の加入条件
雇用保険は労働者を1人でも雇用した場合、強制的に適用される保険です。具体的には、以下の条件で雇用している場合に、加入手続きが必要となります。
• 1週間の所定労働時間が20時間以上
週の所定労働時間は契約をする際に定めた時間が対象となるため、残業などで労働時間が一時的に20時間を超えた場合は、雇用保険の加入条件には該当しません。
• 31日以上の雇用見込みがある
雇用期間については31日以上と雇用契約書に明記されている場合はもちろん、期間の定めがなく雇用される場合も含まれます。そのほか、雇用契約に更新規定があるが、31日未満で雇止めの明示がない場合も、雇用保険の加入条件に該当します。
基本的に、企業の労働者は雇用保険が適用されるでしょう。しかし、法人の代表取締役や個人事業主、公務員のほかに同居親族などは雇用保険の加入対象外です。また、条件を満たしていても、昼間は学生をしている場合は雇用保険の対象外となります。
社会保険と雇用保険の違い
社会保険は広義で健康保険・厚生年金保険・介護保険・労災保険・雇用保険の5つの保険を総称したものです。この場合の雇用保険は、社会保険の中の1つという位置付けです。
また、狭義では健康保険・厚生年金保険・介護保険を社会保険と呼び、雇用保険・労災保険は労働保険と呼ばれます。雇用保険は労働者の生活維持や再就職支援を目的としているのに対し、狭義の社会保険は病気や怪我のリスクに備えて、生活の安定を図ることが目的です。
給付の種類
雇用保険には、主に4種類の給付があります。具体的な給付の種類と内容は、以下の通りです。
求職者給付
内容:基本手当(失業手当)、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、日雇労働求職者給付金
求職者給付の基本手当(失業手当)を受ける場合は、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上、倒産や解雇の場合は6ヶ月以上の期間があれば適用されます。条件に該当していた場合は、ハローワークで手続きをすると再就職するまでの支援を受けられます。
教育訓練給付
内容:教育訓練給付金、教育訓練支援給付金
教育訓練給付は看護師や美容師など、専門職への再就職をするために指定の教育訓練講座を受講するためにかかった費用が一部支給されます。
就職促進給付
内容:就職手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、求職活動支援費
就職促進給付は早期の再就職促進を目的としています。再就職後に雇用保険の所定給付日数の支給残日数に応じて、給付される制度です。
雇用継続給付
内容:高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金
雇用継続給付では、労働者が継続して就労できるように支援するための給付金が用意されています。
参照元:ハローワーク インターネットサービス 雇用保険制度の概要
雇用保険に加入しなかった場合
雇用保険に加入しなかった場合は、失業保険や育児休業手当などの手当が受けられなくなります。雇用している側が雇用保険への加入手続きを行っていなかった場合は、雇用保険法が定める罰則が課せられる場合があるでしょう。自身が雇用保険に加入しているかを確認するには、以下の3つの方法があります。
• 給与明細で雇用保険の控除項目がある
• 雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書を確認
• ハローワークへ問い合わせ
管轄のハローワークに、必要事項を記入した「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」と本人確認書類と一緒に提出すると、確認してもらえます。少しでも不安がある場合は、ハローワークへ問い合わせましょう。
雇用保険の改正内容

雇用保険は2025年4月から、順次改正された内容が施行されます。今回は改正内容について、6つご紹介します。施行前に、ぜひ内容をご確認ください。
雇用保険の適用拡大
現在の雇用保険への加入条件は、週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用が見込まれていることの2点です。2028年10月からは「週の所定労働時間が10時間以上から」となり、より多くの人が雇用保険に加入できるように。
適用拡大となった背景には、雇用労働者の働き方や生計維持の仕方が多様化してきたことがあげられます。雇用のセーフティネットを拡大し、失業時や休職時の保障を多くの人が受けられるようになります。
自己都合離職者の給付制限短縮
現在、自己都合離職をした後に失業保険を申請すると、原則給付を受けられるのは2ヶ月後です。5年以内に2回を超える場合は、3ヶ月の給付制限期間が設けられています。給付までに期間制限が設けられている理由としては、自ら離職をするのは労働の意思がないと捉えられているためです。
しかし、近年は転職する人も増加しており、自己都合退職が増えているために見直しとなりました。改正後は、原則の給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月へ短縮されます。また、離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合は、給付制限が解除されます。
教育訓練やリスキング支援の充実
教育訓練やリスキング支援についても、改正によってより充実します。教育訓練の支援は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合に、費用の一部が支給される制度です。教育訓練給付金の給付率の上限は受講費用の70%でしたが、改正後は80%へと引き上げられます。また、特定一般教育訓練給付金については、従来の給付率40%から50%に引き上げられる予定です。
より個人のスキルアップを強化、推進させていくのが目的です。さらに、教育訓練期間中に不安なく生活を送れるように、教育訓練休暇給付金が創設されます。現状、教育訓練を受けている期間の、生活費などに対する支援はありません。利用するためには教育訓練のために、無給の休暇を取得することと、被保険者期間が5年以上必要です。
給付内容は失業手当の額と同等で、給付日数は被保険者期間に応じて90日と120日、150日のいずれかになります。給付金によって、少しでも不安なくスキルアップができるようになるでしょう。
育児休業給付に係る安定的な財政基盤の確保
育児休業を取得する人が増加しているため、支給額は年々増加しています。そのため、財政基盤の安定が急務となっており、今回の改正で国庫の負担割合が変更となりました。現行は国庫負担割合が80分の1ですが、改正後は8分の1に引き上げされます。また、保険料率が0.4%から、0.5%に引き上げされる予定です。
暫定措置の期間延長
2024年までの暫定措置とされていた、雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、地域延長給付の期間が2年間延長されます。教育訓練支援給付金については、給付率は基本手当の60%を上限とし、2年間の延長です。また、介護休暇給付に係る国庫負担割合を80分の1とする暫定措置も、2年間延長されます。
その他の改正内容
その他に改正される内容として、現在設けられている就業促進定着手当の上限の引き下げと、就業手当が廃止されます。就業手当は所定給付日数の3分の1以上かつ、45日以上を残して再就職した場合に、就業日ごとに基本手当日がくの30%相当額を支給する手当です。
また、就職促進定着手当は早期再就職をし、6ヶ月間定着した場合に再就職によって賃金が低下した人に対して、低下した賃金の6ヶ月分を支給します。2025年の改正では、就職促進定着手当の上限を支給日数の20%に引き下げられる予定です。
子ども・子育て支援法の雇用保険制度の改正内容

子ども・子育て支援法のなかで、雇用保険制度に関連する改正が行われます。新たに創設される出生後休業支援給付と、育児時短就業給付について解説します。
出生後休業支援給付の創設
男性の育休取得をより促進させるため、出生後休業支援給付が創設されました。現在育児休業を取得した場合、休業開始から通算180日までは賃金の67%(手取りで8割相当)、180日経過後は50%が支給されます。育児休暇を取得すると給与が下がるために、育休取得を躊躇する人も多いでしょう。
少しでも育休取得を促進し、育休中の生活費の不安を減らすために、新たに出生後休業支援給付が創設されました。子どもの出生直後から男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に、両親が14日以上の育休を取得すると支給されます。支給日数は最大28日間、支給額は休業開始前賃金の13%相当額となり、育児休業給付と合計で給付率は80%へと引き上げられます。
支給対象となるのは雇用保険の被保険者とその配偶者となるため、専業主婦やひとり親家庭では、配偶者の育休取得要件は適用されません。
育児時短就業給付の創設
育児中の時短勤務についても、新たな給付が創設されます。現状、育児のために時短勤務を選択した際に、下がった賃金分を補償する制度はありません。育児時短就業給付は、少しでも両親が育児をしながら働きやすい環境となるよう創設されました。2歳未満の子どもがいる家庭が対象で、給付率は時短勤務中に支払われる賃金額の10%となります。
雇用保険の改正の施行日など
2025年から始まる雇用保険の改正は、順次施行されます。それぞれの内容の、施行日は以下の表の通りです。※制度のほとんどが、2025年4月1日から施行となります。
| 制度 | 施行日 |
|---|---|
| ・雇用保険の適用拡大 | 2028年10月1日 |
| ・教育訓練やリスキング支援の充実 | 2024年10月1日 |
| ・自己都合離職者の給付制限短縮 ・教育訓練やリスキング支援の充実 ・暫定措置の期間延長 ・その他の改正内容 ・出生後休業支援給付の創設 ・育児時短就業給付の創設 |
2025年4月1日 |
| ・育児休業給付に係る安定的な財政基盤の確保 |
国庫負担割合:2025年4月1日 |
参照元:厚生労働省 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要
まとめ
雇用保険の改正と、現行制度についてご紹介しました。労働者が失業や休業した時でも、安心して生活を送れるようにするための制度が、雇用保険です。企業に勤めている人のほとんどが加入しており、さまざまな給付を受けられるようになっています。
2025年4月には改正された雇用法が施行され、今まで以上に多くの人が給付を受けられるようになります。自己都合離職時の失業保険の給付制限の短縮、出生後休業支援給付の創設など今後利用できる給付はないか、ぜひ今一度ご確認ください。

























