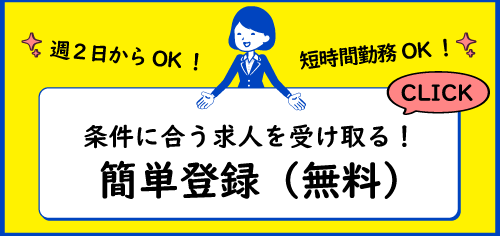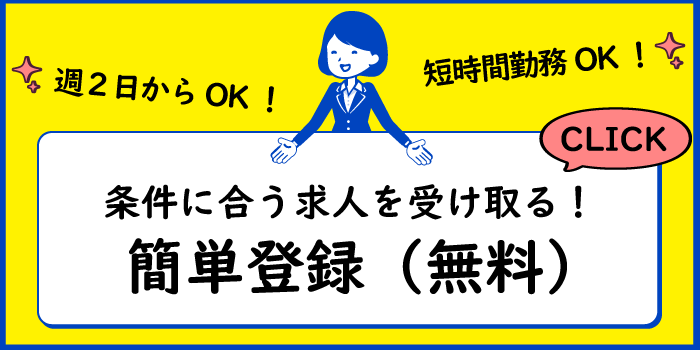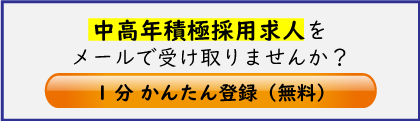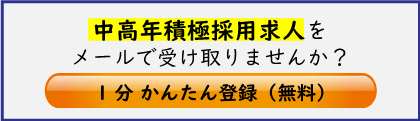フルタイムパートは働き損?メリットやデメリット、損をしないための働き方
- ちょっと得する知識
- 公開日:2023年12月11日

ご自身のお小遣いや家計のために、日々の家事とのバランスを考えて…短時間勤務のパートで働いている方の理由はさまざまです。中にはより収入を増やすために、フルタイムでの勤務を希望する方もいらっしゃることでしょう。今回は現在パートで働いている方、もしくは今後フルタイムでの勤務を検討している方に向けて「フルタイムパート」を解説します。
この記事の目次
フルタイムパートの働き方
フルタイムパートとは
フルタイムとは、正社員と同じ労働時間で働くことを指しますが、フルタイムで働いている方がすべて正社員というわけではありません。雇用形態が非正規雇用であり、正社員と同じ時間で勤務している場合、「フルタイムパート」という呼称が使われることがあります。
フルタイムパートとパートの違い
フルタイムパートとパートの違いは、労働時間にあります。厚生労働省のHPによると、パートの定義は「1週間の所定労働時間が同一の事務所に雇用される通常労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。
つまり、正社員よりも短い時間で働く労働者がパート、正社員と同じ労働時間で働くのがフルタイムパートです。フルタイムパートは、短時間のパートよりも安定して業務を進められるでしょう。そのため、企業側はフルタイムパートの方に対して、短時間パートの方よりも幅広い業務へ取り組んでもらうなど、より戦力となる働き方を期待しています。
引用元:厚生労働省「パートタイム労働者とは」
フルタイムパートと正社員の違い
フルタイムで働いているからといって、必ずしも正社員と同じ仕事内容や待遇というわけではありません。より重要な仕事や、責任のある業務は正社員が担当することがほとんどです。また、パートは時給制が多く、労働時間分のみ賃金が支払われます。賞与や退職金といった手当の対象にはならないため、正社員と比較すると総合的な給与は低いでしょう。
上記のようにフルタイムパートと正社員では、福利厚生や契約期間などさまざまな待遇面での違いがあります。やりがいや給与を求める場合は正社員、働きやすさならフルタイムパートといった、希望の働き方に合わせた選択が必要です。

フルタイムパートは働き損だと言われる理由
フルタイムパートは"働き損"という話を聞いたことがあるかもしれません。フルタイムパートが働き損と言われる理由は、手取りから社会保険料が引かれることにより、自身の手取りが減ってしまうためです。
社会保険加入の条件
・従業員数が101人以上の企業に勤務している
・週の労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込み
・学生ではない
※1:2024年10月から、勤務先の従業員が51人以上の企業が対象に含まれます。今は対象外でも、2024年10月以降に対象となる可能性があります。
引用元:政府広報オンライン
本当に働き損?フルタイムパートのメリット・デメリット
フルタイムパートは社会保険の加入で手取りが減るなど、損に感じる部分もあるでしょう。しかし、それ以上のメリットも存在します。フルタイムパートで働く場合のメリット・デメリットをご紹介します。
フルタイムパートで働くメリット
フルタイムパートでは、収入面や待遇などの面でメリットがあります。自身が希望する働き方を叶えられか、確認してみましょう。
安定した収入が得られる
短時間のパートタイマーと比較した場合、フルタイムパートでは安定した収入が得られます。年収の壁を越えたことにより税金や社会保険料の支払いが発生したとしても、手取りは増えるため経済的な余裕が生まれます。毎月、安定した収入が欲しい人には嬉しいポイントです。
良い待遇が受けられる
フルタイムパートで社会保険に加入する場合は、傷病手当や福利厚生の対象となります。万が一の際に補償を受けられるため、より安心して働けます。
また、短時間のパートよりも有給休暇が多く設けられ、自身の用事や家族の都合に合わせて休みを取得することもできます。場合によっては、賞与をもらえる可能性も。会社によって異なる点もあるため、入社時に確認しましょう。
正社員よりワークライフバランスを取りやすい
フルタイムパートは正社員よりも、ワークライフバランスを取りやすいと言えます。より責任のある業務は正社員が受け持つことが多いため、勤務時間外の仕事の依頼も少ない傾向です。
長時間勤務で収入が増える上に、休みの融通が利きやすい・精神的な負担が少ないなどの働き方を叶えられる可能性があります。私生活をより重視したい場合は、フルタイムパートの働き方にメリットを感じるでしょう。
厚生年金の受給額が増える
フルタイムパートで働くと、短時間のパートタイムよりも厚生年金の受取額が増えます。厚生年金保険料の計算方法は「標準報酬月額×18.3%」、労使折半で支払うため労働者の負担分は9.15%です。
月収が多い分、収める保険料も高くなりますが、将来的に受け取れる厚生年金の金額も上がります。将来に備えて少しでも多くの年金を受け取れるようにしたい場合は、フルタイムで働くことにメリットがあります。
フルタイムパートで働くデメリット
特に気になる体力面や、家計に与える影響についてのデメリットを知っておきましょう。
扶養から外れる
フルタイムパートとして働く場合、年収が103〜130万円を超えるため、扶養から外れてしまいます。健康保険料や国民年金を自身で払う必要があるため、手取りが減ってしまいます。年収が140万円前後の場合は、扶養内で働いていた時よりも手取りが減る可能性も。
また、配偶者の会社によっては、家族手当の条件から外れる場合もあります。家計全体の収入が減ることも考えられるため、扶養から外れた際にどのような手続きが必要か、どのような部分に影響があるのかを事前に確認しましょう。
体力が必要になる
フルタイムパートでは通常のパートタイムと比較して、長い時間の勤務が前提です。週の労働日数も多いため、より疲労がたまります。家事や育児などとの両立を考えると、体力に自信がない方は辛いと感じることもあるかもしれません。
自身の希望する働き方を実現するためには、周りの協力を得ることや、スマート家電、家事サービスの活用などを検討してみるのも良いでしょう。
在職老齢年金が減る可能性がある
在職老齢年金とは60歳以上の人が、働きながら受け取れる年金です。しかし、60歳以上でパートとして働く場合、在職老齢年金が減額される可能性があります。
厚生年金に加入し、基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えると、在職老齢年金の支給は一部または全額停止になります。知らずにフルタイムパートとして働いていると、在職老齢年金が受け取れないため、注意が必要です。
厚生年金に加入しない場合は対象にはなりません。厚生年金の加入対象であるかは、勤務先に事前に確認しましょう。
働き損にならないためのポイント
フルタイムパートとして働いていて、気づいたら働き損だったとならないためにも、事前の情報収集が大切です。ポイントを理解したうえで働けば、働き損を回避できるでしょう。
年収の壁を理解する
フルタイムパートで働く際は、年収の壁をしっかりと理解しましょう。
例:年収130万円を超えて働く場合
年収130万円を超えると、勤務先の規模にかかわらず社会保険に加入しなければなりません。そのため、年収130万円を少し超えるくらいの場合は、保険料の支払いにより手取りが減ってしまいます。支払う金額を考えると、働き損にならない年収は150万円以上が目安です。
また、勤務先が社会保険を適応していない場合は、国民年金保険や国民健康保険に加入する必要があります。保険料は全額自己負担となるため、170万円以上の年収がないと働き損になる可能性があります。
勤務先の状況と併せて、働き損にならない収入を事前に把握しましょう。その上で、家計に必要な額と照らし合わせて働き方を決めることが大切です。
配偶者の福利厚生を確認する
フルタイムパートとして一定の収入を超える場合は、配偶者が会社から受け取っている家族手当や住宅手当などの福利厚生が適用されなくなる可能性もあります。福利厚生の適応に制限がないか、事前に確認しましょう。

まとめ
フルタイムパートは正社員と同様の勤務時間で働きつつ、ワークライフバランスの取れる働き方です。家計のために安定した収入が得られる、厚生年金の受け取り額が増える、といった理由からフルタイムパートを選ぶ方もいるでしょう。
しかし、税金や社会保険料の支払いにより、収入額によっては手取りが減ってしまう可能性があります。以前よりも長時間働いたにも関わらず、手取りが減ってしまうという「働き損」にならないように、事前の確認が重要です。