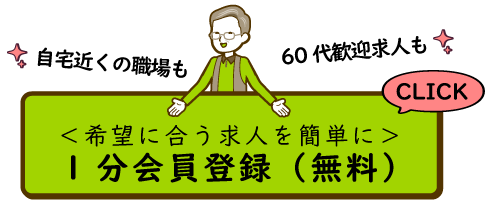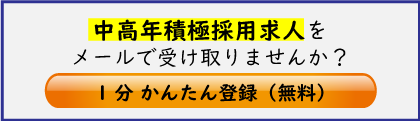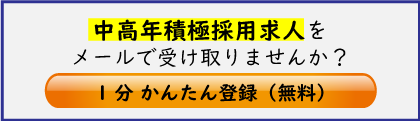人生100時代を生き抜くために、在職定時改定を知っておく!
- ちょっと得する知識
- 公開日:2022年4月18日
- 最終更新日:2024年5月22日

皆さん、2022年4月から「在職定時改定」という制度が導入されることをご存じですか?まだ知らないという方も人生100年時代を生き抜くために、在職定時改定をきちんと把握しておきましょう!
この記事の目次
年金の新制度「在職定時改定」とは?
2022年4月より、厚生年金の「在職定時改定」という制度が開始されます。この制度を一言でいえば、年金を受給しながら働く65歳以上の方にメリットがあるというものです。
厚生年金に一定の加入歴がある場合、65歳になると老齢厚生年金を受け取ることができるのは、皆さんもご存じだと思います。そのため、原則として65歳以上でも会社に勤められている方は、「給与収入」と「年金」という2つの収入があります。しかし、これまでの制度では、厚生年金の保険料を毎月納めていても、65歳以上で働く場合、年金の額がすぐに増額されるわけではありませんでした。
新たに導入された在職定時改定では、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映させる仕組みが取られるようになったのです。つまり、これまで65歳以降は、厚生年金の年金額の増額改定が行われるのは退職等による厚生年金被保険者資格を喪失したときか、70歳になった時のいずれかのタイミングでしたが、これからは働きながら年金が増額するようになりました。
在職定時改定では、年金額を増やしつつ働くことができるようになり、65歳以上の方でも働くことで毎月の収入を増やせるメリットが生まれました。勤労意欲のある方にとっては、働くことでさらなる恩恵が得られるようになったという訳です。
参考:「厚生労働省 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
法律改正前と改正後の制度の違いとは?
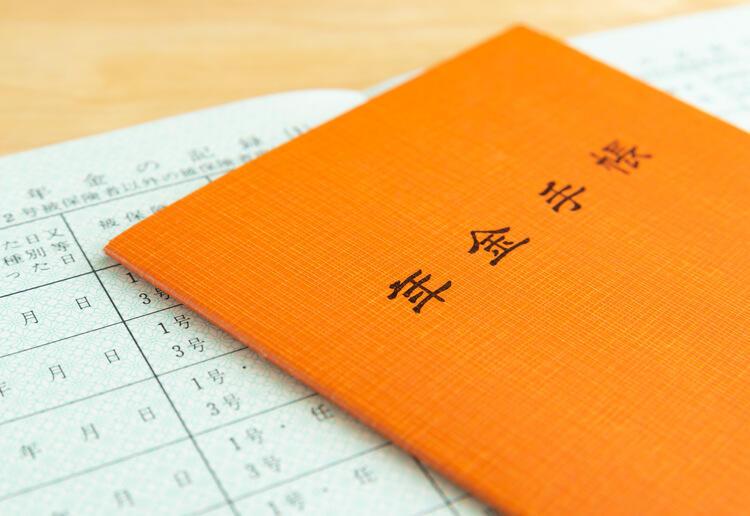
高年齢者雇用安定法などの施行により、多くの高齢者が働けるようになった現代では、年金の仕組みもそれに合わせた改定が必要なのではないか、との議論が高まってきました。そこで、そんな時代の働き方に合わせて制度も新しくなったのです。では、どのような点がこれまでと異なるのでしょうか。
法律改正前は?
厚生年金は、一定の加入歴があれば65歳になると「老齢厚生年金」が支給されます。
しかしながら、これまでは退職または70歳になって厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは、老齢厚生年金の額は改定されませんでした。
つまり、毎月保険料を納めているにも関わらず、その年金を受け取れるのは早くても70歳になってからだったのです。そのため、高齢の従業員にとっては長く働いても、退職しなければ年金の金額には反映されず「働く意欲が湧かない」、「仕事へのモチベーションが低下してしまう」などと制度の在り方が問われていました。
在職定時改定導入後は?
年金制度改正法によって、在職定時改定の制度が新たに導入された後では、65歳以上で仕事を続けながら厚生年金に加入していて、老齢厚生年金の受給資格もある場合には、毎年10月に年金額が改定されるようになりました。
つまり、この制度の導入後は65歳から勤務した場合、退職または70歳までに最大4回の増額が見込まれることになりました。このように、高齢になって働くメリットがより明瞭になった制度でもあるのです。
年金の支給額はどのくらい増加する?
在職定時改定の導入によって、年金の支給額は具体的にどのくらい増加するのでしょうか。
例えば、厚生労働省によると、65歳以降に標準報酬月額※が20万円で厚生年金に加入し、その後1年間勤務して在職定時改定が行われた場合の増加額は以下の通りです。(※標準報酬月額とは、従業員の健康保険料や厚生年金保険料の計算をする際に用いる賃金額のこと)
年間の増加額:約13,000円
1か月の増加額:約1,100円
注意! 高所得者は「年金カット」になる恐れも...!
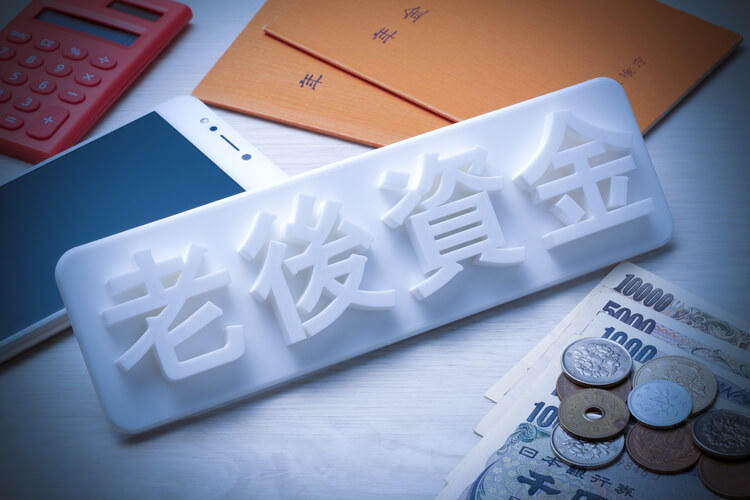
在職定時改定の導入後に注意する点は、在職老齢年金です。
在職老齢年金とは、厚生年金を受けながら働く方の給与と厚生年金の月額の合計額が、基準額50万円を超えてしまうと、年金額の全額または一部の支給が停止されるというものです。
今回の在職定時改定の下、就労しながら年金額が毎年増加していく方にとっては、増額金額によっては年金がカットされてしまう危険性があるのです。このように、在職定時改定は65歳以上の働く方にとってはメリットになるはずが、一定以上の収入の方にとってはかえって年金額を減らされてしまいかねないという注意点があります。
具体的には、老齢厚生年金をもらいながら働いている65歳以上の高齢者の場合、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が50万円を超えると、50万円を超えた額の2分の1の年金額が支給停止になるのです。
支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)×1/2
また、在職定時改定は、65歳以降の厚生年金加入者を対象にした制度です。自営業や業務委託など厚生年金に加入していない方の場合は、厚生年金を受け取りながら働いても在職定時改定の影響はありませんので、この点も押さえておくようにしましょう。
まとめ
より健康に、働く意欲のある65歳以上にとって今回の改正はメリットが多い制度です。これを知った上で、最大限の恩恵を受けられるように、今後の働き方を考えると良いかもしれません。