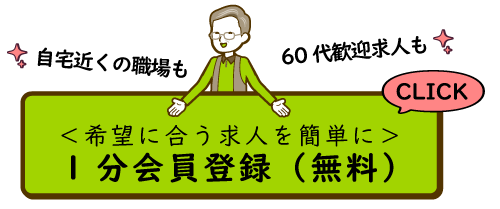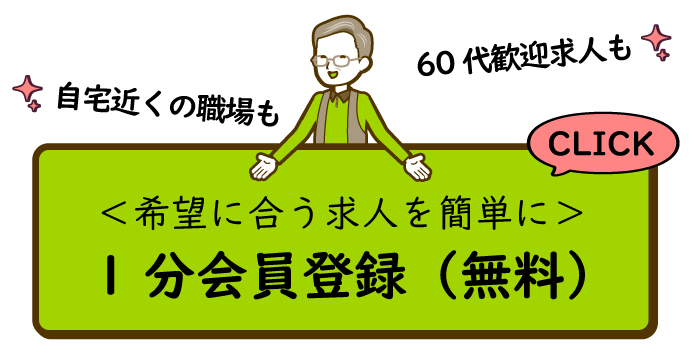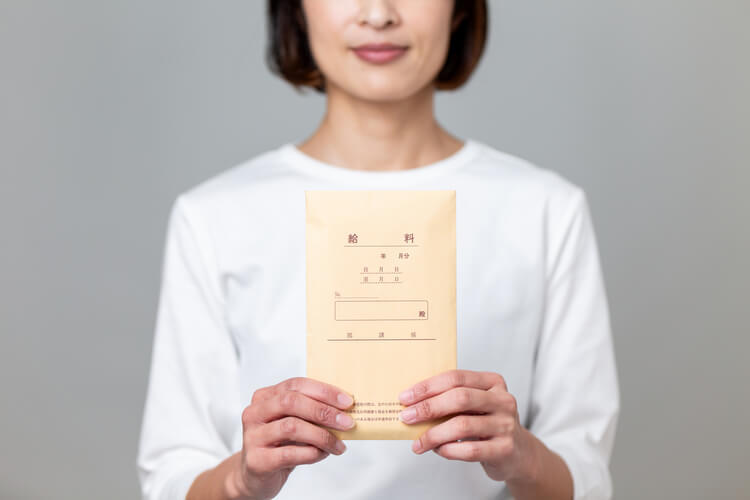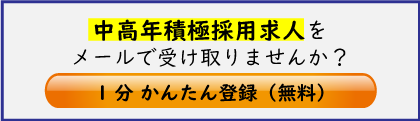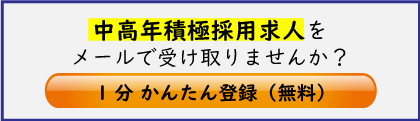定年後も働き続けるメリットとは?経済・社会・健康の視点から解説
- キャリアを考える
- 公開日:2025年3月 3日

寿命が延び、働き方も流動的になった昨今、キャリアにおいて定年後も働き続けるという選択を取る方も増えました。定年後も働き続けるメリットについてお伝えしていきます。
この記事の目次
長く働き続けられる社会になった、日本
2021年に改正された高年齢者雇用安定法により、企業では70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。厚生労働省によれば、70歳までの雇用者への就業機会の確保ができている企業は現在のところ、およそ3割だといいます。
相対的にみればまだまだその数値は高くないものの、数年前には「60歳定年」の企業がほとんどだったことを考えると、長く働ける世の中になってきていると言えるでしょう。
長く働き続けられるようになった背景には、少子化や老後資金の問題など日本社会で考えていかなくてはならない問題が浮かび上がってきます。少子高齢化による社会保障の崩壊はまさに、「老後2,000万円問題」と巷で囁かれるようになったことでも頷けるでしょう。
さらに、人口が減少している現在では、シニア世代は経験や専門知識をもった大切な人材。健康であるうちは長く働いてもらうことが、企業にとっても大きなメリットになのです。そして人生100年時代と言われる今、働きに出ることは活力を得たり、人と接することで生きがいなどを感じたりする機会にも恵まれる大切な機会なのです。
内閣府によると、60~69歳の6割以上が今後も働きたいと考えているといいます。また、60代に比べて「70歳以降も働きたい人」と考える人の割合は少なくなりますが、それでも3人に1人は働く意思があるとのこと。つまり、定年後も働きたいシニア世代は決して少なくないと言えるでしょう。
実際、定年を迎えたシニア世代は別の会社で働き始めたり、リタイア後に再就職を希望したりする人が増えています。シニア世代を対象とした就職セミナーやフォーラムも年々人気を博していますから、アクティブシニアたちの積極的な社会との関わり合いがお分かりいただけると思います。
中には、定年後は働かないで過ごすという選択をする方もいますが、そんな皆さんも趣味を楽しむにもお金がかかる、という壁にぶつかります。ヒューマンホールディングスの「シニアの仕事観とキャリアに関する実態調査2025」によれば、定年後に働いている理由をシニア世代にアンケートしたところ、「生活費を得るため」が一番多く6割の回答となりました。
続いて「社会とのつながりを保つため」と「身体的健康を維持するため」が4割ほどにのぼったそうです。この結果からも、日々の暮らしを金銭的にも健康面でも豊かにするために働くシニア世代が多くいることがわかりました。
さらに、実際に働いている方に聞いたところ、雇用形態は「再雇用」が4割ほどにのぼり、最も多いことがわかりました。次いで「異なる業界・異なる職種で転職・再就職」が挙げられたといいます。このように、定年後に新たなキャリアを築いている人も一定数いることがわかりました。
現在の日本では定年後も働ける社会に変化してきています。そして、シニア層も6割ほどが定年後も働きたいと回答しているとのこと。実際に、65歳以上人口に占める就業者の割合はおよそ25%と言われており、この数値は2010年ごろから上昇し続けているのです。
データ元:ヒューマンホールディングス「シニアの仕事観とキャリアに関する実態調査2025」
定年後も働くメリットその➀ 経済的な観点

今の日本では原則65歳になれば年金がもらえることになっています。その額は、厚生労働省によれば以下の通りです。
・厚生年金保険:約14万4000円(※第1号被保険者、基礎年金月額を含む)
・国民年金:約5万6000円(※受給資格期間25年以上有する者)
この金額で生活をすると考えると、物価高の現在において趣味を充実させたり、旅行に行ったりするには少し余裕がない気がします。また、国民年金の場合には年金だけで生活するのは難しい金額になることがお分かりいただけると思います。
老後に夫婦2人が生活をするために必要な金額はおよそ25万円ほどと言われていますので、年金だけでは心もとない生活になってしまうことが明らかでしょう。
さらに資産についても見てみると、50代の貯金額は単身世帯で平均1,048万円・中央値は53万円、2人以上世帯で平均1,253万円・中央値は350万円。このことからも老後資金を確保できている世帯はあまり多くはないと言えます。
そこで、多くのシニア世代が定年後も働きつづけるという選択肢を持つようになりました。しかも、定年後も働き続けるのならば社会保険に加入ができます。これにより、健康診断や人間ドックなども割安に受けることができるようになったのです。
歳を重ねれば、考えなくてはならないことの一つが健康問題です。会社で定期的に健康診断を行ってくれることもあるので、ご自身で積極的に健康チェックをしなくてよいという点も働くことのメリットの一つでしょう。
また、厚生年金についても満70歳まで加入することができます。厚生年金への加入歴がある人は定年後も働き続けることで「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の両方が受給できるようになるのです。
老齢厚生年金の受給額は、厚生年金の被保険者としての加入期間と、働いていたおおよその給与収入等(総報酬月額相当額)によって計算されますから、定年後も働き続けることで将来もらえる老齢厚生年金受給額を増やすことができます。
さらに、年金に関しては「繰り下げ受給」を行うことも老後を豊かにできる一つの方法かもしれません。例えば、公的年金は受け取りを65歳の受給開始時期から1カ月遅らせるごとに、0.7%ずつ増額されることになっています。
つまり、こういった繰り下げ受給を活用すれば、65歳からの支給予定額が月10万円の方に関しては10年繰り下げれば、75歳以降にはその1.84倍となる月18.4万円が支払われることになるのです。こういった繰り下げ受給も、働くことで月々の収入を安定的に得られるからこそできる方法なのです。
さきほどから指摘していますように、年金額では満足な老後生活を送ることは難しくなってしまいます。調査によれば、定年後も働き続けている人の年収は「定年前の5割程度」が4割ほどといいますから、定年前に月額30万円ほど得ていた方は15万円ほどの収入になるとされています。
世界情勢の変化や物価変動の大きい現代においては、定年後も一定の収入を得ることは老後不安を乗りきるためにも必要なことだといえそうです。
データ元:厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
定年後も働くメリットその➂ 社会的な観点
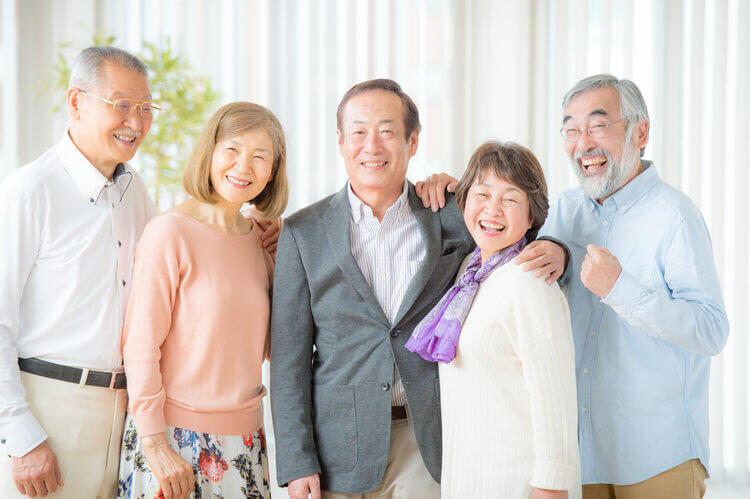
定年を迎えても働き続けるシニアたちは、仕事を通じてやりがいや居場所を見つけられることでしょう。こういった社会においての居場所を確保することは心の平穏にも繋がるとされています。
シニア世代になると子育ても一段落し、仕事でも定年を迎える方がほとんどです。そのため、何もしなければ日がな一日、ボーっと過ごすこともできるのです。しかし、現役世代あれだけ忙しかったのに、いざ毎日が休みとなると急に心に空白ができてしまうことも。
厚生労働省によると、「働いている・何らかの活動を行っている」という人が60代では7割以上、70歳以上でも5割近くに上るといいます。仕事やボランティア活動、趣味といった社会参画を積極的に行っているシニアが多数いるのです。
人は、仕事や趣味の活動場所を失うと、喪失感や孤独感を覚え、心が不安定になってしまうこともあるといいます。それに、人間は遺伝子レベルで、社会的な動物だと言われています。共同体を作り、狩りをして生きていました。
そんな社会的な動物である人間にとって社会に居場所がなくなってしまうことは、生きがいや人との触れ合いをも奪われてしまうことに等しいのです。そのため、私たちにとって働くことは生きがいを感じることができる大切な場とも言えます。
定年後の生活において、社会との接点を失うことは孤立感を引き起こしやすいと言われています。孤独感を覚えることは、心にも体にも決して良いものではありません。仕事を続けることで、人々との交流ができる機会を持つことができるのです。
どんな仕事も自分ひとりだけでは完結しないようにできています。そこで、仕事を通じて誰かに必要とされたり、社会の中に自分の存在意義を見出したりできるのです。また、働くことで、同僚や顧客とのコミュニケーションが増え、孤独感を軽減する効果も期待できるでしょう。
2024年1〜3月に一人暮らしの自宅で亡くなった65歳以上の高齢者はおよそ1万7千人、年間では約6万8千人の高齢者が独居状態で死亡しているとのこと。歳を重ねていくと、不測の事態がいろいろと起こります。自分も含め、パートナーが共に長生きできるとも限りません。
そのため、孤独死や孤立死を防ぐためにも社会においての"居場所"の存在は重要となります。また、働いていれば同僚たちが健康状態や異変に気付いてくれることもあるでしょう。社会との繋がりは孤独をやわらげ、命を繋ぐことにも大いに関係しているのです。
データ元:全国健康保険協会「孤独死について」
定年後も働くメリットその④ 心身の健康的な観点

定年後も働くことで、生活リズムを整えることができます。また、就業は身体を動かすことにも繋がるので健康を保つことができます。歳を重ねると認知機能に衰えてしまうこともありますが、そんな認知機能の衰えも防ぐことができるでしょう。
実は、就業率と健康には不思議な関係があることが近年わかってきています。ある調査によれば、65歳以上の就業率が高い地域ほど、1人当たりの医療・介護費が低くなっていることが数値として表れているのだとか。この結果を見ても、働くことは健康面にもプラスの影響があると言えそうです。
また、働いている方が認知機能の低下が防げるとも言われています。人と関わったり業務を通して日々考えたりすることで、私たちは自分の能力を最大限に使うように努力します。そんな努力の積み重ねが、健康な日々の積み重ねにもなっているのです。
実際、厚生労働省が2005~2015年にかけて実施した調査によると、働いている人の方が働かない人よりも、健康を維持し続けられる傾向があったというのです。働かなくなると、社会との接点が少なくなってしまい、日々にハリがなくなってしまい、健康状態の不安定に繋がってしまうようです。
心の衰えは、外見の老化現象にも直接関係があるとされています。例えば、社会に出れば見た目にも気を遣うためおしゃれをしたり、清潔に保とうとしたりします。しかし、誰も見ていないと思うと「何でもいいや」と、投げやりな生活になってしまうことも。
それに働くことで、適度に身体を動かすことができます。身体を適度に動かすことは筋力維持や体力の向上にも繋がります。このように、働くことと健康には密接な関係があるのです。
皆さんは「退職うつ」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。退職がきっかけとなったうつ病に関して、こう呼ばれているのです。60代以降のうつ病が今、増えているのだといいます。気力が湧かないことを歳のせいにして見過ごされがちになってしまうこともありますが、これはれっきとした「鬱」です。
活発に働いていた人ほど退職うつになりやすいといいますから、睡眠が思うようにできずに食欲がなかったり、悲観的な気持ちになってしまったりした場合には一度、医師の相談を受ける必要があるかもしれません。
まとめ
働くには「傍(はた)」を「楽(らく)」にするという意味もあり、自分以外の誰かを幸せにすることだといいます。働くことはお金を稼ぐことでもありますが、社会に貢献しているともいえます。定年後も働くことで、より充実した人生を送りたいですね。