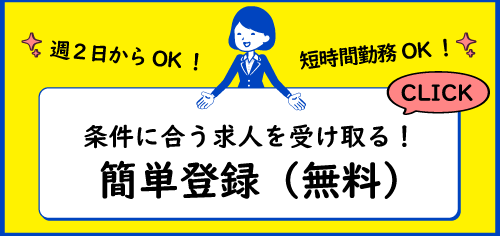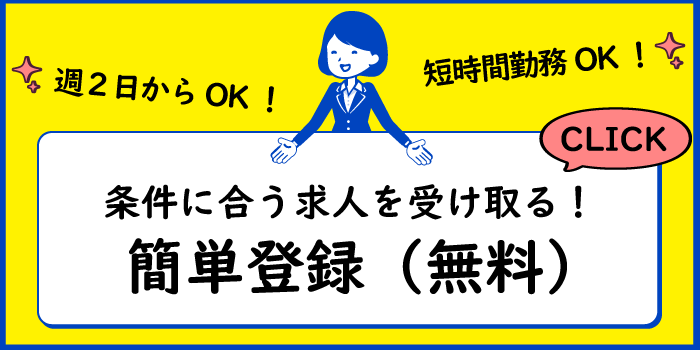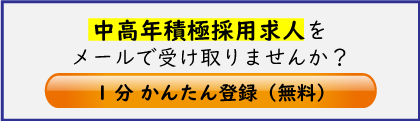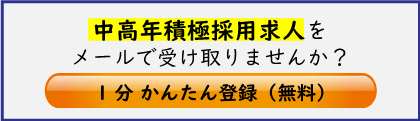パート・アルバイトを掛け持ちしても、扶養内で働ける?注意点や年収の壁を解説
- ちょっと得する知識
- 公開日:2024年6月21日

パート・アルバイトを掛け持ちすると扶養がどうなるのか、といった疑問を持たれる方は多くいらっしゃいます。しかし、年収の壁を越えなければ掛け持ちも可能です。今回は、掛け持ちをしながら扶養内に収めたい場合の注意点や、掛け持ちをした場合に必要となる年末調整・確定申告について解説します。
この記事の目次
時代とともに変化している、扶養内での働き方
現在の日本では、共働き世帯は珍しいものではなくなりました。専業主婦もパートナーを支えるために、扶養内でパートやアルバイトを始める方が増えています。扶養内で働くとは、家計を主に支える方の扶養の範囲内で働くことです。
扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの種類があります。
税法上の扶養では、扶養家族になっていると家計を主に支える方の収入から扶養控除額が差し引かれるため、住民税や所得税が減額されるメリットがあります。
一方、社会保険上の扶養では、家計を主に支える方の勤め先の健康保険に加入でき、厚生年金の第3号被保険者になることができます。そのため、自身で健康保険料や年金保険料を納める必要がありません。
2022年10月、従業員数101人以上の会社で働くパートやアルバイトに対して社会保険への加入義務が発生する年収の壁が106万円になったのは、記憶に新しいことでしょう。また、今年(2024年)10月には従業員数が51人以上の会社に適用されることが決まっています。これにより、社会保険に加入が義務付けられる対象がさらに広がる見込みとなっています。
アルバイトの掛け持ちをしても、扶養内で働ける?
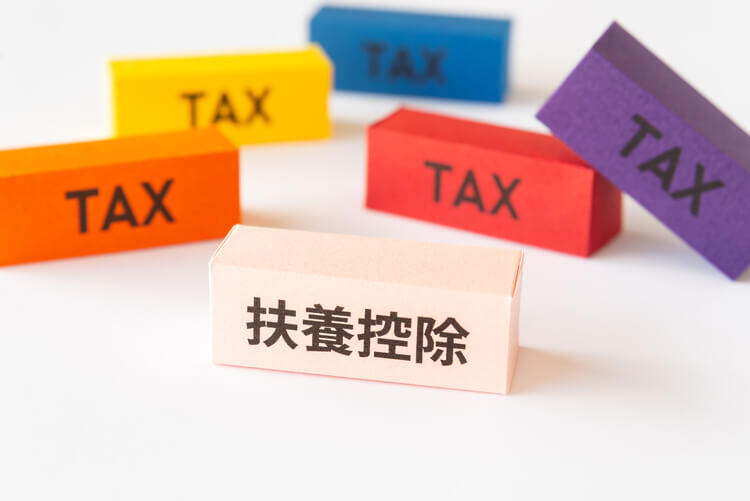
パートを掛け持ちしたいと考えている方は、意外と多いのではないでしょうか。掛け持ちするメリットとしては、毎日の生活に新鮮さを求められたり、これまでにはない経験を積めたり、収入源を増やすことにより経済的にも豊かになったりすることなどがあげられます。
ただ、扶養内で働きたいと思っている方にとっては、アルバイトを掛け持ちすることで扶養を外れてしまうのではないか、といった懸念を持たれる方もいることでしょう。せっかく収入源を増やしても、税金の負担が増えてしまったのでは本末転倒ですよね。
扶養内で働きたいと思っている方は、掛け持ちによって扶養内で働けるのかについて、予め見当を付けておく必要があります。はじめに、掛け持ちを始める前には、必ず職場のルールを確認しておくようにしましょう。就業規則によって掛け持ちが禁止されている勤務先もあるためです。
年収の壁を越えなければ掛け持ちも可能!
掛け持ちをする場合に覚えておきたいのは、アルバイトやパートで働く勤務先の社会保険の加入条件は、その会社1社ごとでの働き方で判断されるということです。掛け持ちをしているからといって、扶養から外れてしまうわけではありません。
つまり、「収入の壁」に留意し、その年収の壁の範疇を越えなければ、掛け持ちをしながらも扶養内で働くことができると言えます。ただし、掛け持ちするうちの1社でも以下の働き方に該当する場合は、扶養内で働くことはできません。
1社でも年収106万以上になる場合
社会保険に加入している従業員規模が101名以上(2024年10月以降は従業員が51人以上)の会社では、年収がおよそ106万円以上になる働き方をした場合には、会社の社会保険に加入することになります。
詳細に数字としてみてみると、月収8.8万円以上、週20時間以上勤務、雇用期間が2ヵ月以上のパートタイマーの方が対象となります。この場合、配偶者の扶養に入っていた人は、扶養から外れることになりますので注意してください。
ただし、これは1社からの収入に限られます。掛け持ちでパートをしていても、各勤務先での収入が106万円以下であれば、扶養内で働くことができます。
合計の 年収130万以上になる場合
掛け持ちをしているかどうかにかかわらず、収入の合計額が130万円以上になると、配偶者の社会保険上の扶養から外れ、自ら会社か国の社会保険に加入することになります。つまり、掛け持ちをしつつ社会保険上の扶養内で働きたい場合は、収入をトータルで考えて出勤を調整しなくてはなりません。
他にも気を付けたい、年収の壁とは?
「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の範囲で働くには、それぞれ「年収の壁」ですみ分けがされています。
・年収100万円の壁
年収が100万円を超えると、住民税の納税義務が発生します。自治体によって住民税の非課税枠は異なりますので、お住まいの地域で確認しておきましょう。
・年収103万円の壁
年収が103万円を超えると、所得税の納税義務が発生します。また、配偶者は38万円の配偶者控除が適用されなくなります。ただし、年収が103万円を超えても、年収150万円までは同額の配偶者特別控除があるため、配偶者の住民税と所得税の額には影響を及ぼさずに済みます。
・年収106万円の壁
特定の条件を満たす働き方をした場合、社会保険上の扶養から外れることになります。パートであっても1ヶ月の所定内賃金が88,000円以上や1週間の所定労働時間が20時間以上の場合は、勤め先の社会保険に加入しなければなりません。
・年収130万円の壁
年収130万円を超えると、勤務先の規模や勤務条件にかかわらず社会保険上の扶養から外れます。パートであっても、勤務先の会社で社会保険に加入が義務付けられます。
・年収150万円の壁
年収150万円までは、配偶者は配偶者特別控除で最大38万円の控除を受けることができます。年収150万円を超えると、配偶者特別控除額は減少します。
・年収201万円の壁
年収201万円を超えると、配偶者の配偶者特別控除の額は0円となります。さらに社会保険上の扶養からも、税法上の扶養からも外れることとなります。
掛け持ちをした場合に、気を付けることとは?

これまで見てきたように、「年収の壁」を越えなければ扶養内で働くことができます。しかし他にも、アルバイトの掛け持ちをする場合に、気を付けておかなければならない点があります。
年末調整をしなければならない
年末調整は、年末に給与から差し引かれてきた所得税と本来納める所得税の再計算し、精算をするものです。パートやアルバイトでも年末調整をする必要があります。1年を通してそのアルバイト先で働いているか、年の途中から年末まで働いている場合、その職場で年末調整を行うことができます。
また、年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申請書」を提出する必要があります。この書類を提出していない場合や提出が遅れてしまうと、年末調整を受けることができなくなるので注意しましょう。
年末調整は掛け持ちで働く場合、1社でしかできません。複数アルバイトを掛け持ちしている場合は、主な収入源を得ている勤務先でのみ年末調整を行うことになります。2社以上でアルバイトを掛け持ちしている場合、1社で年末調整をした後に確定申告をする必要があります。
確定申告が必要になる
掛け持ちでアルバイトをする場合、確定申告をする必要があります。
複数の職場のうち1社の職場で年末調整していたとしても、その他全ての収入について申告をしなければなりません。クラウドソーシングやYouTubeの収益など、給与以外の報酬による所得がある人も確定申告の対象です。
掛け持ち先の所得が20万円以下の場合は、原則確定申告が不要となります。しかし、確定申告によって所得税の還付がある可能性もあるため、事前に確認をしましょう。
確定申告と年末調整の違いとは?
複数のアルバイトを掛け持ちする場合、確定申告と年末調整をしなくてはなりません。では、この2つはどのような違いがあるのでしょうか。
確定申告とは
1年間で得た収入や経費がいくらなのかについて申告し、申告した内容に応じて納税額を決める制度です。1月1日~12月31日の収入総額を計算し、控除されるものを差し引いた額に税率をかけて算出される金額を納税します。
確定申告書に必要事項を記載して税務署に提出するのがこれまでの慣例でしたが、最近ではe-Taxを使ってスマートフォンやパソコンから電子申告することも可能となりました。
年末調整とは
自身で行う確定申告とはことなり、年末調整は勤務先の企業が行います。その年に徴収する所得税の総額を年末に再計算し、算出された税額により源泉徴収された金額が多ければ還付され、逆に少なければ再徴収されます。
気を付けなくてはならないのがパートやアルバイトを掛け持ちした場合、年末調整で税金を計算してもらえるのは収入が多い方の勤務先のみです。アルバイトを掛け持ちしている場合には、メインのバイト先の年末調整を行った後、確定申告をする必要があります。
さらに、年末調整ができるのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している職場のみです。仕事を掛け持ちしていたとしても、年末調整は1カ所でしか行えませんので注意しましょう。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは
収入に対して各種控除を適用させるための申告書です。家族の扶養に入っているパートの方も、パート先で源泉徴収される場合は年末調整の手続きが必要です。
年末調整の注意点とは?
年末調整は1つの職場でしか行えない決まりです。2つ以上の職場に年末調整の書類を提出してしまった場合、正しい所得税額を確定できなくなってしまいます。税額が少ないまま確定すれば、過少申告となる恐れも。
年末調整できるのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している職場のみです。これ以外の職場については、できるだけ早急に取り消しを依頼しましょう。ただし、会社が源泉徴収票の発行を完了している場合、修正をすることはできません。
また、最近ではネットを使って簡単に副業などが行える時代となりました。ネット販売等で得られる収入は雑所得といい、「雑所得」といいます。雑所得は33万円以上だと住民税、38万円以上で所得税の課税対象となることが定められています。
雑所得に対する課税は、たとえ他のパートとの合計収入が住民税の課税基準である100万円を下回っていても、支払わなければなりませんので注意が必要です。そのため、年末調整だけではなく、雑所得があるため確定申告の必要性があることも。後に追徴課税とならないように、しっかりと納税対策をしておきましょう。
データ元:国税庁「令和5年分 確定申告特集」
まとめ
ダブルワーク、トリプルワークが一般的になった現代。一つの職場に縛られることなく多くの経験を積みながらアルバイトの掛け持ちができるようになった反面、扶養面や税金についてしっかりと対処しておかないと多く稼いだ方が損になってしまうことも。掛け持ちしても賢く稼いで、毎日をより良いものにしたいですね。