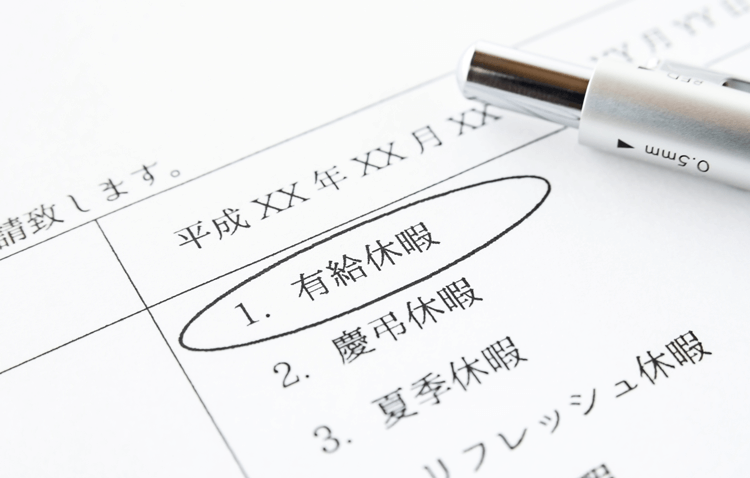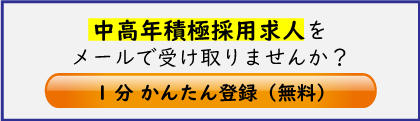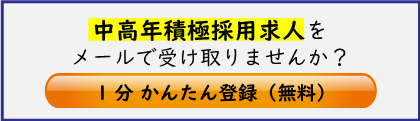周囲の理解を得やすい有給申請理由と伝え方【シチュエーション別】
- ちょっと得する知識
- 公開日:2018年6月 1日

職場の環境にもよりますが、有給申請をどのような理由で出せば良いのか、悩む人も多いかもしれません。労働法で労働者に認められた権利であるにも関わらず、理由や伝え方が不適切だと、周囲の反感を買うリスクも。休む権利を有効活用するためにも、有給申請の基礎知識を今一度理解しておきましょう。
この記事の目次
年次有給休暇について知ろう
年次有給休暇とは?
年次有給休暇とは、業種・業態に関わらず、また正社員のみならずパートタイムにおいても、以下2つの要件が満たされている全ての労働者に与えられることが、労働基準法で定められています。
①雇入れの日から6ヶ月継続勤務
②全労働日の8割以上を出勤
月の所定労働時間が30時間未満のパートタイム労働者であっても、上記の2条件をクリアしていれば認められる権利です。半年以上継続して同じ会社にいる人は、日数の違いこそあれ、等しく権利が生じるもの。また付与される日数は、勤続年数に従って増えていきます。
有給休暇を取得する条件
有給休暇を取得するにあたって、法律上では理由はとくに問われません。そのため、原則的には理由を告げる義務すらなく、旅行やレジャー、習い事など好きなことに使えます。
仮に、有給休暇を取得したことを理由に、ボーナスの査定を下げたり、勝手に欠勤扱いしたりすれば、それは企業側が労働基準法に抵触することに。労働者は法的に保護されているといえます。
会社は有給の使用を拒否できない?
上記を見ると、労働者はどんな理由で、いかなるときも有給休暇を取得することができるように見えますが、使用者には「時季変更権」と呼ばれる権利があります。時季変更権とは、「繁忙期にあたり業務に支障が大きい」「代替人員が見つからない」などを理由として、取得時季を拒否できる権利です。そのため、時季変更権を行使するかを判断するために、「有給を取得する理由を聞く」行為は会社の権利に含まれます。
権利などの法的な話はさておき、有給を申し出て変更を打診されたら、多くの人は「その日は休まないでほしい」という意思と捉えるもの。そうなれば有給取得を諦める、という選択をしてしまうかもしれません。せっかくの権利を活用できるよう、職場の同意を得ながら、有給を取得していくための段取りをご紹介していきます。
早い段階で有給申請する場合

説明したように、制度上は申請理由が「私用のため」でも問題ありません。しかし、働いている同僚や上司が納得するかは別問題。「こちらがこんなに忙しいのに...」という感情を抱かれてしまうと、業務に支障が出てしまうことも。そうなれば、次の有給が取りづらい、という状況になる場合もあります。このような状況を生みださないためにも、できるだけ早めに、理解を得やすい形で申請理由を伝えておくのが望ましいでしょう。
・子どもの学校行事や地域のイベント
家庭を持っている人に理解されやすい理由です。子どもの入学式、PTA、地域のイベントの手伝いが回ってきたといった事情が理由であれば、周囲の納得も得やすいでしょう。特に小学校などでは年間スケジュールが4月に配布されることが多いので、休まざるを得ないイベントが発生しそうな場合は、早めに伝えておくのが得策かもしれません。
・冠婚葬祭
幼なじみの結婚式、親族の年忌法要など、前もって日程がわかっている冠婚葬祭関係は、早めに周囲に伝えましょう。そうすることで、同僚に協力をあおぐなどの工夫もできます。同僚が同じ状況になった時には積極的にフォローする、業務に支障が出ないように前倒しでスケジュールを組むといった配慮も、場合によっては必要でしょう。
前日や当日に有給申請する場合
急な体調不良や親族の不幸など、突発的な事項で有給を使いたい時、どのように申請すれば良いのでしょうか。注意したいポイントは、大きく分けて3つあります。
まず、会社や同僚に対して「申し訳ない」という姿勢を示すことです。どんな事情があるにしても、急な休みは周囲に負担をかけてしまいます。特に、自分ではどうしようもない、非がないと思える事情でも、「恐縮ですがお願いします」という伝え方をすることが、周囲からの協力を得られるポイントとなります。
次に、理由を聞かれた時にきちんと回答することです。法律を盾にして「理由は言いたくない」と拒否し続けた場合、欠勤扱いとすることが認められた事例もあります。労働者も使用者も一方的な利益を得ることがないように、平等な立ち位置を守る決まりが法律です。礼を尽くした対応を常に意識することで、円満な関係を構築できます。
最後に、会社の申請書式を守ることです。メールでの申請が認められている会社もありますが、書類で提出しなければならない決まりのある会社も存在します。事前に就業規則を確認し、有給申請用紙のフォーマットが決まっていれば記入して持参、上司の判断をあおぎます。当日の申請で書類の準備が間に合わないなら、事情をまず相談しましょう。
状況によっては「今からでは代わりの人が見つからないので、忙しいお昼の時間帯まで手伝ってもらえないか」などお願いされることも想定しましょう。本当に何ともならない状況ではない限り、会社の事情も考慮した大人の対応が求められます。
まとめ:マナーを守って有給休暇を申請しよう

周囲との関係性が、有給の取りやすさにつながる
有給の申請に書類が必要な場合は、最初から理由を記載する方法の他、「私用のため」と書類を作成しておき、詳しい理由については口頭で伝える方法もあります。旅行やレジャー目的など、人によっては理解されない可能性もある時は、特に有効な方法です。
大切なことは、どんな理由で有給申請するにしろ、会社や同僚をないがしろにした伝え方は控えること。もちろん休みを取る権利はありますが、自分の権利ばかりを主張してしまうと、なかなか周囲とのコミュニケーションが成り立ちません。また、希望通りに有給取得するには、日常的な行いも判断基準になってきます。
人望が厚い人が休暇を申請する時ほど「ゆっくりリフレッシュして下さい」と、喜んで送り出してくれる可能性が高まるものです。自分だけ有給が取れない、取りづらいことで悩んでいるなら、日頃の身の行いを見直してみましょう。
有給取得が奨励されている流れを活用しよう
社会としては有給休暇取得率を高めようとする方向にあり、アニバーサリー休暇・リフレッシュ休暇など、特定の理由をつけて奨励していこうとする動きが出始めています。部署の中で特定の人だけが我慢することのないように、平等に取得できる環境作りは大切です。
有給を誰もとらない、申請しないことが暗黙の了解となっている環境だったら、転職を検討するのも一案でしょう。本当はやってみたかったことなどがあれば、一度しかない人生。まだまだ元気なうちにやってみるというのも、一つの選択です。年をとってから「あれをやっておけばよかった」という後悔は先に立ちません。
まじめな方ほど有給消化に消極的になりがちですが、休むことは何も悪いことではありません。適切に休むことで作業効率が向上すれば、会社にとってもプラスです。休むことの重要性を今一度考えてみましょう。