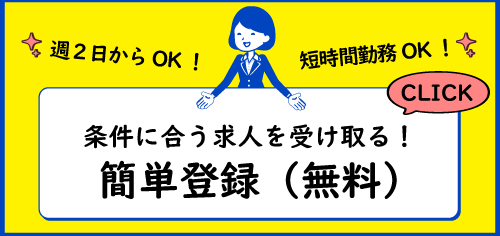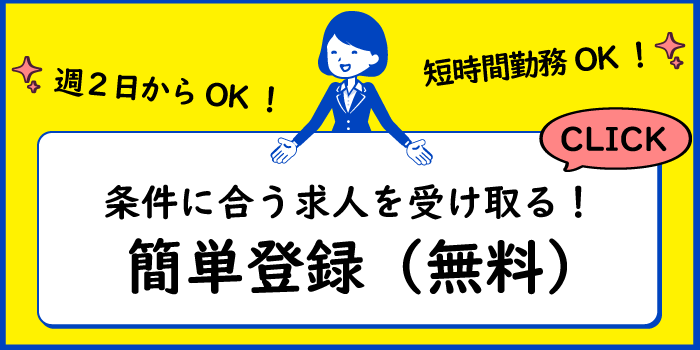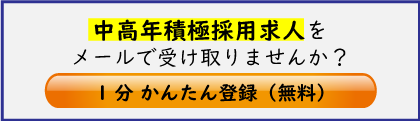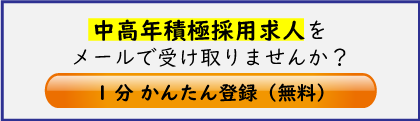2024年12月より「マイナ保険証」が本格的にスタート!どのように利用できる?|「マイナ保険証」の疑問を解決
- ちょっと得する知識
- 公開日:2024年12月24日

健康保険証は2024年12月からマイナンバーカードを基本とする「マイナ保険証」へと移行し、現行の健康保険証は新規発行されなくなります。本日は、「マイナ保険証」について詳しくみていきます。
この記事の目次
「マイナ保険証」が従来の健康保険証代わりに
マイナンバーカードに保険証機能が紐付けされた「マイナ保険証」。まず、マイナンバーカードについて説明します。
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードは、公的機関に申請することにより発行される、氏名や住所、生年月日、性別などが記載された、顔写真付きのプラスチック製のカードです。マイナンバーを証明するだけでなく、身分証明書として利用することができます。
そのため、各種行政手続きのオンライン申請もこのカード1つあればできるようになります。裏面には12桁のマイナンバーが記載されており、ICチップが利用されているため、オンライン上でも安全に本人であることが証明できるのです。
マイナ保険証とは
保険証機能が紐付けられたマイナンバーカードは2024年12月に「マイナ保険証」として本格始動しました。令和6年10月末時点では、すでにマイナンバーカードを持っている約8割が利用登録を完了しているといいます。
「マイナ保険証」は、医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーなどでマイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、従来の健康保険証の代わりに利用することができます。
また、本人の同意に基づき、別の医療機関・薬局で処方された薬の履歴などが他の医療機関や薬局で知ることができるため、薬の飲み合わせや個人の処方履歴に基づいた最適な治療ができるようになるといいます。
ただし、オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局では、「マイナ保険証」が利用できますが、オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証等が必要となりますので、覚えておきましょう。
参考
・デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」
・厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」
「マイナ保険証」を利用するには?

マイナンバーカードを「マイナ保険証」として利用するには、登録が必要となります。登録方法は、主に以下の3つです。
顔認証付きカードリーダーから登録する
医療機関や薬局の窓口等にある顔認証付きカードリーダーで初回登録の手続きを行えば、「マイナ保険証」として登録することができます。方法としては、顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置き、マイナンバーカードを健康保険証として登録するボタンを選択し、画面に沿って手続きを進めます。
マイナポータルから申請する
マイナポータルでも「マイナ保険証」登録をすることができます。マイナポータルにログインをし、「マイナンバーカードを健康保健証として利用する」をチェックし、「登録」を押せば手続きをすることができます。
セブン銀行ATMから申請する
全国のセブン銀行ATMでも「マイナ保険証」の手続きができます。セブンイレブンに立ち寄ることで気軽に手続きできるので、忙しい方はお近くのセブン銀行ATMを利用することをおすすめします。
具体的な利用方法とは?
では、「マイナ保険証」として医療機関や薬局で利用する際には、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。
➀ 読み取り:マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに入れます。
➁ 本人確認:顔認証か、4桁の暗証番号入力のいずれかを選択し、本人確認を行います。
〈顔認証の場合〉画面の枠に顔が収まるようにします。
〈暗証番号の場合〉カード申請時に設定した4桁の暗証番号の入力を行います。
➂ 同意取得:医師や薬剤師に提供する情報(過去の診療情報など)を選んでください。
④ 受付完了:受付が完了したら、カードリーダーからカードを取ります。
「マイナ保険証」のメリットとは?
では、「マイナ保険証」を利用するメリットを見ていきましょう。
適切な診断や薬の処方がされる
「マイナ保険証」では、医療機関を受診した際に薬の情報や健診結果の提供に同意しておけば、過去の履歴から適切な診断や処方を受けることができます。
窓口での限度額以上の支払いは不要に
高額な医療費が発生する場合、「マイナ保険証」であれば高額な医療費が自己負担になったり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをしたりする必要がなくなります。
医療控除申請も簡単に手続きできる
マイナポータルを利用すれば、確定申告時の医療控除も手軽にできるようになります。また、マイナポータルから受けた医療記録が参照できるため、領収書の保管や提出も必要なく、医療控除申請手続きが行えます。
就職や転職後も保険証を待つ必要がない
従来の保険証ですと、就職や転職時に新しい健康保険証の発行を待つ必要がありました。手元に保険証がないタイミングで病院にかかると、一時的に全額医療費用を支払わなければいけないことも。しかし、「マイナ保険証」なら発行申請をしなくとも医療機関や薬局で利用できます。
非常時に安心して活用できる
救急搬送時に「マイナ保険証」で診療情報や薬剤情報、特定検診情報などを医師や医療従事者が把握することで、迅速で正確な救急活動を進めることができます
「マイナ保険証」のセキュリティは大丈夫?
マイナンバーカードは、マイナンバーを証明する書類として利用できるだけでなく、本人確認書類としての利用、各種行政手続きのオンライン申請、各種民間のオンライン取引など、日常生活の中で利用できるシーンが多いのも特徴です。
そんなマイナンバーが保険証として紐付けられた状態あで紛失してしまったり、窃盗被害にあった場合のセキュリティ面は大丈夫なのか、と不安に感じる方もいるかもしれません。では、そんな「マイナ保険証」のセキュリティについて見ていきましょう。
紛失時は一時停止を行える
「マイナ保険証」では、24時間365日のコールセンターが設置されています。もしも、マイナンバーカードを紛失した場合でも、コールセンターに連絡すれば、カードの一時停止をすることができます。
券面に多くのセキュリティ対策が取られている
マイナンバーカードは顔写真付のため、本人へのなりすましを防ぐことができます。また、文字は特殊なレーザーで記載され、複雑な彩紋パターンを施してあるため、券面の偽造を防いでいるといいます。
最低限の情報のみが記載されている
マイナンバーカードのICチップには必要最小限の情報のみが記録されており、税金情報や年金関係情報といった情報は記録されていません。また、ICカードのセキュリティは国際標準である「ISO/IEC15408認証」を取得しており、不正に情報を読み出そうとした場合には自動的にICチップが壊れてしまい、情報が読み取れなくなる仕組みになっています。
利用時には暗証番号が必須
マイナンバーカードは、電子証明書を取得申請する際や各種取扱いの場面では暗証番号が必要となります。さらに、暗証番号は一定回数以上入力を間違えるとロックされる機能になっているため、安心して使えます。
「マイナ保険証」についての疑問点!

続いては、「マイナ保険証」についての疑問をまとめていきましょう。
現行の保険証はどうなるの?
現行の健康保険証等は有効期限の満了後は使えなくなります。ただし、移行措置としてお手元にある有効な保険証は、令和6年12月2日から最長1年間使用することができます。
また、マイナンバーカードを保有していない方には、健康保険組合などの保険者から本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償で交付されますので、マイナンバーカードがなくても医療機関を利用することができます。
「マイナ保険証」が使える医療機関等はどのようにわかる?
マイナンバーカードを健康保険証等として使える医療機関や薬局は厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで知ることができます。さらに、「マイナ保険証」が利用可能な医療機関や薬局ではマイナンバーカードが健康保険証等として使えることがわかる、ステッカーやポスター等が掲示されています。かかりつけ医でも一度確認しておくようにしましょう。
「マイナ保険証」は今後、どのように利用されていくのか
「マイナ保険証」は、医療のDX化を推進するために必要とされており、今後も機能拡充が見込まれています。では、どのような機能が追加されるのか具体的にみていきましょう。
電子カルテ情報の共有
「マイナ保険証」を利用することで、生活習慣病関連検査結果やアレルギーの情報、過去の病名等についても、医療情報・薬局間で共有することが可能となる見込みです。2025年1月から全国約10箇所の医療機関・薬局を対象に、モデル事例として開始され、今後も電子カルテの情報が共有できる医療機関や薬局が拡大していきそうです。
医療費助成の受給者証の一体化
マイナンバーカードは保険証としてだけでなく、難病患者等の医療費助成や自治体の小児医療費助成の受給者証といった、各種医療費助成の受給者証としても使えるようになるといいます。すでに多くの自治体で取組がスタートしており、今後も日本全国区で一体化を進めるとのことです。
診察券としての利用
すでにマイナンバーカードの診察券としての利用が一部の医療機関で始まっており、今後も診察券とマイナンバーカードの一体化が進むとされています。
マイナンバーカード機能をスマートフォンに搭載
2025年度にはスマートフォンにマイナンバーカード機能を搭載するよう、準備が進められています。スマホと連携することで、医療機関や薬局での利用をより速やかに進めることができます。こちらも、順次今後全国の医療機関や薬局に拡大されるとのことです。
まとめ
様々な場所や地域でDX化が進む、現代。そんな中、令和6年12月から「マイナ保険証」が本格的にスタートすることになりました。今後も活用が拡がる見込みなので、まだ申請していない方は早めに検討しておきましょう。