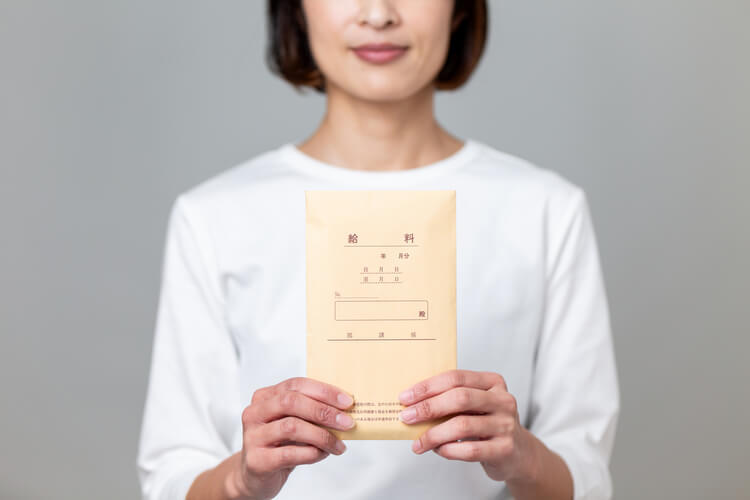ポストオフ制度を考える! 役職定年制度との違いは?
- キャリアを考える
- 公開日:2023年11月29日

ポストオフとは、一定の年齢に達した際に役職を退く制度ことです。組織の活性化や人件費の削減につながるとして、導入を検討する企業も徐々に増えてきました。本日はそんなポストオフについて詳しくみていきましょう。
この記事の目次
ポストオフとはどのような制度?
役職を持つ社員に対し、あらかじめ制定した年齢で役職を解任させるポストオフ制度。一般的に、ポストオフされる年齢の目安は50〜60代の年齢の間です。役職を解かれた社員は従来通りの業務にあたる場合や、別部署へと異動となる場合もあります。
ポストオフ制度を行うことで、企業は組織の活性化とさせたいと考えています。つまり、空いた役職に新たな人材や若手を登用することで、企業内の新陳代謝を促そうとしているのです。また、人件費の削減にもつながるという側面もあります。
なぜ今、ポストオフ制度に注目が集まるのか?
ポストオフ制度が注目されるようになった背景には、主に2つの理由があるとされています。
・組織の活性化
空いた役職に若手社員を登用し重役を担わせることで、実力のある人材のモチベーション維持や会社組織の一新を見込めます。また、優秀な社員の他企業への流出を防げるため、ポストオフ制度で組織全体の活性化が期待できるというわけです。
・優秀な若手の確保
働き方が流動的になってきている現代では、優秀な若手社員を一企業に留まらせておくのは困難です。より条件が良い会社へと移ってしまうことを防ぐためにも、若手にもチャンスがある会社組織の運営が大切になります。若手社員に支持される企業として認知されることで、企業も生存競争に打ち勝とうとしているのです。
役職定年とはどのような違いがあるのか

ポストオフ制度とよく似た言葉に、役職定年制度があります。
役職定年制度では、役職を解かれた後に給与や待遇が悪化することが多く、会社を離職する方も多いのに対し、ポストオフ制度では退任後も給与や待遇が変わらないことが多いため、役職を解かれてからも社内に残る人が比較的多い特徴を持ちます。
また、役職定年制度は年齢のみで処遇を判断されるのに対し、ポストオフ制度は年齢に応じた判断だけではなく、専門性の高さやこれまでの社内への貢献度などで処遇が決定されます。そのため、一定の年齢の基準によって役職が解かれる決まりはなく、その人物を総合評価したうえで必要であれば任を解きます。
「まだこの人にはこのポストで続けて欲しい」との声があれば、役職がついたまま定年まで働くこともできるという訳です。ただし、ポストオフ制度の評価項目には年齢に対する能力も検討材料になってくるため、企業からは優れたパフォーマンスを発揮することを期待されています。
ポストオフ制度のメリットは?
ポストオフ制度のメリットをみていきましょう。
・人件費を削減できる
ポストオフ制度は、人件費を大きく削減できる制度といってよいでしょう。これまで培ってきたスキル持つ中堅社員は、企業にとって貴重な戦力です。実績とスキルが優れた社員に長く活躍してもらえる上、人件費というコストは大幅に抑えられるのです。
・風通しのよい職場になる
年功序列によって生まれるトップダウン気質な空気がなくなり、これまでの厳しい上下関係の傾向は弱まります。若手も意見や発言できる職場になることで、自由闊達な雰囲気が漂う社内になるでしょう。年齢に寄らない組織運営が目指せるのです。
・社員の能力を適正に評価できる
企業側は役職を外れた社員を、個人として正当に評価することができます。社員にとっても役職者の枠の中ではなく、個の社員として評価されることになります。このように、ポストオフ制度によって適正な評価を社員に下すことができるのもメリットでしょう。

デメリットにはどのようなものがあるのか?
では、ポストオフ制度のデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
・モチベーションが落ち、離職の可能性が高まる
ポストオフ制度によって社員のモチベーションが低下し、離職に繋がってしまう場合も。これまで経験したことがない業務に戸惑いを感じたり、給与などの待遇の悪化が起こってしまう点もポストオフ制度を導入するデメリットでしょう。
・新しい関係性に悩む
若手社員が非管理職となった先輩社員との関係に悩むことも、デメリットの一つでしょう。また、その逆も然りで部下が上司となった社員にとっても、コミュニケーションへの戸惑いがあるでしょう。そうした人間関係の悩みや弊害は、業務上の支障になってしまいます。
・業務内容が合わなくなる
業務の内容や環境が新しくなることで、上手く馴染むことができず強いストレスを抱えてしまう社員も出てしまいます。長年培ってきた能力を活かせずに思い悩んでしまった末に、心身に支障をきたして退職に至る場合も。
ポストオフ制度では周りの配慮も必要ですが、本人の意向を聞ける場を企業で設けることも求められるでしょう。
今後の日本経済のキーを握るのはシニア層
現在の日本では少子高齢化が進み、労働人口の確保が企業にとっても当面の課題となっています。若手の人材確保は企業間で激化し、今後ますます難しくなるでしょう。そんな中、高年齢者雇用安定法が改正され、シニア人材活用に向けた取組みは日本社会全体で進んでいます。
若手に頼りすぎず、できるだけミドルシニア層を確保し、少ない人数でも生産性を上げることが企業のテーマの一つでもあるのです。また、シニアを採用することで助成金を設けるなどして、国も企業へ働き手にシニアを活用できるようにと積極的に求めています。
厳しい財政状況下の中、財源確保のために少しでも優秀な人材を会社に確保する施策として導入された、ポストオフ制度。制度を導入するにあたっては、ポストオフ制度の対象となる社員に不安を与えないためにも、企業側も丁寧な説明やサポートが必要不可欠になってくるでしょう。
※データ元:厚生労働省「65歳超雇用推進助成金」
まとめ
ポストオフ制度は企業の財政問題を抜本的に変革できる制度として注目を集めています。今後制度導入が広がるに従って雇う側にとっても、雇われる側にとっても様々な観点で議論される話題の一つでしょう。