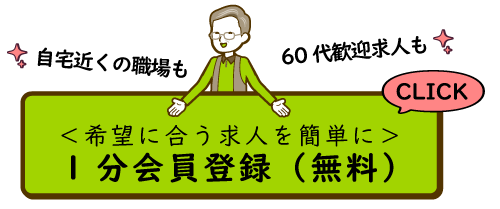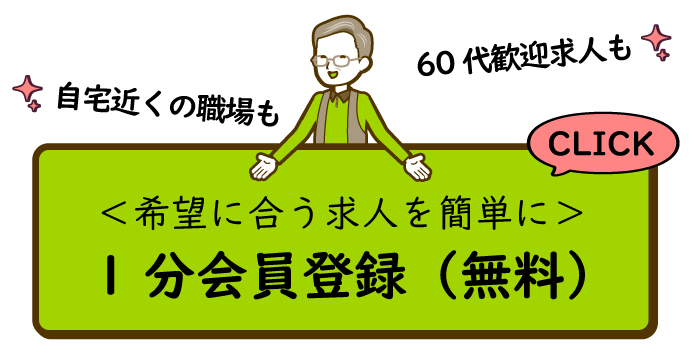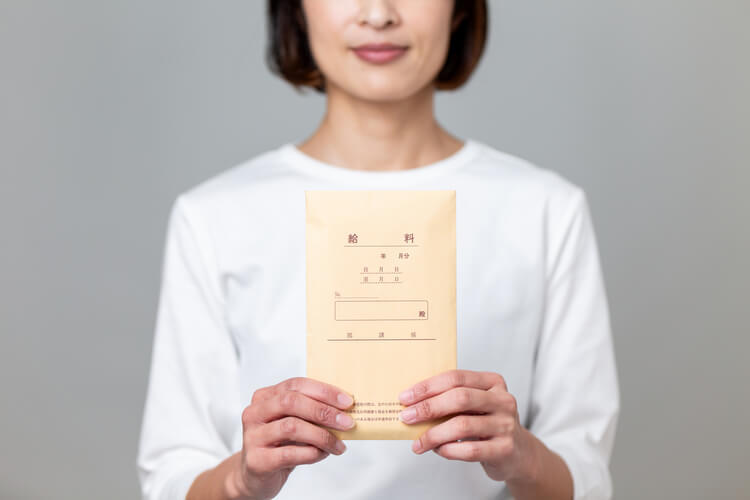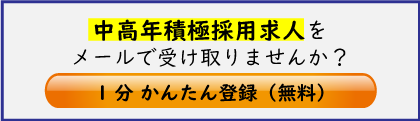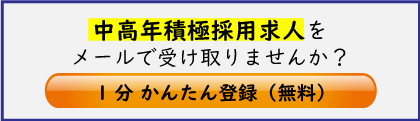知っておけば安心! 役職定年とは
- キャリアを考える
- 公開日:2023年10月26日

ミドルシニアを迎えるにあたり、知っておかなければならない“役職定年”。会社員の方にとっては「こんなはずではなかった」とならないためにも、ぜひ覚えておきたいキーワードです。今回は、役職定年の解説や、メリット・デメリットをお伝えします。
この記事の目次
役職定年とは?
役職定年制とは、ある年齢に達した社員が部長や課長などといった役職から外れる制度のことです。会社に定年制度があるように、役職にも定年があるという風に考えればわかりやすいでしょう。
こうした役職定年制度の背景には、働き方改革によって会社員自体の定年が延びたことがあります。日本はこれまで年功序列や終身雇用による働き方が一般的でしたが、いつしかそうした働き方は流動的になり、働く環境自体が一変しました。
そんな中、企業側も勤続年数や年齢による管理職を置いておくことがコスト的な負担になってきたのです。そこで、人件費が嵩む大企業などでは徐々に役職定年制度が導入され始めました。役職定年の年齢は企業によって様々ですが、多くの企業は役職定年を50代後半に設定されています。
役職定年制度の目的とは?
企業が役職定年制度を導入する目的は、大きく2つの理由が考えられます。
人件費を抑えるため
終身雇用や年功序列制度が代表的な日本企業では、年齢が上がるごとに役職がつくため、企業年数が長い社員を抱えるほど人件費は圧迫されます。しかし、ある程度の年齢で役職を解くとなれば、優秀な人材を抱えたまま、役職手当などの人件費は抑えることができるのです。
組織改革と若手のモチベーションアップを図るため
IT企業などでは役員も数年で入れ替わる仕組みを取っているところもありますが、古い体質の企業は役職を持ったメンバーはあまり変動しません。そのため、組織体制が凝り固まった企業では、若手のモチベーションが下がり事業運営がうまくいっていない場合も。
そこで、役職定年を取り入れ、ある一定の期間でポストが空くことを社員に示すことで、組織改革に乗り出している会社もあるのです。
※データ元:人事院「民間企業の勤務条件制度等調査」
役職定年のメリット・デメリット
それでは、役職定年制度のメリットとデメリットを見ていきましょう。
役職定年のメリット
・組織の活性化
長期にわたって同じ人物が役職に留まることがなくなり、人員の入れ替えが定期的に行われます。それにより、ポストにつくチャンスが多く生まれ、新しいアイデアや意見を言える環境が構築されます。また、優秀な若手が早いうちから役職を目指すこともできるため、若手の成長を早めることにも繋がるでしょう。
・人件費の圧縮
年功序列制度を採用している多くの企業では、年齢を重ねた社員が高位の役職に就き、より多くの給料をもらう体系になっています。しかしながら、年齢を重ねた社員の役職と能力が見合っていないことも少なくありません。
そうした場合に役職定年を採用する企業では、リストラや人員削減などの配置を行う手間をかけることなく、人員整理がしやすくなり、人件費を抑えることができます。

役職定年のデメリット
・モチベーションの低下
役職に就いている従業員にとっては、成果を上げていても決まったタイミングで役職を退かなければならないため、モチベーションが低下してしまうことも。また、役職定年のタイミングで優秀な人材が退職してしまう場合もあります。
さらに、役職定年を迎えると役職手当が付かない場合がほとんどなので、給与が大幅に下がるといいます。シニア人材にとっては役職定年後にモチベーションを保ち、仕事をすることが難しいこともあるでしょう。
・組織で人を育成できない
年齢によって役職が入れ替わるため、前任者が持っていたノウハウがうまく引き継がれないまま、組織運営が進んでしまうことも。また、役職定年でやる気を失った人材が流出してしまうことで、社員の教育がうまく成り立たない懸念もあります。
・日本社会の風土と合わない
高齢化が進んだ日本では、シニアによる活躍が期待されるようになりました。しかし、役職定年制の導入はシニア人材を活用できる機会そのものを減らしてしまうリスクがあります。また、能力で決めるのではなく「年齢」という枠で人材を見ること自体がナンセンスだという意見もあります。
役職定年でモチベーションが下がる理由
役職定年のデメリットの一つにシニア社員のモチベーションが下がるというものがありました。では、なぜモチベーションが下がってしまうのでしょうか。
1.給与の減少
役職定年によって役職手当がなくなった結果、年収が大幅に減少することが考えられます。役職があるときと同じ業務をしているのにも関わらず、報酬が減らされてしまうのでは、モチベーションが下がる大きな要因になりかねません。
2.年下上司との関係性
役職定年者がこれまでと同じ部署で働く場合、元部下が新しい上司になることも考えられます。そのため、元々上司だった社員は居心地の悪さや業務のやりづらさを感じることも少なくありません。このような人間関係の悩みもモチベーションを低下させる要因でしょう。
3.慣れない業務に戸惑う
役職定年者は他部署へと異動することも。そのため、業務の内容が大幅に変化してしまい、全くやったことのない仕事を覚えなくてはならないこともあります。そうして今まで培ってきたノウハウやスキルを活かすことができなくなった結果、仕事へのモチベーションを失うことにつながります。
さらに、これまでは会社から重要な役割を任されていたことで、モチベーションを保っていた社員も、役職から外されてしまうことによって「自分は会社から必要とされていない」という考えに至ってしまうケースも少なくないのです。
年齢だけでキャリアを図れるものではない時代

役職定年によって役職を解かれた社員たちは、様々なキャリアを形成します。多くの方はそのまま会社に残りこれまで通り仕事をしますが、人によっては中小企業に転職したり、自営業やフリーランスに転身したりする人も。
また、日本における役職定年制度の導入件数は、徐々に減少傾向になりつつあります。その背景には「年齢のみ」で社員を登用すること自体が、社会の風潮に合わなくなってきたことにあります。年齢を一律な基準として社員の能力を判断することは、組織の可能性を潰してしまいかねないという議論が起こっているのです。
優秀なシニア社員にはノウハウやスキルの蓄積もあることから、周りの評価なども含めて人材登用を総合的に行っていくべきだという意見が多く聞かれるようになりました。そして、少子高齢化の影響下ではシニア層の活用なくして順当な企業運営を行えなくなってきている企業も増えています。今後、企業はコストと人材登用との狭間で真剣に会社運営について考えていかねばなりません。
まとめ
役職定年は人件費を抑えながら優秀なシニア社員を活用することを目的に始まりました。しかし、近年ではそんな社員たちのモチベーション低下や離職が問題になっています。企業運営と雇用のバランスはいつの時代も課題となりますが、これからも企業にとって役職定年は議論に上がる優先事項の高い問題だと言えるでしょう。