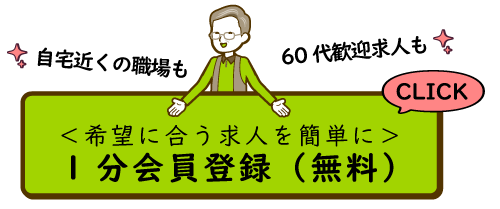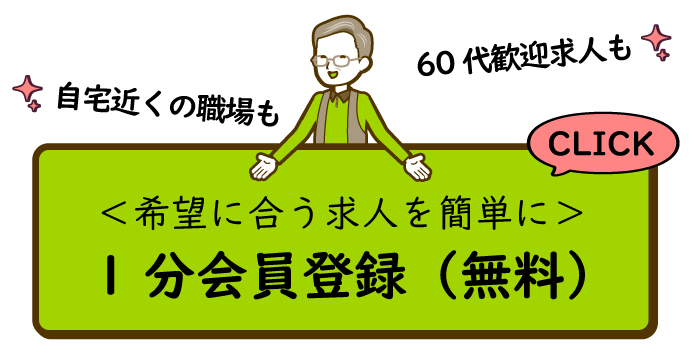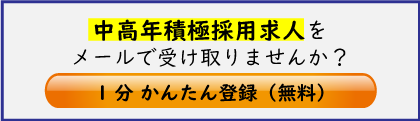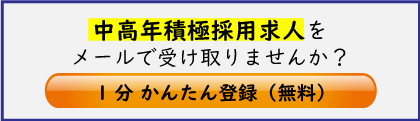定年後の趣味に、人に教えるという選択肢を
- ちょっと得する知識
- 公開日:2021年11月17日

仕事を懸命にやってきてふと気づいてみれば、定年後のセカンドライフがもうすぐそこに……。これまで働いていた時間をいきなり自由に使えるといっても、実際にはどのように過ごせばいいのか、悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。そこで今回は定年後に「人に教える」という時間の使い方があることをお伝えしていきたいと思います。
この記事の目次
定年後の時間の向き合い方とは?
人生100年時代が現実のものとなった、昨今。
私たちは毎日多くの時間を学校や会社で過ごしてきました。
そして、この生活は仕事をリタイアするまでおよそ60年近く続きます。
日常のほとんどの時間を仕事のために使わざるを得ない状況では、ゆっくり自分のために使える時間も少なかったのにも関わらず、定年後は時間が余るほどできてしまうのです。
仕事を生きがいにしていた人にとっては、仕事のない生活がストレスになってしまうことにもなりかねません。
地域の行事に参加したり、地域福祉に取り組んだりなど、ご自身で新しい生きがいを見つけられる人はいいのですが、仕事がなくなったことによって人間関係が希薄になってしまう人も少なくないのが実情です。
それまでは仕事がストレスだと感じていても、意外にそれが生きがいになっていたということも珍しいことではないのです。
また、働かなくなったことで身体の衰えを感じることも多くなります。それがきっかけで病気になってしまい、病気になってしまったことで介護が必要になることも......。
そうならないためにも、定年後の時間を充実したものにするためには、生活パターンが大きく変化することをきちんと知った上で、セカンドライフの過ごし方を準備しておく必要があるのです。
定年後は、どのような過ごし方があるのか?
定年後に趣味がない場合は、誰かと会う機会が減ってしまい、行動範囲が狭くなりがちで体力もそれに伴い落ちてしまうという悪循環が起こりがちです。
【ソニー生命保険株式会社「シニアの生活意識調査2020」シニアの楽しみ】によれば、全国のシニア(50歳~79歳)の男女を対象に現在の楽しみを聞いたところ、「旅行」(43.4%)が最も高く、次いで、「テレビ/ドラマ」(34.6%)、「読書」(29.2%)、「グルメ」(28.7%)、「健康」(26.6%)となったといいます。
これを見れば、アンケートを行った人の約半数が旅行を楽しみにしていることがわかります。しかし、新型コロナウイルス感染症の蔓延からもわかるように、旅行に出かけられないという事態が起こらないとも限りません。
そんなとき、楽しみにしていることが「旅行」だとしたらどうでしょうか。家に閉じこもり、旅行に行けないことへのフラストレーションを抱えてしまうことにもなりかねません。
どのような状況においても、楽しめるものや打ち込める何かがセカンドライフの選択肢にあればいいとは思いませんか?

現代だからこそ「人に教える」という選択肢を!
一人でいると過ぎていく時間も退屈に感じてしまいますが、ご友人がいたらどうでしょう。
カフェでお茶をしながら話しているだけでも時間は過ぎていくのを早いと感じた経験はありませんか?
「でも......周りにそんな気の置けない友人なんていないのよね」と、友人たちのライフスタイルと自身の生活リズムが異なるために、気軽にお茶に誘えるご友人がいない方も多いと言います。
しかも、学生時代は難しくなかった友人作りも、ひとたび大人になると何だか面倒で大変な気がしますよね。
そこで、老後の有り余った時間を使ってSNSやデジタルメディアなどを活用してみてはいかがでしょうか。
オンライン上では気兼ねなく、好きな時に誰かとコミュニケーションを取ることができます。
デジタルという言葉が付くと、ついつい若者のものと思われがちですが、最近では社会人の学びを主軸としたオンライン教育プラット
フォームの開設や、日本語を学びたい外国人のためにシニアを対象にした日本語でのおしゃべりを楽しんでもらおうというアプリなども登場しています。
「人に教える」ということは知識や知見を持った人でなくてはなりません。
その観点でいえば、幅広く様々な経験をしてきたシニアの方々は「教える人」にはうってつけの存在です。
趣味にしていた釣りをYouTubeのチャンネルにしたり、料理が得意な方はオンラインの料理教室などを開いたりすることもできます。
自分の得意や好きなことを教えることで誰かの役に立つのだとしたらなんだかワクワクしませんか。
他者の役に立っているという「貢献感」は幸福を感じ、生きる力になるというデータもあるほどです。
ただでさえ孤独を感じてしまいやすい老後なのにも関わらず、現在はコロナ禍で外にも気軽に出られなくなりました。
周りとのコミュニケーションを取る上でもこういったソーシャルメディアを活用するのも一つの手ではないでしょうか。
また、せっかく人に教えるのであれば、老後になる前に資格や検定などに挑戦して何かのプロになっておけば、すぐに「先生」として活躍することができます。
まとめ
定年退職後の生活は誰しも元気で活動的なものにしたいですよね。
そのような生活を送るためには、セカンドライフの過ごし方を日頃から考えておくのが大切です。
定年後に時間を持て余さないためにも、「人に教える」という誰かの役に立つ趣味を持つことは、充実したセカンドライフを送るヒントなのかもしれません。
関連記事