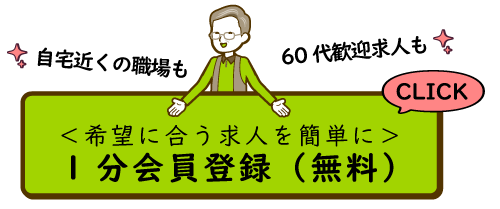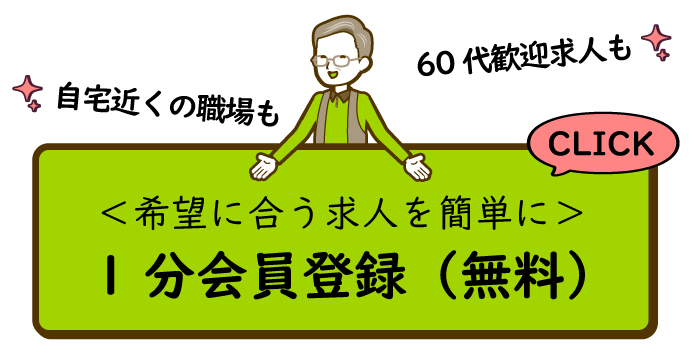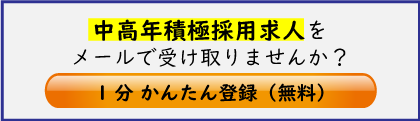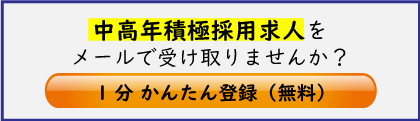学んだことは一生の財産。学びを通じて副収入を得よう!
- ちょっと得する知識
- 公開日:2021年11月16日

日本の平均寿命は男女ともに80歳を超え、世界から見ても超長寿国だといえます。昔、中国唐時代の詩人である杜甫は70歳まで生きることを「古来稀なり」と「70歳まで長生きする者は昔からきわめて稀である」と表現していますが、日本では現在およそ5人に1人が70歳以上です。昔から偉人達が財産を持ったとき、不老不死になるためにはどうしたらいいのか、そこに頭を悩ませてきたといいますから、昔の人が現代人の寿命を知ったなら驚き、羨ましいと感じるのではないでしょうか。昔と比べて長くなった私たちの人生。そんな延びた時間を私たちはどう生きていけばいいのでしょうか。
この記事の目次
老後の資金が足りません!とならないためには
私たちが先人たちより長く生きられるようになった分、考えなくてはいけない問題はそう、お金のことです。
諸外国を見てみると、税金が高い分、福祉が充実している国もあります。
しかし、今の日本に限ってみてみれば、税金や年金をきちんと払ってきているからと言って老後の生活は何も不自由ないかと言えばそうではありません。
『老後の資金がありません』(著:垣谷 美雨、中央公論新社)という本が今年の秋に映画化されます。
小説の中で主人公は娘の結婚、親の介護......とあらゆる予期せぬ事態に遭遇し、気づけば貯金も底をつき......このままでは自分たちの将来の生活資金が足りない! と奔走する話なのですが、読んだとき、「これは他人事ではない」と思いました。
皆さんもご自身の将来と重ねて考えることができると思いますので、ぜひ一度本を手に取ったり、映画館に足を運んでみたりするのも具体的な老後のイメージが湧きやすくなる点で、おすすめです。
また、老後資金のとして必要な額が3,000万円や2,000万円だとあらゆるところで声高に叫ばれているのを耳にしたことはありませんか?
「この数字は一体どこから出ているの?」と思われた方も少なくないと思います。
実は、夫婦2人で老後生活を送る上で必要と考えられている最低限度の生活を送れる平均額は月額でおよそ23万円というデータがあるのです。
さらに、国民年金の平均受給月額は55,000円で、厚生年金の平均受給月額は144,000円。
この数字をみて、「あれ?」と思われた方がいると思います。その通りです。
入ってくるお金に対して、出ていく金額が多いわけですから、老後は貯えがなくては生きていけないのです。
しかもこれは贅沢をせずに暮らした場合です。
趣味や楽しみなどの費用は含まれていません。ですから、足りない金額を寿命までと考えたときに算出されたのが2,000万だとも3,000万だとも言われているのです。
また、みなさんは"下流老人"という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
これは、NPO法人などで活動する藤田孝典氏が『下流老人 一億層老後崩壊の衝撃』の著書の中で「生活保護基準相当で暮らす高齢者およびその恐れがある高齢者」と定義したものです。
現在の高齢者世帯のほぼ半数は所得に占める年金などの割合が80%以上になっているのだとか。
つまりこの先、年金の支給額が減額されたり、受給年齢がさらに引き上げられたりしたら今50代以下の人たちの大半は下流老人になりかねないのだというのです。
これまでに見てきたように、毎月の赤字を埋めるには貯蓄を切り崩すか、高齢になっても働かざるを得なくなってきているのです。
※データ元:
・生命保険文化センター「生活保障に関する調査」(令和元年度)
・総務省 家計調査年報(家計収支編)2018年(平成30年)
・『稼ぎ続ける力 「定年消滅」時代の新しい仕事論』大前研一著、小学館
学びは一生ものの財産
そんな将来を見据えた際に、老後の働き方の一つとしておすすめなのが「日本語教師」です。
なぜおすすめなのかと言えば、日本で働く外国人や留学生が増えているにも関わらず、日本語教師の数は足りないからです。
しかも最近では、若い世代だけでは担うことが難しく、定年後のシニア層への需要が高まってきている傾向があります。
求人情報にも、「定年後の短時間勤務OK」「50歳以上歓迎」といった募集案件を簡単に見つけることができます。
国内で日本語教師として働くには、以下の条件のうち1つを満たす必要があります。
・大学で日本語教育を専攻、もしくは副専攻する。
・財団法人日本語教育振興会が実施する「日本語教育能力検定試験」に合格する。
・民間が主催する、日本語教師養成420時間コースを修了する。
定年後に日本語教師を目指す人は、コツコツと将来を見据えて行うことのできる、「日本語教師養成420時間コース」を受けることが多くなっているのだとか。
このコースを受講するのに年齢制限はなく、既定の時間講習を受けるだけでいいのだといいます。かかる費用は、およそ60万円。
420時間と考えると、働きながら学ぶのは難しそうと思われる人もいらっしゃるかもしれませんが、1年(12か月)で割ると35時間、ひと月およそ1時間程度の勉強でいいことになります。
そして、社会人の平日の通勤時間は男性で約1時間30分、女性では約1時間だといいます。
これを考えても通勤時間を利用して勉強するだけで日本語教師の資格が得られるのです。
資格取得に費やしたお金も、日本語教師の国内での時給は約1,500~2,000円、常勤講師になると月収20万円前後が相場なので、かかった費用はすぐに元がとれることがわかるでしょう。
※データ元:総務省統計局『平成28年社会生活基本調査』

まとめ
銀行にお金を預けていても、利益はわずか。
さらに、高齢者への医療費負担の割合も増えてきているのもまた現実です。
老後が不安だと嘆いているなら今すぐ学びを財産に変える努力をしてみてはいかがでしょうか。得られた副収入を使って自分の好きなことを楽しめば、より充実した人生を送る一助になりますよね。
関連記事