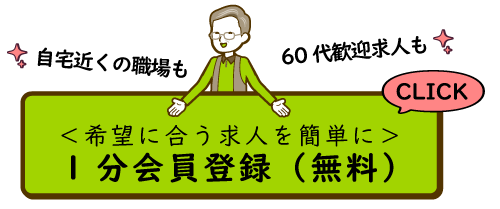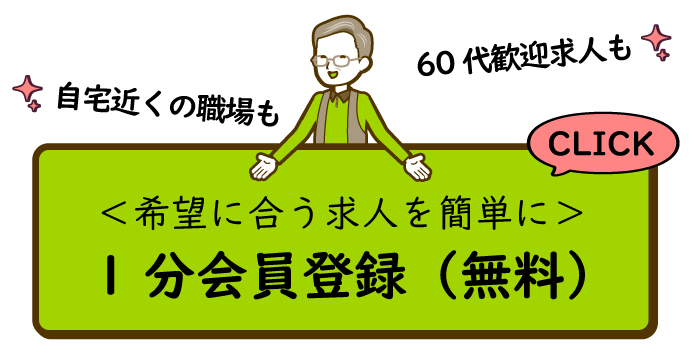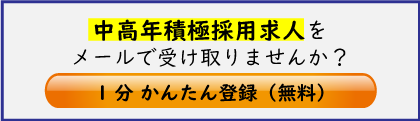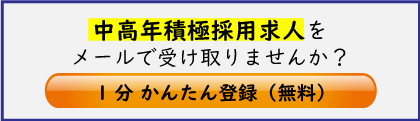これからは自国の言葉を学ぶ時代
- ちょっと得する知識
- 公開日:2021年11月16日

経済協力開発機構(OECD)の世界79カ国・地域の15歳約60万人の生徒を対象に2018年に行った学習到達度調査(PISA)の結果が昨年公開されました。日本は「読解力」が15位となり、前回2015年調査の8位から大きくランキングを下げました。これについて危機感を抱いた人も少なくなかったかもしれません。どうしてこのような結果になってしまったのでしょうか。
この記事の目次
日本語は世界的にも難しい言語⁉
日本語について、このようなカテゴリー分けがあります。
アメリカ国務省が公表しているデータによれば、他国との交渉のためにアメリカ人外国官が「ビジネスレベル」の語学力を習得するための難易度を言語ごとに全4レベルに分けているのですが、その中で日本語はアラビア語、韓国語、中国語などと並んで最も難しいとされるカテゴリー4に分類されています。
※データ元:アメリカ国務省HP
日本語はなぜ難しいのでしょうか。
まず日本語には、ひらがな、カタカナ、漢字の3つの表記があります。
そして、発音には無声音や有声音、特殊拍と呼ばれる長音(おばさんとおばあさんなどの伸ばす音の違い)や促音など発音するのにも細かい点が存在します。
また、同音異義語や、きらきら、さらさらなどといった自然界の音・声、物事の状態や動きなどを音で表す、オノマトペなども多いのが特徴です。
さらに、文法的にも主語の省略が多くされたり、敬語や慣用句があったりと、日本語を読解するには多く日本語を使ってきた日本人でも難しいのです。

国語が乱れている?
文化庁が実施している「国語に関する世論調査」によりますと、普段の生活の中で今の国語は乱れていると思うかを尋ねたところ、「非常に乱れていると思う」を選択した人の割合が 10.5%、「ある程度乱れていると思う」が 55.6%で、調査した半数以上の人が日本語は乱れていると思っていることがわかったのだそうです。
また、どのような点で乱れていると思うかを尋ねたところ、「敬語の使い方」や「若者言葉」、「新語・流行語の多用」などが挙がったのだとか。
乱れている原因の一つになっている「若者言葉」とは、10代~20代前半の青少年が日常的に用いる俗語やスラングなどで、それ以外の世代ではあまり用いない言葉のことだと定義されています。
親世代と子ども世代では同じ日本語を使っているというのに意味が通じないということも少なくないのです。
このような言葉の乱れの原因については戦後、国語の教育時間が大幅に減ったことも要因だと考えられています。およそ50年前と比べて小学校では200時間、中学校では100時間も国語の授業時間は減っているといいます。
なぜこの授業時間の減少が問題かと言えば、冒頭で述べた読解力の問題にも挙げられるように、正しい言葉の理解は正しい物事の解釈にも繋がるからです。
学ぶ時間が減ることは、日本語を学ぶ機会が単純に減っているということなのです。
最近では、日本に就労している外国人の方がしっかりと日本語を勉強しているため、日本人よりも正しい日本語を使えるなんてことも少なくないのだとか。
※データ元:
・文化庁 令和元年度「国語に関する世論調査」の結果の概要
・『日本語のできない日本人』著:鈴木義里、中央公論新社
学ぶことは歳を取るごとに億劫になる!?
何も読解力は若者だけの問題ではありません。
40歳以上の日本の働き手の大半は自ら学習を行うこともしなければ、読書すらしていないというデータがあります。
会社の中で中堅ともなれば人材育成の対象からも外れ、研修などもなくなってしまいます。会社にしがみついて定年を迎えることができれば御の字ですが、今は会社に所属していてもいつどうなるかなんて誰にもわからない時代がきています。
日本で就労する外国人も右肩上がりになっていますから、彼らが言葉の壁さえクリアできれば、優秀な人材としてシニア層が据え替えられてしまうなんてことも起きかねません。
また、日本の定年延長はネガティブに捉えられることが多いのに比べ、欧米ではシニア雇用が積極的になされています。それは、根本的に考え方が違うのだからだそうです。
欧米ではポジションごとの専門性が働く理由になるそうで、日本のように何歳だから働かなくてはという考え方ではないのだといいます。歳に縛られることなく、専門的なスキルを活かして働いていくというスタイルの違いがそこにはあるのです。
日本でもご存じのように、終身雇用制度は守られなくなってきています。
「スキルも特にないし、今更何を学べばいいのかわからない......」と、これからの会社員生活を送る上で不安になる方は、日本語を学ぶのはいかがでしょうか。
社会人だから...、そんな時間がないから...という方でも日本語なら身近にあるので、自分のペースで学ぶことができます。
また、日本語教育能力検定試験などの資格を取得し、日本語教師になることは副業や退職後の雇用にも繋がりますので、とてもメリットが多いのです。
まとめ
言語はこれまで培ってきた国独自の文化だともいえます。
インターネットがあれば大丈夫、日本語なんて使えるから心配ない、と安易に考えるのではなく、国際競争から遅れを取らないためにも自国の言葉を学ぶことはとても大切になってきています。
言語を正しく理解することによって、読解力を上げることはもちろん、生き方の幅を広げることもできるのです。
関連記事