国民健康保険料が値上げ!毎月かかる保険料や負担を軽減する方法
- ちょっと得する知識
- 公開日:2024年5月22日

2024年、国民健康保険料の上限額が引き上げられます。今回は、国民健康保険料の概要や計算方法、なぜ上限額が引き上げとなったのか、軽減措置について解説します。自身の生活に影響がないか事前に把握しておきましょう。
この記事の目次
国民健康保険とは
そもそも国民健康保険とはどういった制度なのか、加入対象者や概要、計算方法などについてご紹介します。計算方法は自治体によって異なるため、あくまで参考としてご確認ください。
国民健康保険の概要
国民健康保険とは、被保険者保険制度や後期高齢者医療制度に加入していない、すべての人が加入する医療保険制度です。
日本は「国民皆保険制度」を導入しているため、無職・フリーランス・会社員と働いている形に関係なく加入が必要となっています。都道府県及び市町村が保険者となる市町村国保と、業種ごとに組織される国民健康保険組合から構成されています。
国民健康保険に加入をすると、病院を受診した際に自己負担額が2〜3割になるほか、高額な療育費がかかった時に一定額以上が免除となります。また、出産や葬儀の際には一時金が給付されるなど、さまざまな恩恵を受けることができます。
国民健康保険の計算方法
保険料の内訳は3つあり、以下のように分けられます。
• 基礎分保険料(医療費):医療費給付にあてる
• 後期高齢者支援金分保険料:75歳以上の後期高齢者の支援金等にあてる
• 介護保険料:40歳以上65歳未満の人の、介護の給付にあてる
また、上記の各保険料は、以下の方法で計算を行います。
• 均等割:世帯あたりの国民健康保険加入者の人数に応じて計算される金額
• 平等割:全世帯が平等に負担する金額
• 所得割:前年の所得に応じて負担する金額
各市町村によって保険料の計算方法が変わるため、自身の保険料が気になる場合は各市町村のホームページを確認してみましょう。シミュレーターが用意されている場合があります。そのほか、市役所などで必要な書類を持って行くと、具体的な保険料を出してもらえることも。
なぜ国民健康保険を値上げするのか
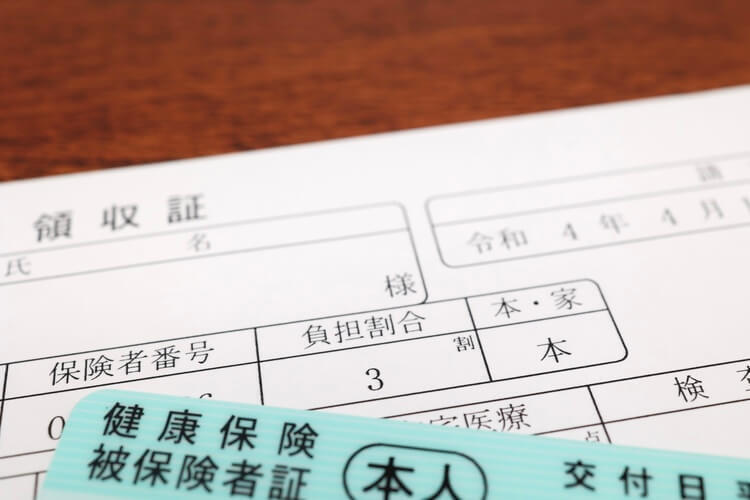
なぜ、国民健康保険料が値上がりしたのか、その理由は気になる点です。
高齢者の医療費給付額を増やすため
2024年度における国民健康保険料の上限額引き上げは、保険料収入の増加による高齢者医療給付費用の確保が目的です。現在、日本では高齢者の人口が増加しており、2022年時点では65歳以上の高齢者人口は全体の29.1%。高齢化に伴い医療費の給付が増えており、現状の保険料では医療給付が賄えなくなっているのです。
国民健康保険料の引き上げルールを考慮
国民健康保険料の上限額を引き上げる際には、以下の点が考慮されています。
• 上限額を超過する世帯の割合が1.5%に近づくように段階的に引き上げる
• 基礎分・後期高齢者支援金分・介護分の上限額を超過する世帯の割合が前年より増加している、あるいはそれぞれにばらつきが見られるかを基準として引き上げ幅を設定する
2024年度に上限額の引き上げを行わなかった場合、限度額相当世帯は1.42%です。しかし、後期高齢者支援金分の限度額相当世帯が2.25%となり、2023年の1.97%から大幅に増加します。そのため、今回上限額を2万円引き上げ、104万円から106万円へと変更になりました。上限額が引き上げとなるため、加入者の全員の保険料が上がるわけではありません。
低中所得者の保険料負担を考慮
所得が伸びにくい状況のなか医療給付が増加しているため、場合によっては保険料率が上がる可能性もありました。しかし、保険料の上限ではなく保険料率を引き上げた場合、高所得者の負担は変わらずに低中所得者の負担のみが増加します。
反対に今回の上限額の増加では、高所得者の負担は増えるものの、低中所得者の保険料には考慮した保険料設定が可能です。厚生労働省の資料でも、中間所得層の被保険者の負担に配慮、引き上げにより中間所得層の伸び率を抑えられると説明しています。保険料の負担は「負担能力に応じて公平にする」が、基本的な考え方です。
被保険者の所得が増えない
国民健康保険の加入者は、会社の健康保険に加入していない人や生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度の対象者・学生・自営業者などです。つまり、国民健康保険に加入している人は、会社の健康保険に加入している人よりも所得にバラつきがあります。
また、会社員の人が国民健康保険に加入する場合は退職後となり、所得は現役時代よりも低くなります。平均所得が低くなるため、中間所得層からの保険料確保が難しくなり、結果として上限額の引き上げとなりました。
値上げの影響を受ける年収はいくら?
国民健康保険料の値上げは「上限額の値上げ」のため、加入者全員の保険料が上がるわけではありません。年収がいくらの場合に影響があるのかを確認しておきましょう。
各区分の上限額は以下のように変化します。2023年度では保険料の上限額は104万円、基礎賦課分は65万円・後期高齢者支援金等賦課分22万円・介護納付金賦課分17万円です。2024年度には後期高齢者支援金等賦課分が24万円となり、合計が106万円となります。
具体的に影響を受ける年収について、厚生労働省では以下のような試算を行っています。
• 2023年度:給与収入 約1,140万円(給与所得・年金所得960万円)
• 2024年度:給与収入 約1,160万円(給与所得・年金所得980万円)
ただし、扶養家族のいない単身世帯の試算のため、扶養家族がいる場合は変動します。上記のように、年収が1,000万円前後の世帯は、国民健康保険料の上限増額による影響を受ける可能性が高いです。税額や児童手当の対象外などのほか、今回の国民健康保険料など、年収1,000万円は大きな変化のあるボーダーラインとなります。
国民健康保険の負担を減らす方法はあるのか

国民健康保険の負担が増えると手取りが減るため、できれば支払額を少なくしたいものです。負担額を減らす方法はあるのか、軽減措置についてなどをご紹介します。
計算方法によって軽減措置がある
国民健康保険料の額を算出する際に、法令で決められている所得基準を下回る場合、減額する制度があります。各減額の割合と、対象者の要件については以下の通りです。 ※ (給与または年金所得者の人数-1)×10万円
| 減額割合 | 対象者の要件(世帯主と被保険者の総所得) |
|---|---|
| 7割 | 43万円+※ 以下 |
| 5割 | 43万円+(被保険者数×29.5万円)+※ 以下 |
| 2割 | 43万円+(被保険者数×54.5万円)+※ 以下 |
例えば、東京都中央区では、各割合の保険料は以下のようになっています。
| 軽減割合 | 7割 | 5割 | 2割 |
|---|---|---|---|
| 基礎分保険料 | 45,000円→13,500円 | 45,000円→22,500円 | 45,000円→36,000円 |
| 後期高齢者支援金分保険料 | 15,100円→4,530円 | 15,100円→7,550円 | 15,100円→12,080円 |
| 介護保険料 | 16,200円→4,860円 | 16,200円→8,100円 | 16,200円→12,960円 |
| 計 | 22,890円 | 38,150円 | 61,040円 |
引用元:中央区「国民健康保険料の軽減・減免」
未就学児の均等割額軽減措置
2022年4月より、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児の均等割保険料の軽減が導入されています。制限は設けられておらず、広く子供がいる世帯に一律で導入しています。均等割保険料の軽減割合は5割です。所得額に関係なく、全員が一定の負担をしている点から、全額免除にはなりません。
すでに均等割軽減が適応されている場合でも、さらに子どもの保険料にかかる軽減措置も適用可能です。7割の軽減措置からも半額になるため、所得が低い世帯の子どもは最大で8.5割の軽減となります。
例えば、東京都中央区ではどちらの軽減措置も適応された場合、以下のような保険料となります。
| 軽減割合 | 7割 | 5割 | 2割 |
|---|---|---|---|
| 基礎分保険料 | 13,500円→6,750円 | 22,500円→11,250円 | 35,000円→18,000円 |
| 後期高齢者支援金分保険料 | 4,350円→2,265円 | 7,550円→3,775円 | 12,080円→6,040円 |
| 計 | 9,015円 | 15,025円 | 24,040円 |
あくまで上記は中央区の例のため、詳細は住んでいる市町村に確認しましょう。
社会保険料控除を活用する
社会保険料控除とは、毎年1月1日〜12月31日までに納付された社会保険料に対して受けられる所得控除をいいます。社会保険の種類は年金保険・健康保険・介護保険・雇用保険・労災保険です。
自身の支払った保険料のほか、生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を支払った場合も含まれます。例えば配偶者や20歳を超えた子どもの国民年金なども、本人が払ったことが明確であれば、年末調整時に控除ができます。控除の対象となる社会保険料は、以下の通りです。
1. 健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
2. 国民健康保険の保険料または国民健康保険税
3. 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
4. 介護保険法の規定による介護保険料
5. 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
6. 国民年金基金の加入員として負担する掛金
7. 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
8. 存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金
9. 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金または納金等
10. 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
11. 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
12. 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
13. 健康保険法附則または船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
14. 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもののうち一定額
15. ※日本の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法ならびに類似の条件および制限に従って取り扱うこととされているものに限る
引用元:国税庁「No.1130 社会保険料控除」
全国健康保険協会では保険料率が改定される
国民健康保険のほか、全国健康保険協会でも2024年度に保険料率の改定が決定しています。全国健康保険協会は、主に中小企業で働く従業員やその家族が加入する公的な健康保険です。2024年度の保険料について、以下の24の都道府県で値上げが予定されています。
• 福島県
• 群馬県
• 新潟県
• 富山県
• 石川県
• 福井県
• 山梨県
• 長野県
• 岐阜県
• 静岡県
• 愛知県
• 三重県
• 滋賀県
• 京都府
• 大阪府
• 兵庫県
• 奈良県
• 和歌山県
• 広島県
• 山口県
• 香川県
• 愛媛県
• 大分県
• 宮崎県
上記以外の22の都道府県では引き下げが予定されており、唯一神奈川県のみ変更がありません。
まとめ
2024年度から国民健康保険料が引き上げとなりました。上限額の引き上げのため、加入者全員の保険料が上がるわけではありません。しかし、年収1,000万円前後の方は上限額になる可能性があるため、今回の変更の影響を受ける場合があるでしょう。
国民健康保険は、退職後の多くの人が加入する可能性のある保険です。少しでも不安なく利用できるよう、なぜ引き上げがされたのか、軽減措置はないのかなど改めて知っておきましょう。

























