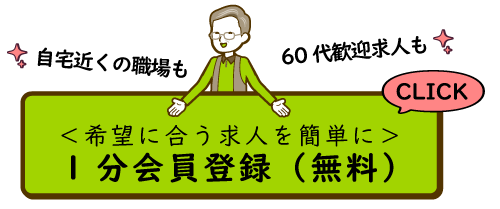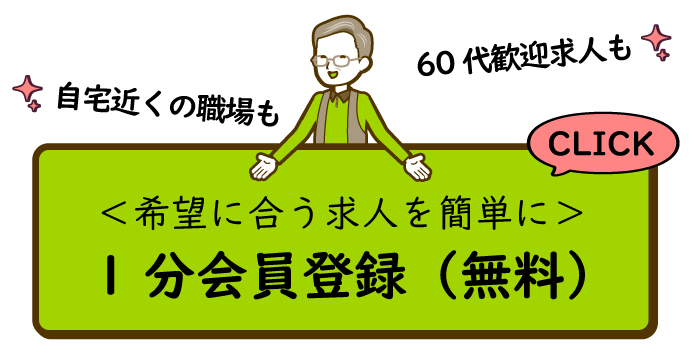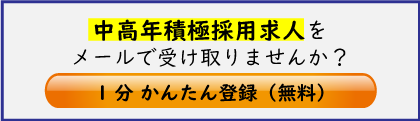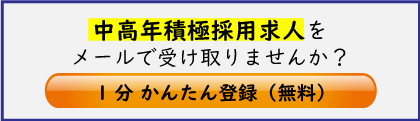老後は日本語のプロになって、新しい働き方を実現する
- ちょっと得する知識
- 公開日:2021年11月17日

みなさんは定年後、どのように過ごしたいと考えていますか。現役時代はせかせかした毎日を送ってきたからこそ、「ゆっくり、のんびり過ごしたい!」と考えられている方も多くいらっしゃると思います。しかし、現実は意外と違うのです! 驚かれるかもしれませんが、再雇用などで働いている人や、夢中になれるライフワークを持つ人の方が何もせずに家で過ごしている人よりも健康で溌剌としているのだといいます。体を休めている方が健康的なはずなのに、どうしてそんなことが起きてしまうのでしょうか。
この記事の目次
時間は有り余るほどあるけれども・・・
現役時代と定年後をわかりやすく、数字で表してみたいと思います。
22歳から65歳までの43年間働いていた時間を単純に計算すると、※8万6,000時間。
(※8時間×250日×43年=8万6,000時間として算出)
定年後、65歳から85歳まで20年間の自由に使える時間は※10万2,200時間。
(※14時間×365日×20年=10万2,200時間として算出)
それぞれのライフスタイルや働き方にもよりますが、定年後の時間は働いていた時間よりも長いことがわかります。
さらに、人生100年時代と言われる現代ですから、定年後の時間は長生きをすればするほど増えていきます。
この定年後こそ、新たな自分の人生のステージが始まるといっても過言ではありません。
ある英国の金融機関の調査では定年退職後や引退後に暇だと感じ始めるようになるのは10か月というデータもあり、ヒトは何もせずにボーっとしていられない生き物だということもわかってきたのだそうです。
具体的に何をすればいいかわからない人が多数!
【ファイナンシャルアカデミーによる「定年後のキャリア」に関する意識調査】によれば、調査対象の全体の約7割の人が「給料が下がっても働きたい」と回答したといいます。
その理由には「老後資金の確保のため」「生きがいだから」「社会とのつながりを持ちたい」などが挙がったといいます。
ただ、定年後のキャリア対策については「十分できている」と回答した人は全体のわずか1%という結果になったのだとか。
定年後も働きたいと思っている人が多数派であるにも関わらず、そのための準備をできている人はあまりいないことがわかります。
そして、定年後のキャリア対策について「十分できている」「まあできている」と回答した人たちでも現在持っているスキルを上げることや情報収集は行っていても、「資格取得」や「学校等で専門的な知識を学ぶ」「習い事をする」といった具体的な行動に移している人は少ないのだそうです。

現役時代から学びを視野に入れる「リカレント教育」
日本では、本格的に「人生100年時代」が始まろうとしています。
男女問わず若者から高齢者まで国民全員が社会で活躍することが求められているのです。
定年退職後の再雇用や再就職で活躍するためにも、絶えず新しい知識を身に付けることが大切です。そのための手段として、リカレント教育が注目されています。
これは社会人のための学びとも言われます。「何歳から何歳まで」といった年齢制限もないため、定年退職者がリカレント教育を受けることも多いのだとか。
内閣官房の人生100年時代構想推進室は、2018年に『リカレント教育参考資料』を発表しました。
リカレント教育とは、学校教育から離れて社会人になった後でも、仕事で求められる能力の向上や自己研鑽を目的に励む、学びのことを指します。
社会人になってから専門的な知識やスキルを学ぶため、「社会人の学び直し」と呼ばれることもあります。
この資料によると、高等教育機関への25歳以上の入学者の割合は、OECD参加国の平均が16.6%なのに対し、日本は2.5%とその割合が著しく低いことが分かっています。
また、「仕事が忙しくて学び直しの余裕がない」「費用がかかりすぎる」といった理由から、学び直しに問題があると感じている社会人が8割近くもいることもわかりました。
このように日本では、リカレント教育はまだあまり普及していませんが、「人生100年時代」を見据え、キャリア相談を設けるなど、現在国主導でリカレント教育を進める取り組みがなされています。
あまり知られていない、日本語を学ぶメリット!
スーパーやコンビニなどに行くとほとんどの店員さんが外国の人だった、なんて経験はありませんか?
たとえばネパールやブータンなどでは、外国人観光客に接する仕事に就ければ安定的な収入を得ることができるのだそうです。
また、ベトナムやタイでは日本企業に採用されても、日本語ができるとできないとでは、収入が倍くらい違うといいます。
そういったこともあり、日本で語学を学ぶ外国人はとても多いのです。
しかしながら日本では、外国人日本語留学生は増加しているのにも関わらず、日本語教師は圧倒的に不足しているという実情があります。
そのため、日本語教師の求人には「50歳以上、初心者歓迎」、「定年後の方OK」といった求人が多く見受けられます。
日本語を使いこなすプロになるためにはきちんとした資格取得が必要になりますが、その資格取得には時間もかかるため、日本語学校は常に講師不足だというのです。
しかし、この資格は一度職を得てしまえば、70歳を過ぎても働けるので、定年退職後に日本語教師になる人もいるのだとか。
さらに、海外では日本よりもさらに日本語教師が不足しており、インターネットの求人サイトでは65歳初心者でも募集可能な案件などもみられます。
ですから、セカンドライフのイメージが具体的にできていない方は、まずは日本語のプロになっておくだけで将来の働き口が大きく広がるのです。
※データ元:【日本語講師養成講座】学校法人三幸学園グループ
まとめ
老後という時間は私たちが考えているよりとても長いです。
ただし、きちんと自分でその老後をイメージできなければ、せっかくの限りある時間を無駄に過ごしてしまいかねません。
「うちのじいちゃんかっこいいんだぜッ」「私のおばあちゃんいつまでも元気!」と、孫たちから称賛されるような老後を送るためにも、現役時代のうちから資格取得を考えておくのは一つの手でしょう。