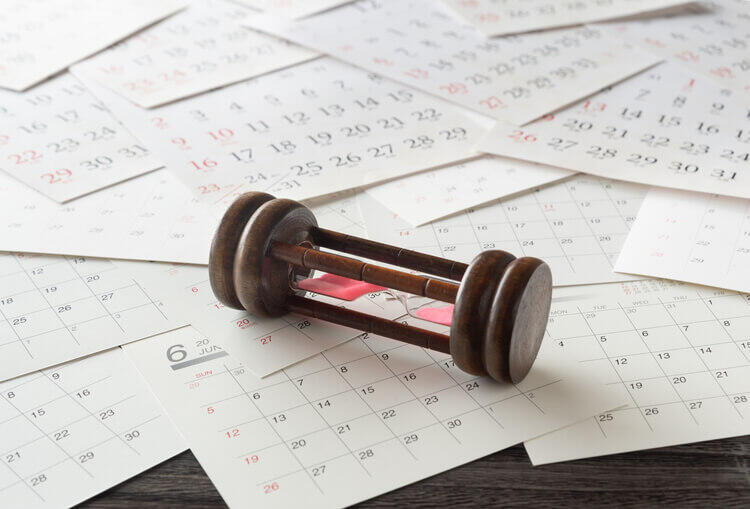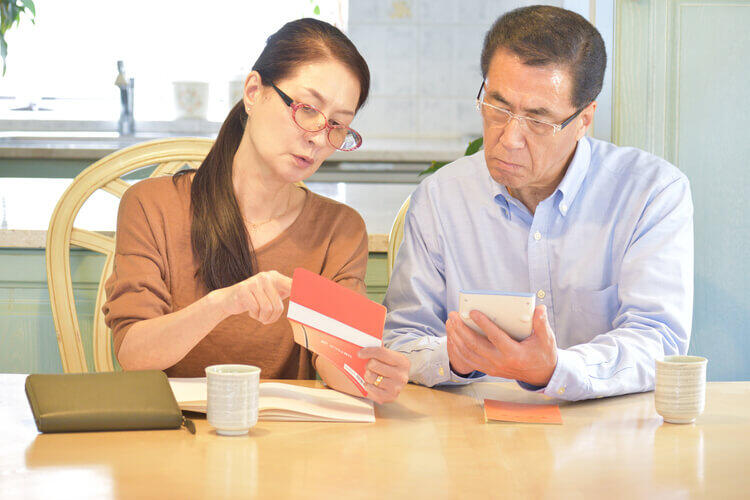遺族年金とは?対象者や受給額、2025年の制度改正を解説!
- ライフプラン・人生設計
- 公開日:2025年5月22日

今回は遺族年金の概要から受け取れる人、受給額などをご紹介します。また、2025年に行われる制度改正や受け取れない人の対処法なども解説しています。自身が遺族年金の対象となっているか、どのくらいの額をもらえるか気になる人は、ぜひ最後までご確認ください。
この記事の目次
遺族年金は2種類ある
遺族年金は国民年金または厚生年金保険の被保険者、または被保険者だった人が亡くなった時に、その人によって生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。それぞれの内容については、以下でご紹介します。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は被保険者だった人が亡くなった場合に、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取れる年金です。国民年金は満20〜60歳の人がすべて加入するため、遺族年金もすべての人に関係する年金となります。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は亡くなった人が会社員や公務員だった場合、その配偶者や子供に支給される年金です。厚生年金に加入している人が対象となるため、自営業の人は対象にはなりません。遺族基礎年金とは受け取れる条件が異なります。
遺族年金を受け取れる人

遺族年金を受け取るためには、生計を同じくしていること、年収850万円未満であることが条件です。生計を同じくしているかどうかの判断として、亡くなった人と同居しているかが見られます。また、別居をしていても亡くなった人から仕送りを受けていた場合などは、生計を同じくしていると認められることがあります。
そのほか、遺族の前年の収入が850万円未満、または所得が665.5万円未満が条件です。上記以外に、遺族基礎年金と遺族厚生年金では、それぞれ受給できる条件が異なります。自身がどちらの条件に該当しているのか、違いについて確認しましょう。
遺族基礎年金を受け取れる人
遺族基礎年金を受け取れるのは、国民年金に加入している「子のある配偶者」または「子」のみです。つまり、子のいない配偶者は遺族基礎年金を受け取れません。子は18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満の障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人を指します。ただし、子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間は、子には遺族年金は支給されません。
そのほかに、以下のような条件を満たしている必要があります。
1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所を有していた人が死亡したとき
3. 老齢基礎年金の受給権者であった人が死亡したとき
4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき
参照元:日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
1と2の要件については、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。また、3と4の要件については、保険料納付済期間や保険料免除期間および合算対象期間の合計が、25年以上である人に限られます。
ただし、死亡日が令和8年3月末までで死亡日において65歳未満である、死亡日の前日時点で死亡した月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合は、納付要件を満たすとされます。
遺族厚生年金を受け取れる人
遺族厚生年金は、亡くなった人が会社員や公務員だった場合に受け取れる年金です。死亡した人の遺族のうち最も優先順位の高い人が受け取れるため、子のある配偶者や子はもちろん、子のない配偶者、父母や孫、祖父母でも受け取り可能です。
ただし、子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。また、子のない夫は55歳以上である場合に受給ができますが、受給開始は60歳からとなります。
遺族厚生年金の受給要件は、以下の通りです。
1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3. 1級・2級の障害厚生年金を受け取っている人が死亡したとき
4. 老齢厚生年金の受給権者であった人が死亡したとき
5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡したとき
参照元:日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
もし、優先順位の高い人が遺族厚生年金を受け取った場合、それ以下の人は年金を受け取れません。
老齢年金を受け取っている人はどうなる?
65歳以上で、遺族厚生年金と自身の老齢厚生年金の受給権の両方を持っている場合、平成19年3月31日までは原則どちらかを選択する必要がありました。
しかし、年金制度改正によって老齢厚生年金は全額支給、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止になります。もし、遺族厚生年金が老齢年金よりも多かった場合は、差額分が遺族厚生年金として支給されます。
遺族年金の受給額
遺族年金の受給額は、年金の種類や生年月日、家族構成などによって異なります。それぞれの受給額について解説します。
遺族基礎年金の受給額
遺族基礎年金は、子のある配偶者が受け取る場合と子が受け取る場合で金額が異なります。
子のある配偶者が受け取る場合
• 昭和31年4月2日以後に生まれた人:816,000円+子の加算額
• 昭和31年4月1日以前に生まれた人:813,700円+子の加算額
子が受け取る場合は、816,000円+2人目以降の子の加算額を割った額が、1人あたりの金額となります。1人目・2人目の子の加算額は各234,800円、3人目以降の子の加算額は各78,300円です。
遺族厚生年金の受給額
遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額です。報酬比例部分の計算については、以下の通りです。
平成15年3月以前の加入期間の場合
• 平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数
平成15年4月以降の加入期間の場合
• 平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数
もし、厚生年金保険の被保険者期間が300ヶ月(25年)未満の場合は、300ヶ月とみなして計算します。例えば、40歳未満の子のある妻で厚生年金の加入期間は300ヶ月、平成15年3ヶ月以前の加入期間なしの場合で試算します。
| 平均報酬月額 | 30万円 | 40万円 | 50万円 |
|---|---|---|---|
| 受給額 | 36万9968円 | 49万3290円 | 61万6613円 |
あくまで目安のため、場合によって金額は前後します。
遺族年金は2025年に制度改正が行われる

現在、20代〜50代の死別した子のない配偶者は、主たる生計維持者を夫と捉えられています。夫と死別した妻は、就労と生計の維持が難しいと考えられ、30歳以降は無期給付が行われています。妻と死別した夫は、就労による生計維持が可能であると考えられ、55歳まで受給権が発生しない、といった男女の差が存在しています。
男女差をなくすために、今回の改正では20代から50代の死別した子のない配偶者に対し、男女関係なく遺族厚生年金が一律5年間の有期給付となります。また、夫を亡くした40歳〜65歳までの妻を対象にした、中高齢寡婦加算が廃止となります。
さらに、今回の改正によって改良される点は、以下の通りです。
• 5年間の遺族年金額の増額
• 収入制限の撤廃
• 死亡時分割の導入
死亡時分割は夫が亡くなった場合、亡くなった被保険者の厚生年金を分割して妻の老齢厚生年金に上乗せする制度です。適用されるのは、夫婦の婚姻期間までとなります。さらに、遺族基礎年金の子に対する支給停止規定の見直しも行われます。
参照元:厚生労働省 遺族年金制度等の見直しについて
遺族年金を受け取れない人の対処法
遺族年金の受給条件に該当せず、受け取れない人もいるでしょう。また、遺族年金だけでは経済的に不安を感じる人のために、対処法を5つご紹介します。生命保険や制度を活用して、少しでも経済的な負担を減らしましょう。
①寡婦年金
自営業者と生活を共にしており、子がいない配偶者の場合、遺族基礎年金も遺族厚生年金も受け取れません。しかし、寡婦年金を受け取れる可能性があります。寡婦年金とは死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上ある場合に、支給される年金です。
支給されるのは、夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻が、60歳から65歳になるまでの間です。保険料を納めている期間には国民年金の保険料免除期間を含むため、学生納付特例期間なども該当します。また、婚姻関係には事実上の婚姻関係が含まれます。
支払われる年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。もし、亡くなった夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがある場合や、妻が老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合は支給されません。
➁死亡一時金
死亡一時金は、第1号被保険者と生計を同じくしていた遺族が受け取れるお金です。具体的な条件は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時です。死亡一時金を受け取れるのは、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の中で、優先順位の高い人になります。
国民年金保険料を納付した月数が36月の場合は12万円、最大の420月の場合は32万円が受け取り可能です。もし、付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。死亡一時金と寡婦年金は同時の受給ができないため、どちらか一方のみを選択する必要があります。
もし、両方の受給要件に該当する場合は、どちらが良いか金額などを確認しましょう。また、死亡一時金を受け取る権利には時効があり、死亡日の翌日から2年までに手続きをする必要があります。
➂終身保険
終身保険は保険期間が一生涯続く死亡保険で、解約しない限りは保障が続きます。死亡保険の場合は被保険者が死亡または指定されている高度障害状態になった時に、保険金が支払われる仕組みです。
終身保険に加入していれば、遺族の年齢や家族構成などに関係なく保険金が支払われるため、残された家族の経済的な負担を軽減できます。遺族年金を受け取れない可能性がある場合や、金額に不安がある場合は、万が一の備えとして加入を検討しましょう。
④定期保険
定期保険も死亡保険の1つですが、終身保険と異なり保険期間が決まっています。定期保険には10年や15年などの期間が設定されている場合と、60歳までや70歳までの年齢で区切られている場合があります。
定期保険の期間中に死亡または指定されている高度障害状態になった時に、保険金が支払われる仕組みです。終身保険と比較して、安い保険料で保障を得られるため、生活スタイルに合わせて加入を検討しやすい保険です。
⑤個人年金保険
個人年金保険は国民年金などとは別に上乗せをする、個人で用意する年金です。毎月の保険料を一定年齢まで支払いを続け、受給開始時期になると年金として受け取れる仕組みです。もし、保険料払込期間中や年金据置期間中に亡くなった場合、払い込んだ保険料相当額を死亡保険金として受け取れます。保険を契約する際に死亡保険金の受取人を指定できるため、遺族のためにお金を残しておけます。
まとめ
遺族年金の概要や受け取る条件、受給額についてご紹介しました。遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つがあり、職業によって受け取れる年金の種類は異なります。遺族基礎年金は亡くなった人と生計を同じくしていた子のある配偶者または子が、遺族厚生年金は亡くなった人の子のない配偶者や父母も受け取れるなど、受け取れる人の条件異なります。
また、受給額も異なるため、自身の場合はいくらもらえるのか事前に計算しましょう。もし、遺族年金を受け取れない、受け取る金額に不安がある人は別の年金や保険の用意などをご検討ください。