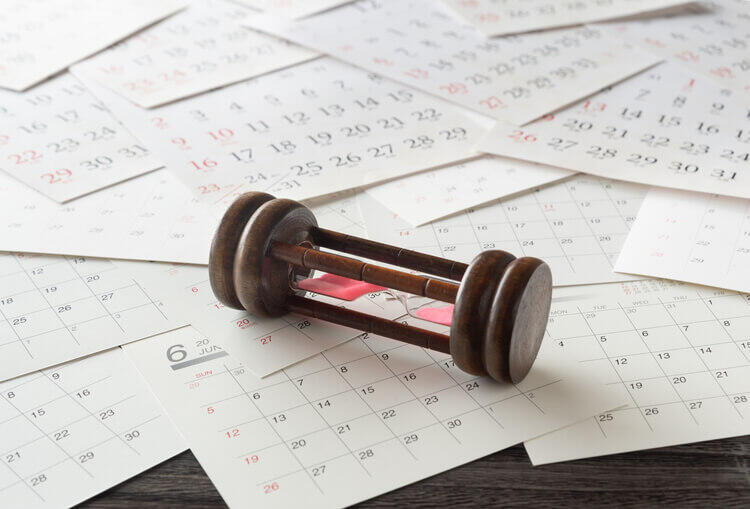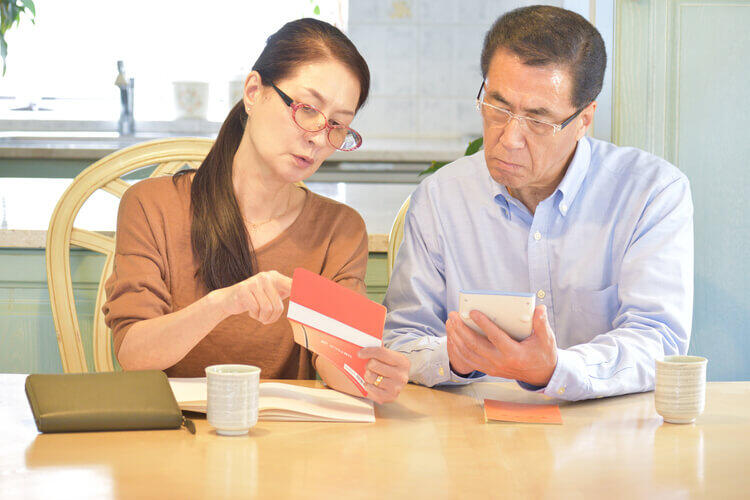相続でもめる可能性は高い!?相続でよくあるトラブルの原因や対応策についてご紹介
- ライフプラン・人生設計
- 公開日:2025年7月 4日

「相続でもめそうなことに関する意識調査」で、4割の人が相続でもめる可能性があると回答しました。今回は相続でよくあるトラブルの内容から、対策について解説します。相続について不安がある方は、ぜひ最後までご一読ください。
この記事の目次
相続でもめる可能性がある人は約4割
AlbaLinkが2025年3月26日~31日に実施した「相続でもめそうなことに関する意識調査」で、30代以上の男女500人のうち約4割は相続でもめる可能性があると回答しました。特に誰ともめる可能性が高いか?という質問に対しては、「兄弟姉妹」が多く、次に「兄弟姉妹の配偶者」という回答が多く挙げられています。
また、相続でもめそうな内容について、「不動産の取り扱い」と回答した人が47.0%、「納得感のある財産分与」と回答した人が34.0%でした。不動産を所有している親族がいる場合、その取り扱いについて心配している人が多くいることが分かります。その他、誰が手続きを進めるのか、費用分担はどうするのかなど相続に関する不安は多岐にわたります。
相続は遺産の金額が高いほどもめるイメージがありますが、実は金額はあまり関係ありません。遺産が1,000万円以下であっても、裁判になるケースも。また、遺産が借金などマイナスの財産の場合でも、処分をどのようにするかでもめる可能性があります。
相続でもめる原因になることとは?
親族・兄弟の仲が悪い
元々、親族・兄弟の仲が悪い場合、相続でもめる確率は高くなります。遺産の分割は話し合いによって決まることが多いですが、関係者の仲が悪い場合は意見が合わずにトラブルになる場合があります。よくあるトラブルの内容としては、話し合いを拒否される、意見が合わずに決着がつかない、感情的になって話が進まないなどです。
遺産が実家のみ
遺産が実家の不動産のみの場合も、もめる可能性が高くなります。遺産が実家しかない状態で実家に住み続けたい相続人がいると、実家を売却して分割することができません。この場合は他の相続人は相続ができなくなり、不公平が生じるためにもめてしまいます。
また、家を取得する際は代償分割か、売却して現金清算をするかによって意見が対立する可能性があるでしょう。代償分割を選択した場合でも、代償金の額で意見が分かれてしまい、もめるケースもあります。
遺産の中に不動産が複数ある
遺産の中に不動産が複数ある場合、誰がどの不動産を取得するのか、評価方法をどうするのかで意見が対立する可能性があります。売却をする際も、代償分割か換価分割にするかで意見が衝突し、話し合いが長引くことも。不動産は現金のように簡単に分けられないため、相続の際はもめる確率が高くなりやすいでしょう。
被相続人に内縁関係の配偶者や認知していない子どもがいる
婚姻関係や認知されていない人は、遺言書に記載がない限り相続権は発生しません。そのため内縁の配偶者が法定相続人である子どもから、家を立ち退くように要求されて住まいを失う、資産がなくなってしまい生活に困るなどのトラブルが起こる可能性があります。
高額な生前贈与された相続人がいる
生前贈与が行われた相続人には、特別受益が認められます。特別受益と認められると、生前贈与された財産を相続財産に持ち戻し、遺産分割を行う必要があります。しかし、被相続人が特別受益の持ち戻し計算を免除した場合、他の相続人と遺産の配分でもめるでしょう。持ち戻し計算を行う場合でも、いつ・どのくらい贈与されたかがわからず金額でもめる場合もあります。
介護の負担割合が偏っている
被相続人の介護を特定の人だけが行っていた場合、介護に参加しなかった兄弟ともめることがあります。介護を献身的に行っていた人には相続の寄与分が認められ、法定相続分よりも多めに遺産相続が可能です。しかし、他の相続人が寄与分の相続を認めず、調停などに発展する可能性も。
事業継承の問題がある
被相続人が事業を行っていた場合、誰が相続をするのかでもめることもあります。事前に後継者を指定し、育成を行っている場合は問題ないでしょう。しかし、突然事業を継ぐ必要が出てきた場合、親族で意見が割れる可能性があります。
遺産分割がスムーズに進まないと事業に必要な株式などの承継が進まず、会社の経営ができなくなることも。被相続人が事業を行っている場合は、事前に対策を取っておかないと会社がなくなる可能性もあるでしょう。
遺言書があっても相続でもめる可能性がある!?
相続でもめないために、遺言書の作成は効果的です。しかし、ただ作っただけでは効力がなく、トラブルが発生する場合もあります。
遺留分侵害が発生している
遺留分とは一定の相続人に保証されている、相続での最低限の取り分のことです。被相続人との関係性によって、以下のように変化します。
• 配偶者または子が相続人の場合:2分の1
• 直系尊属のみが相続人の場合:3分の1
• 兄弟姉妹などの場合:遺留分なし
相続人が複数いる場合は、上記の数字に法定相続分を乗じて割合を出します。もし夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続する場合は妻が4分の1、子どもが8分の1ずつを相続します。
遺言書で、遺産は全て長男に相続させるといった内容自体は有効にはなりますが、残った親族から「遺留分侵害額請求」が行われる可能性があるでしょう。もし遺留分侵害額請求が行われたら、請求された側はした側に対して、侵害額相当のお金の支払いが必要です。
遺言書の無効を主張された
遺言書は法律で決まった書き方でない場合、無効と主張される可能性があります。特に自筆証書遺言は、要件を満たしていなかったり内容に不備があったりすると、有効性が認められないこともあるでしょう。
また、公正証書遺言でも有効性に疑問を持たれることがあります。遺言能力が疑われる場合や、証人が条件を満たしていなかったとされる場合です。遺言書を作成していても、無効であるとされれば意味がありません。
遺言書の内容があいまい
遺言書の内容があいまいだと、トラブルの原因になります。例えば「神奈川にある倉庫を長男に相続させる。」といった内容が記載されていた場合、対象物件が特定できないとして効力が認められない可能性があります。
また、登記申請が拒否されることがあれば、相続はスムーズに進みません。具体的な内容を記載せず、伝わるだろうで遺言書に記載をすると問題の原因になります。遺言書を作成する際は、あいまいな表現を避けて書く必要があるでしょう。
家族以外の人に寄贈を指定している
家族・親族以外の相続権がない人にも、遺言書を通して財産を残すことが可能です。しかし、家族ではない友人や法人に遺産を渡す遺贈を行うと、家族もめる可能性があります。遺贈を行う場合は、なぜ行うのかを明記しておくと家族からの不満を減らせるでしょう。
遺産分割後に遺言書が見つかった
親族での遺産分割が決まった後に遺言書が見つかった場合は、基本的に遺産分割協議で決めた内容は無効となります。しかし、発見されるまでの間に不動産や資産を売却していると、権利関係に変化が出てしまいます。裁判で争うこともあり、時間とお金を費やすことになるでしょう。死後にもめる可能性を減らすためには、すぐに遺言書が見つかるように手配をしておくと安心です。
また、もし相続人の全員が合意すれば、遺言書とは別の方法での遺産分割が可能です。遺産分割協議を認めないような内容が記載されていなければ、遺言書の内容の通りではなく分割協議で決めた内容のまま遺産分割ができるでしょう。
相続でもめないための対策

相続でもめないためには、事前の対策が重要です。制度の活用や専門家への相談で、スムーズな相続が行われるように準備をしましょう。
生前からよく話し合う
関係者全員が生きている時から、よく話し合いをしておきましょう。被相続人が相続についてどのように考えているか、希望を推定相続人に伝えておくと考えに沿ってスムーズに遺産分割が行えます。また、遺産の内容や管理方法なども、親族間で共有しておきましょう。日頃からコミュニケーションを取っておくと、相続の際にもめる可能性は減らせます。
家族信託を利用する
家族信託は将来財産を管理できなくなった時に備えて、信頼できる家族や第三者に財産の管理や処分を依頼する制度です。認知症などで判断能力が低下した時でも、資産を柔軟に管理できます。死後の財産管理や帰属先を決められるので、相続対策としても有効です。
法的に有効な遺言書を作成する
相続トラブルを回避するためには、法的に有効な遺言書を作成しましょう。遺言書には3種類あります。
• 自筆証書遺言:遺言の全文や日付、氏名を手書きで行う。押印が必要
• 公正証書遺言:公正人が作成、保管をする
• 秘密証書遺言:公正役場で手続きをするが、内容は公正人に知らせずに作成する
自筆証書遺言は自宅で費用をかけずに作れますが、法的な形式に則っていないと無効になる可能性があります。法的に有効な遺言書として認められるのは、公正役場で手続きを行う公正証書遺言と秘密証書遺言です。相続トラブルを回避するのなら、公正役場で遺言書を作成しましょう。
後見人制度を使う
成年後見制度は、本人に代わって後見人が財産管理を行う制度です。成年後見制度には任意後見制度と、法定後見制度の2種類があります。元気なうちであれば、自身が選んだ人を後見人として財産管理を任せる任意後見制度が利用できます。認知症などで判断能力が低下した場合は、裁判所へ申立てを行い法定後見制度を利用しましょう。
専門家へ相談する
相続でもめる可能性が高い遺産がある、兄弟間の仲が悪く相続に不安があるなどの場合は専門家へ相談しましょう。生前からできる対策や遺言書の書き方など、解決策をアドバイスしてもらえます。相続でもめないよう、なるべく元気なうちから対策を行いましょう。
相続でもめたら弁護士に相談する
もし相続でもめた場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼をすると、相続人同士での話し合いを依頼できる代理交渉や、家庭裁判所での調停・審判なども対応してもらえます。
専門家であり第三者が間に入るため、冷静にストレスなく話し合いを進められるほか、法的に有効な主張であるかも確認してもらえます。当事者同士の話し合いがこじれそうな場合は、弁護士に依頼をして交渉や家庭裁判所での手続きを進めてもらいましょう。
まとめ
相続でもめる可能性が高い点や、よくあるトラブルについて解説しました。相続の際には遺産の内容はもちろん、親族の仲が関係し、話し合いがまとまらないことがあります。特に不動産を複数所持している場合や、複数の相続人に対して実家しか遺産がない場合などは、トラブルになりやすいでしょう。
遺言書を作成している場合でも、法的に有効な形式でない場合は相続時にもめることになってしまいます。少しでもスムーズに相続を進めるためには、法的に有効な遺言書の作成と、専門家への相談を元気なうちから行っておきましょう。