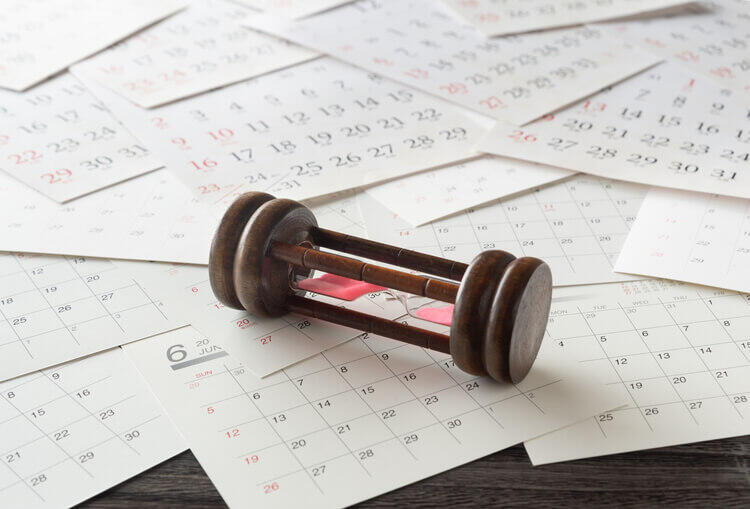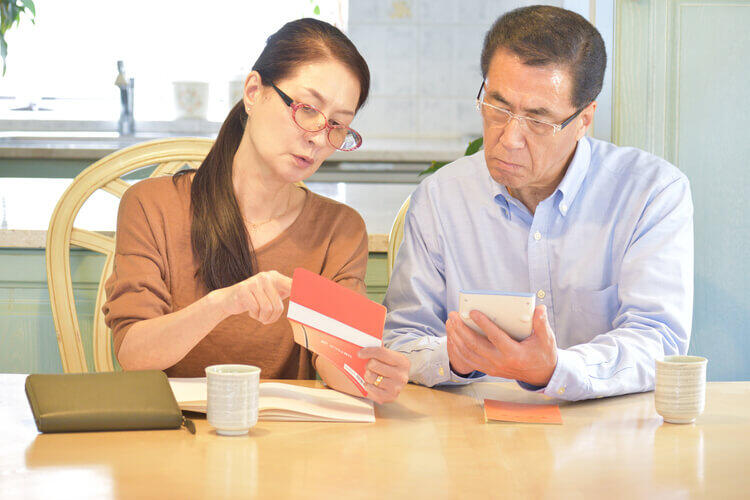生前贈与はいくらまで非課税?制度の概要やメリット、デメリット、手続き方法・使い道などもご紹介
- ライフプラン・人生設計
- 公開日:2025年3月31日

子供や孫に資産を残せる生前贈与について、気になっている人は多いでしょう。相続対策にもつながる生前贈与を検討しているミドルシニア世代に向けて、生前贈与の概要からメリット・デメリット、手続きなどをご紹介。また、節税につながる制度も解説します。
この記事の目次
生前贈与とは
生前贈与とは、死後に引き継ぎが発生する相続とは異なり、自身が存命中に子供や孫などに対して自身の財産を贈与することです。生前贈与には、暦年贈与と相続時精算課税制度の2つがあります。それぞれ対象や非課税枠が異なるため、贈与の際には違いを理解した上で活用しましょう。
| 暦年贈与 | 相続時精算課税制度 | |
| 非課税枠 | 年間110万円 | 累計2,500万円+年間110万円 |
| 対象 | 1月1日〜12月31日までの1年間に行われた贈与 | 原則60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子供・孫への贈与 |
| 税務署への申告 | 1月1日〜12月31日までの1年間に行われた贈与 | 年間110万円までなら不要 基礎控除分以外は必要 |
暦年贈与
年間110万円までであれば非課税で利用できます。贈与額が110万円を超えた場合は、超えた部分の金額に対して贈与税が発生します。注意するべき点は、非課税枠の110万円は受贈者1人あたりの金額である点です。
例えば、父親から110万円を受け取り、それ以外の家族からの贈与がなかった場合は、贈与税は発生しません。しかし、同じ年に父親からも祖父からも110万円ずつ贈与された場合は、220万円の内の110万円が課税対象となります。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度の非課税額は、累計2,500万円のため1回で使い切る必要はありません。残額を翌年以降に繰り越せるため、数年にわたって贈与を行うことができます。また、2024年からは年間110万円の基礎控除が設けられており、その分については贈与税の申告は不要です。相続時精算課税制度で贈与した財産は、贈与者が死亡したときに贈与時の価格で相続税の課税対象となります。
現金を贈与する場合や相続をする人の年齢が若い場合には暦年贈与を、収益のある不動産や将来の値上がりが見込まれる財産の贈与には、相続時精算課税制度を検討してみましょう。
生前贈与のメリット
生前贈与にはどのようなメリットがあるのか、通常の相続よりもメリットとなる点はどこかについてご紹介します。
相続時の税負担が軽くなる
生前贈与を活用すると、相続時の財産が減るため相続税の負担を軽くできます。相続税の基礎控除の計算は、3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)です。もし、法定相続人が2人の場合は、基礎控除額は4,800万円です。生前贈与を活用して少しずつ財産を、基礎控除の4,800万円と同等もしくは、それ以下になるようにしておくと相続税を最小限に抑えられます。
特定の時期や人に贈与ができる
生前贈与は特定の財産を特定の人に贈与させたい、この時期に贈与したいなどの希望を叶えられます。相続でも遺言書を通して相続人と財産の指定はできますが、もし他の遺族が満足しなければトラブルとなります。遺言書の作成ができなければ、意図していなかった人に財産が渡る可能性もあるでしょう。相続のトラブルを減らし、自身が希望する人に財産を渡せるのは、生前贈与のメリットです。
減税効果が累積する
生前贈与には相続時の税額負担を減らせるのはもちろん、さまざまな減税制度が用意されています。住宅購入時や結婚など、大きな出費の際に利用すれば、非課税で贈与できるでしょう。財産の譲渡を税金の負担を減らして、スムーズに行えるのは嬉しいポイントです。

生前贈与のデメリット
複数の非課税枠が用意されている生前贈与にもデメリットがあります。非課税枠が適用されない場合や、生前贈与と認められない場合がある点についてご紹介します。
110万円の非課税枠が適用されない場合がある
暦年贈与を選択して、毎年基礎控除の110万円以内で贈与をしていた場合、原則贈与税は非課税です。しかし、定期贈与とみなされた場合は110万円以内でも、贈与税が発生する場合があります。
定期贈与とは、あらかじめ決めた一定額の財産を定期的に分割して贈与する方法です。1,000万円の財産を毎年100万円ずつ贈与した場合は、定期贈与とみなされる可能性があります。定期贈与とされないためには、贈与が発生するごとに贈与契約書を作成しましょう。
死亡前の一定期間の贈与は相続税の課税対象となる
生前贈与をしていても、贈与した時期によっては相続税の課税対象となります。以前までは相続開始3年以内の生前贈与が、相続財産の対象となっていました。しかし、2024年からは相続開始7年以内の生前贈与が対象に変更となりました。
現在は経過措置が設けられており、死亡3年以内もしくは、2024年に贈与された財産が相続税の対象となります。ただし、2031年以降からは、死亡7年以内の生前贈与が相続税の課税対象へと変更されます。
生前贈与の節税効果
生前贈与には、暦年贈与や相続時精算課税制度以外にも、節税となる制度が用意されています。以下では、4つの制度について解説します。
夫婦間での不動産贈与
夫婦間で居住用の不動産を贈与した時に利用できる、配偶者控除があります。自宅の贈与はもちろん、自宅を取得する際の費用も贈与の対象です。基礎控除の110万円も併せて利用できるため、最高で2,110万円までが非課税で利用できます。ただし、利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
• 居住用不動産または居住用不動産を購入するための資金の贈与
• 婚姻期間が20年以上の夫婦
• 同一の夫婦間で初めての利用
• 贈与の翌年3月15日までに贈与を行った不動産または贈与資金で購入した不動産に住んでおり、将来も住み続ける
贈与を行った後は、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告書の提出が必要です。
住宅取得資金の贈与
子供や孫が住宅を購入する際に、親や祖父母から資金援助を受ける場合は、住宅取得等資金贈与の非課税の特例を利用できます。住宅の購入はもちろん、リフォームに関する資金援助も一定額までが非課税の対象です。
2026年12月31日までが対象となっており、質の高い住宅は1,000万円、一般住宅は500万円までが非課税です。質の高い住宅とは、省エネ性能のある住宅などが該当します。ただし、贈与を受けた人の合計所得が2,000万円以下や、床面積が50m2以上などの条件が設けられています。
教育資金一括贈与
子供や孫の教育資金を一括で贈与する場合、教育資金の一括贈与の非課税制度が利用できます。受贈者が30歳未満の場合に、最大1,500万円が2026年3月31日までは、非課税となる制度です。
ただし、学校教育法上の教育施設や外国の教育施設に、直接費用を支払う費用の場合は500万円までが非課税の対象となります。もし、贈与された財産を教育資金以外で利用した場合や、受贈者が30歳時点で贈与された金額が残っていた場合は、贈与税の支払いが必要です。
結婚・子育て資金の一括贈与
子供の結婚や孫の誕生によって、資金を一括贈与する場合は、受贈者1人あたり1,000万円までが非課税となります。そのうち、結婚資金は300万円が上限です。
対象となるのは、18歳以上50歳未満の子供や孫で、受贈者名義の金融機関の口座等に結婚・子育て資金を一括して拠出します。結婚や子育て資金の場合は、使途を領収書などで金融機関が確認し、書類で保管されます。

生前相続の流れや手続きについて
生前贈与を利用したいがどのような流れで行うのか、必要な手続きについて不安な人もいるでしょう。まずは、生前贈与の流れについて解説します。
1. 贈与する財産や相手を決める
2. 贈与契約書を作成する
3. 財産を贈与する
4. 贈与税の申告を行う
生前贈与の際は後から問題が起きないように、贈与が起こったタイミングで都度、贈与契約書を作成しましょう。贈与者と受贈者で同意があったと証明できるものがあれば、トラブルを回避できます。
また、贈与する財産の種類によっては、名義変更などの手続きが必要です。不動産を贈与する場合は、登記申請書や対象不動産の登記済権利証などを持って名義変更を行いましょう。そのほか、贈与税が発生する場合は、税務署への申告と納付が必要になります。
生前贈与のポイント
生前贈与のポイントについて、3つご紹介します。自身の財産や周囲との関係なども考慮して、最適な方法をご検討ください。
多くの人に贈与する
生前贈与は多くの人に贈与すると、税額が変わってきます。贈与税は累進課税制度が採用されているため、1人の人に大きな金額を贈与すると税率が高くなる仕組みです。例えば、1人に1,000万円を贈与すると税率は30%となり、非常に高額になります。
暦年贈与を活用
暦年贈与は、年間110万円まで非課税で贈与ができます。毎年110万円の贈与を行うと、10年間で1,100万円を非課税で贈与可能です。少しでも税金の負担を抑えたいのなら、積極的に暦年贈与を活用しましょう。ただし、定期贈与とみなされると110万円以下でも課税される可能性がある点は、理解しておきましょう。
相続トラブルの回避に
生前贈与は自身が生きている間に財産を指定した人に渡せるため、相続時のトラブル回避につながります。例えば、自宅は配偶者に贈与し、現金などの財産を子供に贈与したいなども、自分の意思で実行できます。
また、財産は少ないけれど遺言での相続には不安がある場合も、自分が決めた人に財産を渡すところを確認できる生前贈与はメリットとなるでしょう。少しでも相続時のトラブルを回避させるためには、生前贈与も活用しましょう。
まとめ
生前贈与の制度やメリット・デメリット、手続きなどについて解説しました。生前贈与は相続と異なり、自身が生きている間に指定した人物に資産を譲渡できる制度です。年間で110万円の基礎控除が用意されているほか、相続時精算課税制度を利用すると、累計で2,500万円まで非課税です。
そのほか、配偶者や子供の住宅購入費用のための贈与に関する非課税制度も用意されています。生前贈与は相続時のトラブル回避ができるほか、相続税の負担軽減にもつながるなどメリットもあります。ぜひ、家庭の資産状況に応じて生前贈与を行いましょう。