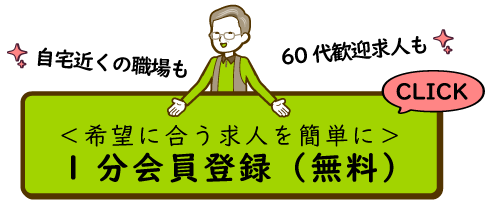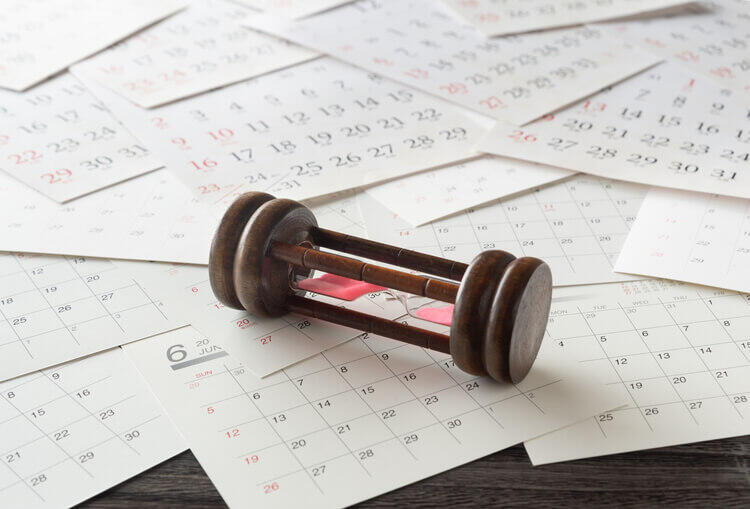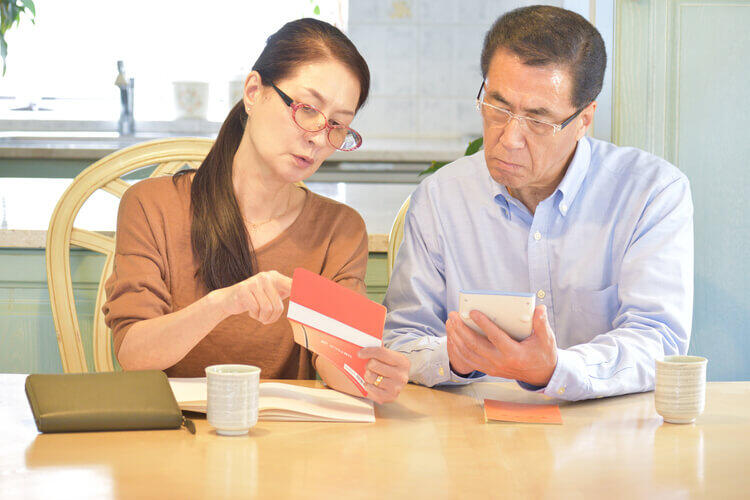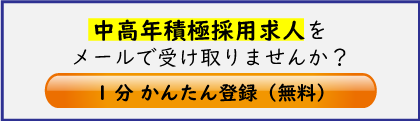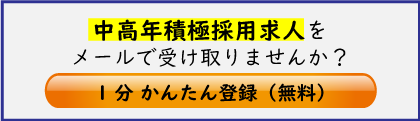老後にかかる医療費が心配!定年後の自己負担額や保険適用外の医療費目安も紹介
- ライフプラン・人生設計
- 公開日:2025年6月 6日

生活費や介護費用、医療費など、老後のお金に関する不安を抱えている人は多いでしょう。今回は老後にかかる医療費についてのほか、保険適用外の医療の自己負担額、将来備えておきたい医療費の目安についてご紹介します。また、医療費をおさえる制度や今から将来に向けて備えておく方法も解説していますので、老後の医療費について心配な人はぜひご一読ください。
この記事の目次
老後に必要な医療費
厚生労働省の「生涯医療費(令和3年度)」によると、日本人の生涯医療費は2,800万円です。定年退職後の65歳からは1,604万円と、生涯医療費の半分以上が定年以降に必要となります。そのため、老後に向けて生活費のほかに医療費も用意しておかないと、いざという時に支払いができなくなる可能性があります。
また、年齢階級別の1人当たり医療費の自己負担額も確認してみましょう。
| 年齢 | 自己負担額 |
|---|---|
| 55〜59歳 | 62,814円 |
| 60〜64歳 | 76,015円 |
| 65〜69歳 | 86,208円 |
| 70〜74歳 | 72,229円 |
| 75〜79歳 | 65,474円 |
| 80〜84歳 | 74,053円 |
| 85〜89歳 | 80,741円 |
| 90〜94歳 | 83,935円 |
| 95〜99歳 | 82,123円 |
| 100歳以上 | 76,748円 |
参照元:厚生労働省「医療保険に関する基礎資料(令和3年)」
医療費の負担が増える高齢の時期でも、健康保険に加入しているため、自己負担額はあまり大きくありません。上記の自己負担額を月平均にしてみると、どの年代でも月額5,000円〜7,000円代になります。公的医療保険が適用されている場合は、問題なく自己負担額を支払えるでしょう。
保険適用外の医療費について
公的医療保険の適用外となる治療やサービスを受けた場合は、全額自己負担になります。生命保険文化センターの「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」によると、入院した際の平均日数は17.7日で、自己負担額費用の平均19.8万円です。ただし、病気や怪我の種類によって、必要な入院日数や治療費は異なります。
例えば、悪性新生物(がん)で入院した場合と、骨折で入院した場合の自己負担額は下記の通りです。
| 悪性新生物(がん) | 骨折 | |
| 1日当たりの診療費(一般協会) ※1 | 83,045円 | 54,392円 |
| 平均在院日数(65歳以上) ※2 | 15.5日 | 42.0日 |
| 総診療費 | 1,287,197円 | 2,284,464円 |
| 診療費の自己負担額(一般所得者) ※3 | 57,600円 | 115,200円 |
| 保険適用外サービス (差額ベット代 ※4+食事代 ※5) |
7,110円×15.5日=110,205円 | 7,110円×42.0日=298,620円 |
| 総自己負担額 | 167,805円 | 413,820円 |
※1 厚生労働省「医療給付実態調査 報告書 2022年度」
※2 厚生労働省「患者調査 令和5年度」
※3 厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」
※4 厚生労働省「主な選定療養に係る報告状況 令和4年7月1日現在」
※5 厚生労働省「入院時の食費について」
医療費に関して、このくらいのお金があれば大丈夫という、絶対的な金額はありません。しかし、高齢になれば入院日数が長くなるため、自己負担額は多くなっていきます。シミュレーションの金額を参考に、将来の医療費を備えておきましょう。
老後の医療費としていくら準備するべきか

老後の入院で必要となる平均額は、20万円前後です。そのため生活費とは別に、20万円ほどの医療費を用意しておきましょう。また、通院をする場合は入院費用とは別に用意しておくと、万が一の時に安心です。
しかし、定年退職後の年金だけでは、生活費と医療費の両方を用意するのは難しいでしょう。年金の平均支給額は月14.6万円です。老後の生活に必要な最低限の生活は月で平均23.2万円とされており、8.6万の赤字です。そこに医療費や介護費用などが加算されるため、年金だけでは老後の生活は厳しくなります。
医療費の自己負担額を減らすために利用できる制度
医療費は公的制度などを利用すると、自己負担額を減らせる場合があります。高額な医療費の負担を少しでも減らすために、以下の3つの方法を知っておきましょう。
医療保険への加入
医療保険に加入していると、公的医療保険の対象にはならない先進医療費や差額ベッド代などのお金をカバーできます。医療保険は一生涯保障する終身型と、一定期間保障する定期型に分かれており、特定の疾病に特化した商品や医療に関する全般に対応したものがあります。
保障も入院1日当たり1万円といった日額型と、実際の費用を保障する実費型があるため、自身の希望に応じて検討しましょう。ただし、医療保険は高齢になるほど保険料が高くなる傾向にあるため、本当に必要な保障だけを選ぶ必要があります。受け取れる年金の額が少ない、将来の貯蓄が足りない可能性がある人は、医療保険への加入をご検討ください。
高額療養費制度
高額療養費制度は、月の限度額を超える医療費を支払った場合に、公的医療保険制度が超えた分を負担する制度です。日本の公的医療保険制度では、自己負担は医療費の3割と決まっています。つまり100万円の医療費が発生した場合、自己負担額は30万円です。
しかし、あまりにも医療費が高額だと、3割の自己負担でも家計に大きな影響を与える可能性があります。そのため一定額を超えた分は、払い戻しを行って負担の軽減を行っています。高額療養費制度の患者負担割合と自己負担額は年齢によって異なります。
▼70歳未満
| 年収 | 負担割合 | 月の上限額 |
|---|---|---|
| ■年収約770〜1,160万円 ■健保:標報53〜79万円以上 ■国保:旧ただし書き所得600〜901万円超 |
3割 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% (多数回該当:140,100円) |
| ■年収約1,160万円〜 ■健保:標報83万円以上 ■国保:旧ただし書き所得901万円超 |
3割 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% (多数回該当:93,000円) |
| ■年収約370〜770万円 ■健保:標報28〜50万円以上 ■国保:旧ただし書き所得210〜600万円超 |
3割 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% (多数回該当:44,400円) |
| ■〜年収約370万円 ■健保:標報26万円以上 ■国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
3割 | 57,600円 (多数回該当:44,400円) |
| ■住民税非課税 | 3割 | 35,400円 (多数回該当:24,600円) |
▼70〜74歳未満
| 年収 | 負担割合 | 月の上限額(外来個人ごと) | 月の上限額 |
|---|---|---|---|
| ■年収約370万円〜 ■健保:標報28万円以上 ■国保:課税所得145万円以上 |
3割 | 44,400円 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% |
| ■〜年収約370万円 ■健保:標報26万円以下 ■国保:課税所得145万円未満 |
2割 | 12,000円 | 44,400円 |
| ■年収約370〜770万円 ■健保:標報28〜50万円以上 ■国保:旧ただし書き所得210〜600万円超 |
2割 | 8,000円 | 24,600円 |
| ■〜年収約370万円 ■健保:標報26万円以上 ■国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
2割 | 8,000円 | 15,000円 |
▼75歳以降
| 年収 | 負担割合 |
月の上限額 |
月の上限額 |
|---|---|---|---|
| ■年収約370万円〜 ■課税所得145万円以上 |
3割 | 44,400円 | 44,400円 |
| ■〜年収約370万円 ■課税所得145万円未満 |
1割 | 12,000円 | 44,400円 |
| ■住民税非課税 | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
| ■住民税非課税(所得が一定以下) | 1割 | 8,000円 | 15,000円 |
参照元:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」
一度窓口で医療費を全額支払う必要はありますが、上限額を超えた分が還付されるのは嬉しい制度です。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は75歳以上もしくは、65歳〜74歳までで一定の障害状態にある人が加入する医療保険です。医療費は69歳までは3割負担、70〜74歳は2割負担ですが、後期高齢者医療制度の被保険者になると、現役並み所得者以外は1割負担になります。
そのほか「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」を提示すると、入院時の食事代の負担が軽減されるほか、被保険者が死亡した際に葬儀を行った人へ葬祭費が支給されるなどの給付が用意されています。
75歳を迎えると自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きなどは特にありません。保険料は年金から天引きされるため、支払い忘れも起こらないでしょう。

老後の医療費に備える方法
老後の医療費や生活費を、年金だけで補うのは難しいでしょう。少しでも老後のお金に対する不安をなくすためには、早いうちから貯蓄や投資を活用して備えておきましょう。
貯蓄
老後の医療費や生活費の負担を減らすには、貯蓄を行いましょう。貯蓄をする際は、ただお金を貯めるのではなく、目的や目標額を決めると続けやすくなります。例えば、老後の生活や病気に備えるために、3年後までに300万円貯めるなどです。
目標や目的を決めたら、家計の見直しで収入と支出を確認し、毎月の貯蓄額を設定します。この時、目標金額に届かないからといって、無理な貯蓄をしようとするのはやめましょう。生活を切り詰めるような、無理な貯蓄は長続きしません。まずは目標を意識しつつ、無理のない範囲でコツコツと続けていきましょう。
iDeCo
iDeCoは個人型確定拠出年金で、公的年金とは別に、自分自身で用意をする年金制度です。自身で掛金を拠出し、運用商品を選定・運用します。通常、投資によって得た利益には税が加算されますが、iDeCoの場合は運用によって得た利益を、非課税で受け取れる税制優遇が用意されているのが特徴です。
ただし、運用益を引き出せるのは、原則60歳になってからと決まっています。そのため、老後に向けた資金を作りたい人におすすめです。
NISA
NISAは少額投資非課税制度で、つみたて投資枠と成長投資枠を活用しながら年間360万円まで投資ができる制度です。長期の積立や分散投資に適した商品などもあり、コツコツと資産形成をしたい人に向いています。
iDeCoと同様に、運用や受け取り時に発生する税金が非課税となるのも魅力です。一方でNISAの場合はiDeCoとは異なり、途中での引き出しも可能なため、それぞれの目的に応じた資産形成がしやすくなっています。
もし医療費の支払いができない時は
どうしても医療費の支払いが難しくなった場合は、以下の方法をご検討ください。
• 病院や医師に相談
• 分割支払い
• 公的制度を利用する
病院には医療費に関する相談窓口が用意されているため、少しでもお金に不安を感じたらまず相談しましょう。場合によっては、費用が安くなる方法がないか考えてくれる可能性もあります。また相談の際には、分割支払いに対応しているかも確認しましょう。病院によっては、医療費を分割で支払える場合があります。
病院へ相談をしたが、どうしても支払いが厳しい場合は、公的制度の利用も検討しましょう。高額療養費貸付制度や、付加給付制度など、医療費の負担を軽減させるための制度が用意されています。加入している健康保険組合によっても、利用できる制度は異なるため、よく確認しておきましょう。
まとめ
老後に必要となる医療費の自己負担額や、自己負担額を減らすための方法についてご紹介しました。公的医療保険が適用される場合、老後の自己負担額は6〜8万円ほどとさほど高くありません。しかし、保険が適用されない治療やサービスを利用すると、自己負担額は大幅に増える可能性もあります。
少しでも医療費に関する不安を減らすためには、将来のための資産形成はもちろん、医療保険などの加入で備えておきましょう。また、利用できる公的制度についても事前に調べておくと、安心して生活を送れるでしょう。