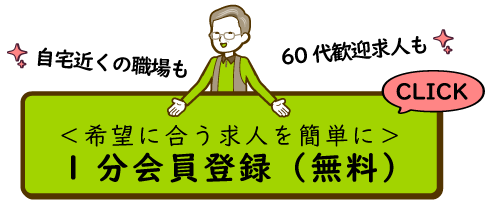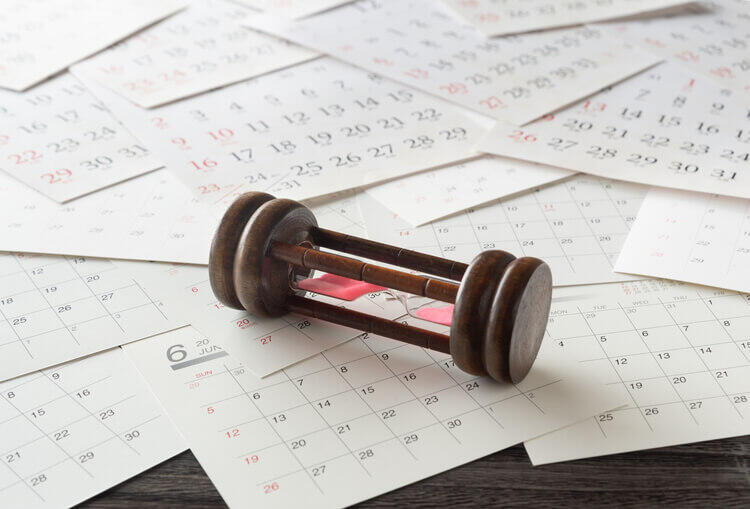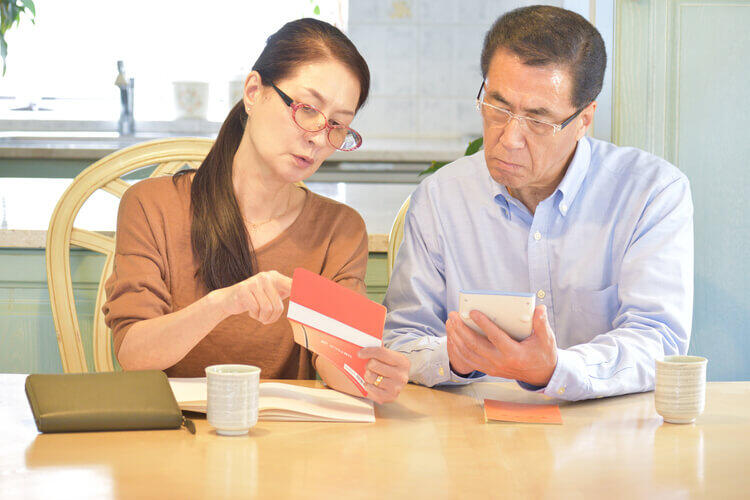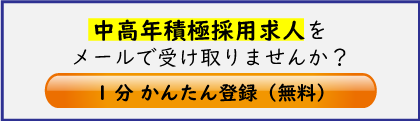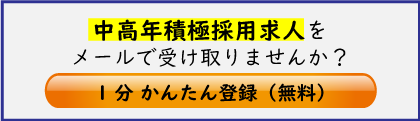2024年10月から年金が増えるって本当?在職定時改定で増える人・減る人、収入別シミュレーションもご紹介
- ライフプラン・人生設計
- 公開日:2024年12月 6日

令和4年から開始した在職定時改定制度は、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年10月に改定し、過去に納めた保険料を年金額に反映させる仕組みの制度です。在職定時改定制度について、基本情報から年収別シミュレーション、注意点などを解説。また、在職定時改定後に再就職する際の確認ポイントも紹介します。
この記事の目次
在職定時改定制度で毎年年金額が改定される
在職定時改定制度とは、65歳以上で年金を受給しながら働き続けている人に対して、毎年定期的に年金額を改正していく制度です。
計算の対象となるのは、その年の9月1日に厚生年金保険被保険者である65歳以上70歳までの労働者で、基準日(9月1日)が属する月前の厚生年金保険加入記録によって改定が行われます。つまり、今年の9月1日時点で65歳となっている人は、今年の在職定時改定の対象ですが、9月1日以降に65歳となる人は来年から対象です。
在職定時改定制度の対象者
在職定時改定の対象となるのは厚生年金に加入している人です。フリーランスや自営業者など国民年金のみに加入している人は対象にはなりません。過去に厚生年金に加入していた期間があり、老齢厚生年金を受給していた場合は、定年退職後の働き方が自営業などでも対象になります。
在職定時改定が行われるのは70歳までのため、70歳以降の人は働いていても年金の増額はされません。
在職定時改定制度ができる前の制度
在職定時改定制度ができる前までは、年金額の改定は"退職時"と"70歳時"のみでした。たとえば、65歳以降も働き67歳で退職した場合、退職時に65歳以降に納付した厚生年金保険料が再計算され反映という流れです。
また、70歳以降も働き続けた場合は、70歳になった時点で、65歳以降に納付した厚生年金保険料が再計算され反映となります。つまり、65歳以降の働いている間は、定期的な年金額の変動はない仕組みとなっていました。
適用される年金
在職定時改定制度が適用されるのは、老齢厚生年金です。しかし、中には適用されない年金もあります。在職定時改定の対象外となる年金を確認してみましょう。
• 老齢基礎年金
• 65歳までの特別支給の老齢厚生年金
• 繰り下げ受給の老齢厚生年金の待機中
• 65歳以前に受給している繰り上げ受給中の老齢厚生年金
年金を60歳からの繰り上げ受給している場合は、その期間は在職定時改定が適用されません。在職定時改定は、65歳以降の老齢厚生年金に対して適用されます。
給与が高い人は在職定時改定で年金額が減る可能性がある
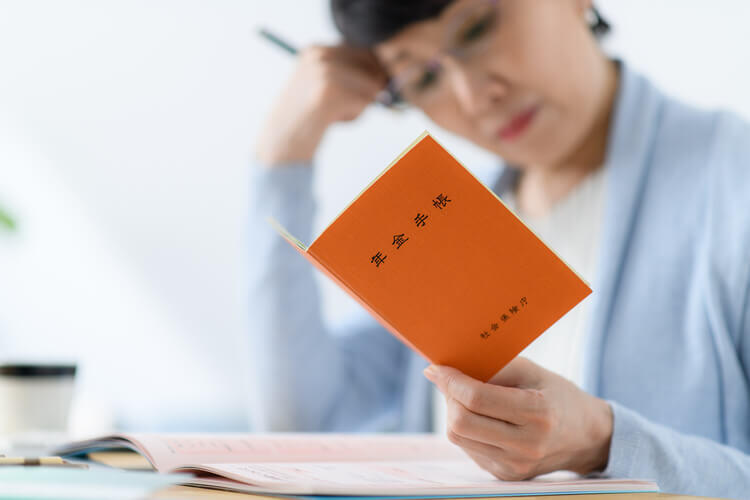
在職定時改定では、65歳から70歳までの厚生年金に加入している人の年金が増える場合が多いですが、場合によって減る可能性もあります。特に年金以上に給与が高い人の場合は、在職老齢年金によって一部の年金がカットされる場合があります。
年金がカットとなるのは、「年金額+給与収入=50万円超」の場合です。カットされた後の金額については、「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2」で求められます。
例えば、総報酬月額相当額が27万5,000円、老齢厚生年金が10万円の場合の、年金の支給状況と月の収入額は以下の金額となります。
総報酬月額相当額 27万5,000円 +老齢厚生年金 10万円=37万5,000円
50万円以下のため、全額受給ができます。また、これとは別に老齢基礎年金を毎月全額受給できます。しかし、総報酬月額相当額が50万円、老齢厚生年金が14万円だった場合は、以下の通りです。
総報酬月額相当額 50万+老齢厚生年金 14万円=64万円
月の収入が50万円超となるため、老齢厚生年金の7万円分が支給停止となり、実際には57万円となります。人によっては、老齢厚生年金の全額が支給停止となるでしょう。この時にカットとなった年金は、2度と受け取れません。
上記のように収入が高い人は、在職定時改定制度で年金額が増えても、在職老齢年金によって受給できる額が減る可能性があります。
なぜ在職定時改定制度が始まったのか
そもそも在職定時改定制度が始まった背景には、高齢者雇用の推進や少子高齢化などがあげられます。
在職定時改定制度の導入前は、65歳以降に老齢厚生年金が支給されていましたが、退職や70歳になって厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは、老齢厚生年金額は改定されませんでした。働き続けて毎月保険料を納めていても、受け取るのは70歳以降からとなっていたため、高齢者の就業意欲低下につながっていた面も。
現在では70歳までの継続雇用が努力義務となり、働きやすい環境を整えていかなければなりません。65歳から70歳までの期間も、モチベーションを上げて働いてもらうためには、現行の制度では不十分だったということです。
また、現在の少子高齢化の社会では、現行の年金制度の維持が難しく、担い手の負担が増加しています。今回の在職定時改定の導入によって、高齢者は働きながら年金の受給額を増やせるため、年金制度の維持や高齢者の雇用増加につながります。
在職中の労働による保険料納付が年金額に反映されるため、高齢者の就業意欲の向上につながる可能性がある制度だと言えるでしょう。
在職定時改定制度でいくら増額するのか
在職定時改定制度でいくら増額するのか、気になる方も多いでしょう。在職定時改定による年金の増額は、年収によって異なります。厚生年金に加入している年齢と、年収による増額は以下の通りです。
| 厚生年金加入年齢 | 年収200万円の時の増額 | 年収300万円の時の増額 | 年収400万円の時の増額 | 年収500万円の時の増額 | 年収600万円の時の増額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66歳まで | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 |
| 67歳まで | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円 |
| 68歳まで | 33,000円 | 49,500円 | 66,000円 | 82,500円 | 99,000円 |
| 69歳まで | 44,000円 | 66,000円 | 88,000円 | 110,000円 | 132,000円 |
| 70歳まで | 55,000円 | 82,500円 | 110,000円 | 137,500円 | 165,000円 |
年収が高くなると、年金の一部がカットまたは全額カットされる可能性があるため、在職老齢年金制度を考慮して収入を調整しましょう。
在職定時改定のメリット

在職定時改定の導入によって、受給者や企業にとって良い影響があります。どのようなメリットがあるのか、3つをご紹介します。
65歳以降の年金額が加算される
在職定時改定制度のメリットは、65歳から70歳以降に受給できる年金の額が、毎年増額することです。従来の制度では70歳まで働いていても、退職や70歳になって厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは、老齢厚生年金額は改定されませんでした。
しかし、在職定時改定によって、高齢者の経済基盤が充実していきます。安心して65歳以降も働けるのは、在職定時改定制度の魅力です。
従業員のモチベーションアップにつながる
企業側としては、在職期間中に年金の受給額が増加するため、従業員のモチベーションアップにつながる点はメリットです。従来までは働いている間は、保険料を支払っていても年金額が変わらなかったため、仕事へのモチベーションにつながりにくい環境でした。
しかし、在職定時改定によって定期的に年金が増額されるため、意欲的に働く人が増えるでしょう。
経験豊富な人材確保がしやすくなる
定年を迎えた経験豊富な人材を確保しやすくなる可能性があるのも、在職定時改定のメリットです。近年では企業側に対して、65歳までの継続雇用制度の導入や、70歳までの就業機会の確保の努力義務などが求められています。
そのため、企業側は積極的な高齢者の労働力確保を行う必要があります。在職定時改定によって労働期間中でも年金が増額されれば、豊富なスキルや経験を持った労働者が確保できる可能性が高まるでしょう。
在職定時改定の注意点
在職定時改定には、いくつか注意点もあります。せっかくの年金増額の機会を損しないためにも、どのような点に気を付けるべきか確認しましょう。
支給停止分には適用されない
在職老齢年金制度が適用され、年金の支給額が一部もしくは全額が停止された場合、減額や停止された金額に対しては、在職定時改定は適用されません。先述した通り、月の収入が50万円を超える場合、老齢厚生年金の支給が減額もしくは停止されます。また、減額された分は後から受け取ることはできません。
繰り下げ受給した場合に適用されない
年金の受給を75歳まで繰り下げた場合、繰り下げの基準は65歳時点の年金額です。もし、収入額が高く年金が調整された場合は、その金額が繰り下げの基準となります。今回の在職定時改定を選択した場合、65歳からの収入分、年金額も増額できるのではないかと考える人もいるでしょう。
しかし、繰り下げ受給を選択した時点で、その期間の年金の受け取りをしないという選択をしているため、在職定時改定は適用されません。結果的に、通常の65歳からの年金受給を選択した人よりも、受け取れる金額が少なくなる可能性も考えられます。
労働意欲低下のリスクがある
在職定時改定によって年金額が増加するため、労働意欲が高まる可能性がありますが、金額によっては反対に労働意欲を下げる場合があります。たとえば、年収が200万円の人は年間で11,000円が増加しますが、年収が400万円の場合は年間で22,000円です。人によっては思ったほど増額されず、退職を早めようと考える人も出るでしょう。
企業側は、少しでも労働意欲を維持させるために、高齢の労働者に対して福利厚生や人事制度などの見直しが必要となります。労働意欲の低下によって離職とならないよう、対策を取る必要がある点は企業側にとってデメリットです。
在職定時改定後に再就職する際の確認ポイント
在職定時改定は、定年後から70歳まで継続して働いてもらうためのモチベーションを上げることが役割の1つです。しかし、在職定時改定だけではなく、企業側でも高齢者が働きやすい環境作りが重要になります。定年後に就職をする際は、以下のような施策が充実しているか確認しましょう。
• 人事評価制度
• 昇給制度
• キャリアコースの導入
定年前と定年後では仕事をするうえで、求められる役割は異なります。定年後でも評価される制度や活躍できるコースがあれば、より労働意欲が高まります。少しでも長く働ける環境が整っているか、ぜひ就業前に確認しましょう。
まとめ
在職定時改定の基本情報や、年収別の増額シミュレーションなどをご紹介しました。在職定時改定は、65歳以上の人が働きながら年金を受給する際、毎年10月に年金額が改定される仕組みです。
従来では、退職時もしくは70歳時点にならないと改定されなかった年金額が、毎年改定されるため増額されるチャンスが広がりました。しかし、年収額によっては年金が一部または全額停止となるなど、損をする可能性もあるため事前に確認をしましょう。
在職定時改定は、高齢者が働きながらより経済基盤を安定させられる制度です。少しでも安心して暮らすためにも、自身は該当するのか、どの程度の金額が増額されるのか、ぜひ一度ご確認ください。